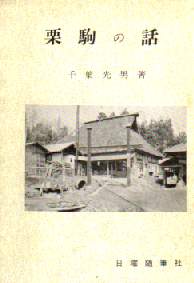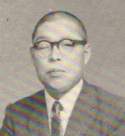 千葉光男氏(写真右)は、大正4年1月30日、栗駒村沼倉木鉢に生を受けた。その後、昭和19年栗駒村森林組合に勤めた。 千葉光男氏(写真右)は、大正4年1月30日、栗駒村沼倉木鉢に生を受けた。その後、昭和19年栗駒村森林組合に勤めた。
昭和27年には沼ケ森生産森林組合を設立して、杉や赤松などを植えた。その事業は、昭和43年までに、実に700ヘクタールの規模となった。その間、昭和30年には陛下ご臨席の下、緑化推進全国大会(宮城県黒川郡大衡村)が開催され、県知事より造林功労者として表彰を受けることとなった。昭和33年には社団法人栗駒愛林会を発起し、今日に至っている。 その傍ら、千葉光男氏は、地元栗駒の歴史に興味を持ち、元栗駒村村長菅原巳之吉氏の薫陶を受けながら、様々な地元栗駒の話を収集した。その成果は、栗駒町の史談会の各紙に発表され、好評を博した。昭和43年には、今回デジタル化が完了したこの「栗駒の話」が刊行された。「栗駒の話」には、素朴軽妙な筆致で語られる氏独特の世界が形成されている。そこには単に栗駒の一地域の昔話というよりは、かつて日本の里村の何処にでもあった春の息吹のような世界が展開している。まさに「在るようでいて無い」そんな風土が瑞々しく語られている。 序文は、日本民俗学の父柳田国男の後継者と云われる故宮本常一博士が寄せている。氏の交遊の広さに改めて驚かされるばかりだ。序文の中で宮本氏はこのように語っている。「地方にこういう人のいる間地方は発展する。・・・なぜならそうした人はその地を真から愛し、真から大切にしているからである。」同感である。千葉氏のような人がいる限り、栗駒という里村は、今後も奥州独特の風情を残す里の村としてその文化風土や景観が引き継がれていくことであろう。 私は、この本を、2000年のある夏の日に、亡き父(佐藤光弥)の本棚から見つけた。巻末に「呈上 佐藤光弥大兄」とあった。その時、何故か分からぬが、ひとつの因縁のようなものを感じた。千葉光男氏は、長年に渡って父の友人であり、その縁もあってか、栗駒の沼倉飛騨守の碑を円年寺に建立するという時には、父が世話人のような役割を担い、その歴史的背景の裏付けについては、常にその中心に居られたのが千葉光男氏であったと聞いている。 図らずも父は1971年秋に他界し、それから30年の歳月が過ぎようとしていた。そんな夏の日に、千葉氏が父に送った一冊の書物(栗駒の話)を目にした時、突如として私の中にこのような思いが浮かんだ。「この書物を、何とか多くの人々が読めるようにしよう」と。それは栗駒のためであり、千葉氏への深い敬意であり、亡き父への追悼の意味を持つものである。そのことを千葉光男氏に話すと、一瞬の躊躇もなく、快諾していただいた。 ところがそれからが大変であった。快諾していただいたにも関わらず入力作業は、遅々として進まなかった。それでも何とか二年余りの歳月が流れ、ようやくにして、ここに全文を入力し終えることができた。誠にもって、千葉氏のご行為に報いた安堵感で只々一杯である。 皆さま、どうかこの本が醸し出す独特の里村の人々の感性をじっくりと味わっていただきたい。どっこい都会ばかりが日本ではないということが、しみじみと分かるはずである・・・。 2002年4月24日
佐藤弘弥 |