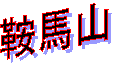
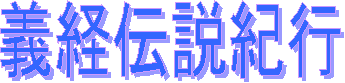
5
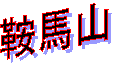
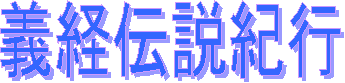
5
1 2 3 4 5

僧正が谷周辺
遮那王が鎮座まします僧正が谷に詣ずる人や絶へなし
11 僧正が谷不動堂と義経堂
背比べの石から、道はいっそう細くなって下りとなる。この辺りは、鬱蒼と茂る杉の大樹に囲まれていて、晴天の日ですら、薄暗い感じがする。道なり原生林を数分進むと、突然、道が開け、平場となり、不動堂が現れる。この辺り一帯は、僧正が谷と呼ばれ、鞍馬山での義経伝説の発祥地のようなだ。謡曲「鞍馬天狗」では、ここで、牛若丸こと義経公は天狗と出会っている。幼い日の義経公は、夜な夜な天狗たちに剣術や妖術を習っていたという。この場に、佇んでいると、そんな荒唐無稽な話も、なるほどと思わせる不思議な雰囲気がある。

僧正が谷不動堂
僧正が谷の天狗の教ゑをば胸に刻んで男(ひと)義に殉ず
僧正が谷不動堂から20mばかり進んだ道の右奥に、まるで弁慶のような大杉を従えた小さな御堂が建っている。これが「義経堂」である。実に瀟洒(しょうしゃ)な建物で、とても稀代の英雄源義経をお祀りしているようには見えない。しかしそれも無理からぬことかもしれない。今も義経公には朝敵の汚名が着せられているのだ。そんな人物が、京都の洛北において、その人物の御堂を建て、それを守っている京都人がいるということにある種の感動を覚えた。

鞍馬山義経堂
弁慶の如き神木随えて義経堂は楚々として立つ
鞍馬弘教初代管長を務められた故信楽香雲師(しがらきこううん)は、その著「鞍馬山歳時記」(鞍馬山双書1970年)の中で、鞍馬山と義経公の関係についてこのように書いておられる。
「鞍馬山といえば、たいていの人は牛若丸を思い出す。のちに源家を再興した九郎判官義経と鞍馬山の関係については、いまさらここに書くまでもあるまい。義経公のことを、世俗では、中世における卓越した武将、つまり日本歴史上の一人物としてしか見ていない。だが、鞍馬山では違う。「遮那王尊」として神格化し、魔王尊のお心とお力とを現実の世界で如実に具現した方として尊崇する。だからこそ魔王尊の脇侍として、鞍馬山奥之院の義経堂にお祀り申し上げてある。衣川の館に討死したあの義経公は、幼時を過ごした懐かしのふるさと鞍馬山へお帰りになったのである。かつて日本中を席巻した義経公にとって、ほんとうに心からくつろぐことのできるところ・・・それは鞍馬山でしかない。そして義経公は、今もなお、この鞍馬山で生きていらっしゃるのである。」そして、鞍馬寺では、毎年九月十五日に、「鞍馬山義経祭」を挙行しているのである。

僧正が谷の大樹の隙間から鞍馬山の空を望む
遮那王と呼ばれし人もこの空を眺めしものか心震わし
この鞍馬山で幼い義経公は、どんな思いを持って過ごしたのだろう。ここで、南北朝末期に成立した「尊卑分脈」(そんぴぶんみゃく)というもっとも信頼に足るとという系図が記述した義経公の元服までを辿ってみることにする。
「平治元年十二月の乱において、逆徒の汚名を着ることになった父義朝が殺された後、義経の母の常磐は、平清盛らの追手を逃れるため、三人の幼い子供たちを連れて、奈良の山の中を逃亡した。その時、義経はわずか二歳で、母の胸に抱かれていた。後に、母の常磐御前が、京都に再び上った後に、十一歳の時より、鞍馬寺に住むことになった。善淋房の覚日坊という僧(東光房阿闍梨賢日の弟子)は、「義経公は、幼い頃から、とにかく武芸に親しんでおられた」と語っている。
さて義経が十六歳になる時、鞍馬寺において、東国の旅人の陵助重頼と言う者と意気投合し、契約を交わしたようであった。結局、義経は、承安四年三月三日の明け方に、鞍馬寺を出発し、関東へ向かった。さらに関東に赴くと、しばらくして今度は奥州に下った。奥州では藤原秀衡の館に住んで、五、六年を奥州で過ごした。」(現代語訳佐藤)
周知のように母の常磐は、幼い三人の子の手を引いて、極寒の吉野を彷徨った挙げ句、清盛の元に投降した。その理由は、彼女の実母が、清盛の手の者に囚われたというものだった。母を助けたい一心で、常磐は清盛と渡り合い。「どうか母を自由にして欲しい」と訴えた。その後の子細は不明であるが、とにかく清盛は、常磐の健気に感じ入って、母はもちろん常磐と宿敵義朝の子三人を放免した。一説では常磐の美貌に免じ、一時側において寵愛した、とあるが、私はこの説には否定的である。おそらく清盛は、侍にしない、という確約を常磐にとって、許したのである。(注1)しばらくこの哀れな母子を側に置いたとして、世間のほとぼりが冷めるのを待って、公家の一条(藤原)長成の妻として、父のような役割を果たしたと考える。
さて鞍馬山に義経公は入った年齢には、ふたつの説がある。7歳説と11歳説である。前説は、「義経記」の立場である。「義経記」では、幼いため、7才まで母と暮らし、その後に鞍馬寺の東光坊という僧の許に稚児として預けられた、と記されている。一方、「尊卑分脈」は、後説を採っている。新訂増補「国史大系」を編纂した歴史家の黒板勝美(1874?1946)は、その著「義経伝」で7歳説を採っている。同じく歴史家の高橋富雄氏も「義経伝説」(中公新書)で7歳説である。私はあえて、「尊卑分脈」の11歳説の立場を支持したい。
さて稚児として預けられた幼い牛若に関して、「尊卑分脈」には、注目すべき記述がある。それは牛若の師匠の東光坊の弟子覚日坊が語ったという次の発言だ。
「義経公は、幼い頃から、とにかく武芸に親しんでおられた」とにかく、剣術に夢中になっていたということだろう。天狗に剣術を習ったという伝説は、この辺りの事実が大きくなって膨れあがったに違いない。一方、「義経記」(巻第一の三)では、同じ覚日坊が語っているのだが、かなりニュアンスが違うことを言っている。
「今のまま二十歳頃まで学問したならば、鞍馬の東光坊から、後の仏法の歴史と伝統種を受け継いで、毘沙門天の御宝とも評される人となりましょう」(現代語訳佐藤)ここには少し伝説上の美化があるように思う。おそらく尊卑分脈の表現の方が現実に近かったのであろう。つまり、牛若は、幼い頃学問そっちのけで、剣術の稽古に明け暮れていたのである。要は体育系の男子である。つづく(注1)清盛は、平家がその後滅び去った事によって、不当にその人間としての評価が落とし込められているが、この時代においてはまさに傑出した大人物だ。おそらく俗物たちが、自分と同じさもしい考えで、きっと「常磐の美貌に目がくらんで、助けたに違いない」と勘ぐったのであろう。清盛は、常磐とその子だけではなく、幼い頼朝だって、伊東に流して命を助けている。清盛には、深い仏教に対する帰依から来る慈悲の心が確固として存在した。強いていえば、それが政治家としての彼の弱点だった。しかし近い将来、平清衡の人間としての器の大きさが再評価時が来ると思う。

木の根道
僧正が谷に顔出す木の根をば踏まぬと飛べば天狗よ我も

鞍馬山奥の院魔王殿
奇っ怪な強き霊力(エナジー)感じつつ奥の院立つ魔王のごとく

鞍馬寺の西門
登りたき時に登らでいつ登る鞍馬の山の伝説の坂

貴船川
貴船口辿り着きたるへとへとの我をせせらぎ閑かに迎ふ
せせらぎは山かけ着きしへとへとの我を貴船の母とし迎ふ