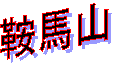
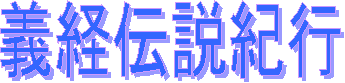
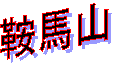
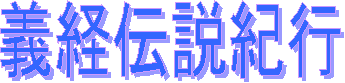
3 1 2 3 4 5
義経公供養塔
都づら坂行けば牛若暮らしける跡に昭和の石塔の建つ
6 義経公を教えた東光坊の僧坊跡
由岐神社を過ぎると、つづら折りの坂は、いよいよくねくねと厳しさを増してゆく。この辺りには、かつて、十に及ぶ院と九つの僧院が建っていたようだ。少し行くと、右手に川上地蔵堂が見えてきた。まだ新しい御堂である。ここにかつて安置されていた地蔵尊は、義経公の守り本尊であったと伝えられている。道を挟んで右手には、義経公が、預けられた東光坊阿闍梨(とうこうぼうあじゃり)の僧坊跡と言われる所に義経公供養塔が建てられている。昭和15年に建立されたものである
「義経記」によれば、この東光坊という人物に、七才の牛若は、二月初めに預けられたことになっている。要はここで義経公が、幼き日に寝泊まりをしていたことになるのだが、どうも実感が湧かない。それはこの場所が余りにも狭いせいもあるのかもしれない。

川上地蔵堂
瀟洒(しょうしゃ)なる地蔵堂かな、一心に牛若祈る姿が浮かぶ
義経公が鞍馬入りの情景を想像してみた・・・。
春まだ浅い鞍馬街道を、数人の従者に手を引かれて歩いてくる幼子がいる。牛若時代の義経公だ。道にはまだ深く雪が残っている。何度も雪に足を取られて転ぶのだが、幼子は弱音を吐かない。すぐに立ち上がって、従者の手を強く握って、視線は常に前にあった。心の中には、母の常磐御前の涙を服姿があった。それを思うと牛若は悲しかったが、けっして泣くまいと思った。源氏の血を引く人物を受け入れた東光坊にも、ある種の覚悟があったはずだ。彼は鞍馬寺の別当であり、かなり位の高い僧侶である。また阿闍梨とあるのだから、密教の修行も積んだ人物であったはずだ。彼が、この幼子を山門の前にまで向かえに出ていて、この由岐神社のすぐ側の、自らの僧坊まで、手を引いて来たのであろうか・・・。
以後、有名な鞍馬山における義経伝説が生まれてくるのである。僧坊の辺りは草むらで何もそれらしきものは残っていない。しかもつづら折りの坂であるから、それほど巨大な建物が建っていたとは思えない。むしろ質素な御堂のような建物だったかもしれない。さて義経伝説によれば、天狗に剣術を習ったというのであるが、もしかするとこの東光坊という人物が、実際には若き義経公に学問から剣術(兵法)に至るまでのすべてを教えたのかもしれない。
川上地蔵堂を過ぎ、坂道を左に折れると、道はますます蛇のように蛇行をし、背中にリックの重みを感じるようになった。何しろコンピューターやカメラ、書籍、着替えとすべて入れてあるのだから結構重い。おまけに紺のスーツにビジネスシューズだから、ちょっと端から見ればまるで天狗のように映ったかもしれない。
義経さんが習った天狗というのは、山伏修行をしていた修験の連中だと思うが、山伏とは、そもそも山の武士なのだから、妖術はどうか分からないが、剣術は得意なはずだ。ここで天狗のことを少し考えてみよう。
中国の妖怪の類を表した書に「山海経」というのがある。この中で、天狗のことをテンコウと呼び、次のように説明されている。「その状は狸の如く、白い首、名は天狗(てんこう)。その声はリュウリュウ(未詳)のよう。凶を防ぐによろし」これは想像上の動物であるから、そのまま信じる訳には行かないが、図も載っているので、よく見れば外見は狸というよりは山猫に近い感じだ。凶を防ぐに良い、というのだから、縁起のいい妖怪のようだ。
日本の天狗とは、どうもかなり違うようだ。日本の天狗の場合は、古事記や日本書紀に登場する異形の国つ神である猿田彦命(サルダビコノミコト)の容貌をベースにして形成されたイメージが強い。この神さまの容貌は、日本書紀によれば、鼻の長さが七握(ななつか)背の高さが七尺あまりで口の周囲が明るく光っている。目はヤタの鏡のようで赤ホオズキに似ていた、という。七握というのは、拳で七つというのだから、鼻が異様に高いということを大げさに言っているのだろう。それで背が高く、目が光っている。これは我々が祭りでよく見るあの天狗とも見えるが、子供の頃に、初めて西洋人を目前で見た時の印象に近いものがある。
この猿田彦という人物が、日本の神話に登場するのは、ニニギノミコト(アマテラスの孫)が高天原(たかまがはら)から豊葦原(とよあしはら)の中つの国にやってくる時である。これはアマテラス一族が天つ神として、東に移って国家統一を実現しようとやってくる時の話と考えてさし支え在るまい。その時、猿田彦の一族が、途中にいたということになる。そこでニニギノミコトは、この異形の人物を味方に付ける方法を考える。アメノウズメという女性を使者として差し向けて、これをうまく道案内にしてしまう。女性の力というものは、昔からこんな具合に凄いものがあった。
こうして天孫降臨と言われる国家統一の第一歩が叶ったのである。だから祭りの先導役は、決まって天狗のお面を着けた猿田彦が務めることになるのである。
さて柳田国男に「天狗の話」という小論があるが、この話が実に面白い。
「元来天狗というものは、神の中の武人であります。中世以来の天狗のほとんと武士道の精髄を発揮している。少なくても武士道中の要目は天狗道においてことごとく現れている(中略)すなわち第一には清浄を愛する風である。第二には執着の強いことである。第三には復讐を好む風である。第四には任侠の気質である。儒教で染め返さぬ武士道はすなわちこれである。これらの道徳が中庸で止まれば武士道で、極端に走れば天狗道である。」
この天狗道とは、極端に走った武士道である、という柳田の認識が明解でいい。考えて見れば、天狗道の四つの条件である「清浄・執着・復讐・任侠」という性格は、源義経という人物において、最も見事に顕現していると思う。要するに義経さんにおける天狗道的性格は、時々常軌を越えているとさえ思えるほどだ。
例えば、たったひとつ、兄の頼朝が平家追討に立ち上がったと知った時の義経さんの歓喜と熱狂は、たとえ奥州の父と慕う藤原秀衡の「時期尚早!」との声にも耳を貸さないほど強烈なものがあった。そして一人で、奥州を旅立とうとする。見かねた秀衡が、佐藤継信・忠信兄弟ほか八十名ほどの郎党をつけて鎌倉に渋々送るのである。これは奥州を束ねる大政治家秀衡にとっては青天の霹靂の如き事件だった。義経さんを中心に据えて、奥州が京都や関東に並び立って行くためのカードが、消えてしまったのだから・・・。
また一の谷で劇的な勝利をした後、逃亡した平家を屋島に追う際も、嵐の海を突いて決死の覚悟で向かう彼の姿は人智を越えた天狗道的性格そのままである。やはりその根底には、先の四つの天狗道的性格が、彼を突き動かしていることは明白だ。
そんな義経さんの一連の天狗道的性格が、様々な義経伝説を生むことに繋がったのであろう。だからおそらく事実は、鞍馬山で天狗に剣術を教わったというよりは、元々義経さんには、天狗道に通じるような性格が本来あって、後世の人が「義経という超人的な生涯を送った人物が育った鞍馬山には、怖ろしい妖術を使う天狗が棲んでいるはず。」となったというのが、ことの真相ではあるまいか。

転法輪堂に続く石垣
秋天に鞍馬の山の紅葉たち紅く染まりてゆく時を待つ
8 新参道から転法輪堂まで
中門と呼ばれるかつて仁王門の横にあって勅使が通ったという門が立っている。門をくぐり、更につづら折りの坂の石段を登ると道は新参道と合流する。右にやや下って行けば多宝塔が立つ地点に行き着く。近くには鞍馬寺ケーブルの終点多宝塔駅がある。
この多宝塔だが、元々は本殿の東隣にあったものが江戸時代に焼失し、昭和35年に再建されたものだと言う。中にはケーブル工事中に発見された開運の毘沙門天が安置されている。左に急角度に折れて進むと展望台のようなになっている踊り場に着いた。
結構足ががくがくとする。マフラーにスーツという軽装だが、額には汗が滲んでいた。眼前に拡がる東の山々に目をやれば、比叡の山々が仄かに赤く染まっているのが見えた。西の本殿の方を見ると実に立派に石垣が組まれている。入口である仁王門を過ぎた辺りにも、このような石垣が在ったが、その昔ここは京都の北方を守る砦として役割を担っていたのであろうか。
階段を少し登ると、豪奢な造りの転法輪堂が秋空に向かって甍を伸ばしていた。
秋空にすくとぞ立ちて法を説く大悟の釈迦や転法輪堂
少し行くと巽(たつみ)の弁財天社があり、その手水舎(てみずや)で歳の頃なら5、6才の男の子が、柄杓で面白そうに、水を掬っている姿が見られた。何か牛若時代の義経さんのようにも見えて、こんな歌を詠んだ。
牛若のごとき幼子水取りて何を祈るや鞍馬の神に
この地点から本殿までは、もう少し石段を登らねばならない。
つづく

本殿金堂前の手水舎(てみずや)
牛若のごとき幼子水取りて何を祈るや鞍馬の神に
つづく
2002.12.3
2002.12.11 Hsato
Home