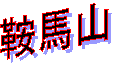
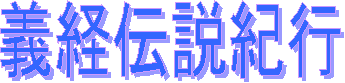
4
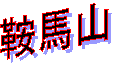
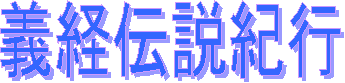
4
1 2 3 4 5

昼暗き鞍馬の紅葉赤々と秋の一日を焦がして妖し
9 鞍馬山と神仏習合について本殿金堂が近い。確かに背中の荷が足に堪えてきている。階段を登りながら、鞍馬寺という古寺のあちこちに見受けられる神と仏の習合した影についてあれこれと思いを廻らせた。何故ならば、神仏習合というものの根底には、宗教というものの本質があり、又日本という国家の歴史の秘密が横たわっているようにも思われるからだ・・・。
直感で言えば、鞍馬寺は、日本古来の神と大陸から伝来した仏の宗教が融合して出来た山岳霊場のように思われる。鞍馬寺では、中心の伽藍のことを「本殿金堂」と呼ぶが、これは「本殿」という神道における社(やしろ)を呼び慣わすような呼び名と「金堂」という仏教の御堂を重ねたような名で実に象徴的である。今日、日本では、神と仏がうまい具合に合体して違和感がないようになってしまうことを、「神仏習合」と呼ぶ。神仏習合の考え方では、新参の神ではあるが、より力のあると思われた仏教の仏たちを「本地」とし、神は仏たちの仮の姿の「垂迹」(すいじゃく)とする考え方で「本地垂迹説」とも呼ばれる。きっと長い日本の歴史の中では、文明の衝突というには、少々大げさかもしれないが、日本中で土着の神々と仏教の仏たちの数々の対立があったはずだ。
確かカール・マルクスが、その著「経済学批判」の序文の中であったと思うが、文明による征服のパターンを三つに分けて説明していたように記憶している。それによれば、征服には、前の文明を全部滅ぼすやり方と、前の文明を一部取り入れてやるやり方と前の文明をそっくり生かしてそれを乗っ取るような三つのやり方がある、というものだった。まさに日本における「神仏習合」は、二つ目のやり方ということができる。
日本に仏教が伝来したのは6世紀の中頃のことである。それまでは古神道の教えが人々の間で広まっていたはずである。そこに国家宗教として仏教が、インド、中国、韓国をへて日本に渡って来た。仏教は、周知のように今から2500年ほど前に、北インドの小国の王子だったゴータマ・シュッタルタという人物が、人生の一切を苦と看過して覚りを開き「目覚めた人」という意味の「ブッダ」と呼ばれ、その後、東アジアに拡がった宗教である。ブッダという人物は、国家色のない極めて個人的な悟りを目指す人物であったが、その死後次第に教団は大きくなり、アショカ王やカニシカ王という権力者が、この宗教を庇護し、国家の基礎に据えるようなこともあって、宗教としての飛躍を遂げていったのである。しかし地元のインドでは、何故か拡がらず東へ東へと信者を次第に拡大していったのである。地元のインドでは、やはり民族宗教色の濃いヒンドゥー教が、主流を占めるようになったと見るべきであろう。こうしてブッダの教えは、生きと生ける数多の衆生を救う目的を明確に持つことによって、自らを「大乗仏教」と呼び、古来よりのブッダの教えを忠実に守ろうとする一派を小乗仏教と一段低く観るような風潮となっていったのである。

金堂の朱色に負けぬ晩秋の今落ちむとす葉の朱さ哉
日本に伝播した宗教としての仏教は、国家建設に意欲を燃やしていた蘇我氏のような連中が大いにこの権威を利用した。しかし仏教思想の日本への浸透は、容易には進まなかった。少しして仏教思想で国家統一を推進しようとした蘇我馬子(?−626)と古神道を守ろうとした物部守屋(?−587)の対立は内乱となって爆発したのだ。この時、蘇我氏の血を引く聖徳太子は、蘇我氏と手を組み、日本国家の精神的礎を仏教で築こうとした。結局、今でも聖徳太子(574−622)の国家建設の大義を実現する根本には、仏教の思想が中心に据えられていることは明白である。
六世紀から七世紀にかけて、蘇我氏のような大陸からの渡来したと思われる氏族たちが、物部氏のような旧勢力を差し置いて、日本の政治の中枢にじわじわと頭角を現してくる背景には、新宗教としての仏教の衆生を普く救うという教義とその熱いエネルギーが是非とも必要であったということであろう。事実その後、仏教は、日本国家建設の強力なイデオロギーとなっていく。遣唐使や遣隋使となって、若者たちが大挙して日本海を渡り、新しい土木建築芸術などの最新知識を身に着けて帰ってくることになった。その中には、最澄(767‐822)や空海(774−835)のように宗教としての仏教を習おうとした若い僧侶たちもいた。
彼らは自分の命をも顧みず、海を渡り、仏教の教義はもちろんのこと、国家建設に必要と思われる最新学問を貪欲に吸収し持ち帰った。特に空海は、短期間のうちに、密教の経典を日本に持ち帰ると共に、持ち帰った技術をもって生まれ故郷の香川満濃池の修復に力を注ぐなど、今日の「弘法大師伝説」を生むような際立った人物だった。文明同士の衝突もそうだが、競争相手との対立関係が、時として新しい世の中を創造する活力となることがある。ましてや自分の信じている国や信仰が相手よりどこかで劣っていると感じた時には、それに反発し、それ以上の優れたものを吸収してやろうという気持が湧いてくるものだ。最澄は、空海から密教の教義を教わろうとしたが、その夢を果てせずに亡くなってしまうと、その弟子の円仁(794−864:慈覚大師)が中国に渡り、様々な困難を乗り越えて密教を習得して、空海の東寺の密教の「東密」に対抗し、天台宗の密教という意味の「台密」(たいみつ)を確立した。更にこの円仁という人物は、国家建設を成し遂げる目的をもって、まるで映画「ミッション」のキリスト教宣教師のように、蝦夷(えみし)と呼ばれる東北の奥地にまで足を運んで、大和朝廷の北進の宗教者として布教活動を精力的に展開するのであった。
ところでこの神仏習合であるが、昨今は、何かあたかも日本独特の「和」の精神のようにして解釈されることが多いが、そもそも仏教の仏たちの由来は、インド古来の神々であり、インドの先住民であるドラヴィタ人の神と、後に移動してインドの地に来たアーリア人の神々が習合して出来上がったものである。つまり仏教の仏や神々たちは、インドの地で、習合を繰り返してきたのだから、土着の神々たちを自分の配下に置く手順には長けているのである。世界からすればど田舎でしかなかった当時の日本の民の信じる神たちを手なずけて自分の神仏に習合してしまうことなど、インド哲学の伝統を踏まえて行えば、朝飯前の仕業であったはずだ。
鞍馬寺の歴史以前の話はよくは分からないが、650万年前に金星から鞍馬寺の奥の院に鎮まったと言われる魔王尊「サナート・クマラ」の伝承にしても、どうもインドのヒンドゥーの神々の影響が色濃く感じられるのである。

朱の眩し金堂過ぎていよいよに魔王尊棲む暗き道ゆく
10 霊宝殿から背比べ石まで本殿を抜けて、いよいよ天狗さんが棲むという奥の院に向かう。奥の院への道は、本殿までとは違う空気がある。昼過ぎなのに、やはり暗い。おまけに何か信じぬ者を寄せ付けない「気」のようなものが漂っている。天狗さんの領域に足を踏み入れたということなのか。異界に分け入っていくような不思議な感覚がした。
今回、霊宝殿は、今回は行かないことにした。この中には、梅原猛氏が、「この毘沙門天を見る度に、源義経のことを思い出す」と言った「毘沙門天像」が安置してある。角張った顔をして、眉間に皺を寄せ、手で日を除けて、遠く北方に鋭い視線を放っている国宝の像のことである。私はこの像が義経公のイメージに重なるという感覚は持っていない。余りに表情が厳めしく、美しい稚児牛若丸のイメージとかけ離れ過ぎていると思うからだ。梅原氏が、何故この像に対し、義経公のイメージを持つのか、その辺りのことを考えてみた。
どう考えても、私にとっては、この像は、義経公ではなく、坂上田村麻呂にしか見えない。周知のように坂上田村麻呂(758-811)は、毘沙門天の化身と言われた人物であった。田村麻呂は、当時大和朝廷に組みしないエミシと言われる人間たちの国であった奥州を服させた功労者である。彼は桓武帝の命を受け、新しい神仏を合わせた宗教思想と圧倒的な兵力をもって、エミシの軍と対峙し、苦戦の末に、打ち破った。
しかし奥州のエミシの文化というものが、滅ぼされたのか、と言えば、そうではないと言いたい。その根拠に、その後も、奥州には、エミシの心を受け継ぐ猛者たちが次々と出現した。例えば、安倍氏が滅んでも、次には奥州藤原氏という具合に、奥州のアイデンティティーは時代を経てもそれを復興し守る人物が現れてきたことは、歴史上の冷厳な事実である。田村麻呂からほぼ四百年後の世界に生きた源義経公は、鞍馬山を出て、青春の一時期、奥州藤原氏三代頭領の藤原秀衡公が統治する時代、奥州に身を寄せた。そして再び奥州を出て、平家追討の大活躍をするのであるが、最後には、奥州平泉の地で自害を遂げることなるのである。
その後、鞍馬のこの毘沙門天のイメージが、何かの拍子に田村麻呂から義経公にいつしか移ったのかもしれない。思うに民衆の心の中を辿ってみれば、「義経記」から「御曹司島渡り」(「御伽草子」のひとつ)と受け継がれる義経伝説形成の過程で、平家を打ち破った天狗や鬼神の如き人物像が、鞍馬の天狗→鞍馬山の毘沙門という流れで、いっきに義経=毘沙門天化身説が浮上してきたとみてもいいのではなかろうか。
これは民衆の心の中で起こった毘沙門天のイメージの変遷である。民衆は常に新しい英雄像を探している。きっと現実感のない坂上田村麻呂に象徴される毘沙門天信仰が、いつしか当時とてつもなく強いと見られた武将の源義経という人物に、そのイメージが移ったということであろう。
特に奥州は仙台のご出身である梅原氏が、何気なく鞍馬の「毘沙門天像」を見て、義経公を思い出すという感覚は、もしかすると彼のどこかににある判官贔屓の強い奥州人のアイデンティティーが呼び覚まされて、義経=毘沙門天のイメージが湧いた可能性もあると言うと言い過ぎであろうか・・・。

牛若の息次ぎ水と伝はりしわき水枯れて少し寂しも
霊宝殿を過ぎると、与謝野晶子の書斎を移築したとされる冬柏亭(とうはくてい)がある。そう言えば、霊宝殿の横には、与謝野鉄幹と晶子の歌碑があり、鉄幹は、こんな歌を遺していた。遮那王が背くらべ石を山にみてわが心なほ明日を待つかな
坂道を上っていくと、牛若と呼ばれた義経公が夜な夜な天狗さんに剣術を習いに駆け上がって行く時に、水を汲んで呑んだという伝説のある「息次ぎの水」があ。きっと鞍馬の湧き水の味は格別だろう。呑んでみたいと思うが、残念ながら水が枯れているのか、竹の先からは水が涌いていない。柄杓が間を持たないように二つ三つ並んでいた。ふと西行の鞍馬で詠んだこんな歌を思い出してしまった。
世をのがれて鞍馬の奥に侍りけるに、かけひの氷りて水までこざりけるけるに、春になる まではかく侍るなりと申しけるを聞きてよめる(訳:世の喧騒を逃れて、鞍馬山の奥に入 った時、筧(かけい)だけでなく、流れるはずの水までが氷っているのをみて、誰かが 「春まではこんな感じですよ。」と言ったのを聞いて詠んだ歌)わりなしやこほるかけひの水ゆゑに思ひ捨ててし春の待たるる
(訳:仕方がないことだなあ。筧(かけい)の中で水が氷っているのだから。呑みたいと いう気持はさっぱり捨てて、春の来るのを待ちましょうか)
西行は、いつの頃にこの鞍馬山に来たのであろうか。もしかすると義経公が、まだこの鞍馬山に入る前かもしれない。そんなことを思いながら、いよいよ険しく細くなる土の道を登って行くと、屏風坂の地蔵過ぎて、奥州に向かう義経公が、自分の背を刻したという「背比べ石」の石があった。木の囲いに囲まれてあるのは、おそらく訪れた者たちが、めいめいにこの石に触ったりするので、倒れたりしたら危ないというのでこのようにしているのかもしれない。私には、違和感があった。余りにも物々し過ぎる気がしたからだ。そこににぎやかに女子高生と思われる4人ほどのグループが現れた。背比べの石の前に行くと、こんな会話をしている。
「随分、義経さんって小さいのね」
「そりゃー仕方ないわよ。牛若丸の時代だもの。奥州へ旅立つ頃だもの。まだ子供だったはずよ」
「でも。16歳でしょう。私と背丈変わらないわよ」義経公は、確かに小柄だったようだ。それは吉野の吉水神社や愛媛の大山祗(おおやまつみ)神社に奉納したと伝えられる鎧を見ても分かる。但し注意しなければならないのは、義経公の使う鎧は、自身が敏速に動き回るように作らせているので、無駄なものがそぎ落とされているため、小さく見えることも加味しなければならないと思われる。

みちのくに旅経つ頃の牛若の身の丈伝ふ背比べの石