

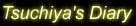

|
11月24日(木) 60〜70年代の再検証が相変わらず続いています。しかしまぁ、書籍やら映画やらとにかく山程あって、いつになったら終わるのか、見当がつきません。 今はもう、脳内がゴチャゴチャで、前作『新しい神様』を作る前の地点、「俺たちの敵とは?」的な青臭いけど重要な一点、に浸っている段階です。 再検証の流れで、ずっと観たかった『dial H-I-S-T-O-R-Y』(監督 : ヨハン・グリモンプレ)を観ることが出来ました。ハイジャックのドキュメンタリーです。そのパンフレットに載っていたスラヴォイ・ジジェクの言葉にしびれました。 「もちろん肝心なのは、世界貿易センタービル崩壊を、またも登場したメディアのスペクタクルであるというように矮小化する疑似ポストモダンゲームをやらず、それを殺人ポルノの破滅的なかたちとして読むことだ。9月11日のテレビスクリーンに見入るとき問うべき問いとはたんにこうだ。<これとまったく同じものを、すでに何度も何度も見たのはどこでだっただろう。>」 殺人ポルノの監督とその熱狂的な観客とは一体誰か?『PEEP "TV" SHOW part2』、誰か作ってくれ。 そう言えば、宮台真司さんが今年の邦画ベスト10に『PEEP "TV" SHOW』を入れてくれたみたいです。 今日は頭が疲れてるので、この辺で。 |
|
11月13日(日) どうも日記には何か特別な出来事とか告知とかを書くもんだという感覚があって、何もないと書かない日々が続いてしまいます。なので今日は、取り立てて書くこともないんですが、書いてます。 最近は、前回の日記にも書いたメイキングものの関係もあって、60〜70年代のおさらいをしてます。まぁ、政治闘争の時代なわけですが、やはり、端的に言って面白そうな時代だったんだな、と思います。妄想だろうが何だろうが「作家即運動者」と足立正生が提唱したように、表現者自身が運動体として「世界」を相手取ってその変革の為に格闘していたわけだから、面白くないはずはありません。若松孝二の「爆弾映画」を同時代に観る興奮は、悔しいけど、やはり羨ましいです。 「悔しい」というのは、そういう興奮を作り出せていない自分自身に対してなわけですが、それにしても00年代、面白くないです。 『PEEP "TV" SHOW』の劇場公開時のトークショーで宮台真司さんが、結局、土屋の映画は「世の中、面白くねぇーんだよ」ということで、それが結果的に政治性となっているみたいなことを言ってました(その様子は来月末リリースされるDVDとビデオに収録されます)が、まぁ、そういうことなんだと思います。 『PEEP』制作時は、9.11の同時多発テロ(というか、戦争なんだから、やはり同時多発攻撃か)があり、アフガンからイラクに至るアメリカの侵略に対する日本国内の反戦デモもそれなりに盛り上がっていて、私も何度か参加したんですが、どうも面白くない。「爆弾映画」のような興奮がない。ピースは退屈だと思わずひねくれてしまいたくなる。ホントのところは、テレビの中のツインタワー崩壊映像に異常に興奮している自分がいる。そして、そのこと、つまりはメディアによる包囲網の方が、今の自分の闘争目標なんじゃないかということで、『PEEP "TV" SHOW』が出来たわけで、自分としては、その後の上映活動(というか単純に宣伝活動ですが)も含め「作家即運動者」の実践的側面もあったりしたんですが、そういう文脈で捉えてくれた人はいなかったですね(勿論、私の力不足です。はい)。 そんな感じで「面白くねぇーな」と思っていたら、知る人ぞ知る外山恒一氏から手紙が届きました。九州の霧島市の市議会議院選挙に立候補するそうです。 外山氏を一言で説明するのは、簡単そうでとても難しいんですが、まぁ、「自称革命家」です。いろんな人が彼のことを否定的に見ている(というか相手にしていない)ようですが、私はどうも彼の愚直さとひねくれ具合にひかれる部分があります。 「現在わが国は戦時下にある、というのが私の基本認識です。(中略)2001年の同時多発テロ以来の、アメリカのいわゆる『対テロ戦争』に、我が国は巻き込まれ、事実上参加しているに等しい、などと云っているのではありません。私の認識は、そんな寝ぼけた左翼のようなものとは違います。(中略)本当は内戦が起きているのです。(中略)現在おこなわれている戦争は、かつてのような国家対国家の戦争ではなく、国家の内側での多数派対少数派の内戦であるということです。」 これが彼の今の主張です。面白いと思いませんか?監視国家としての日本は今、内戦状態にあるという認識に立った途端、世の中が面白く見えて来ませんか? 外山氏の作風としては、それへの闘争を「投票用紙(ゴミ)は(とりあえず「外山恒一」とでも落書きして)投票箱(ゴミばこ)へ!」というキャッチコピーでもって市議選に立候補ということになり、逆に反感というか、又吉イエス的扱いになったりするんですが、それも彼なりの作戦かと思われます。 いずれにしても、皆さん、「世の中、面白くねぇーんだよ」と思いせんか? 取り立てて書くこともない、と言いながら、結構書いてしまいました。 |
|
11月2日(水) もう遠い過去のようですが、阪神、4連敗でしたね。最終戦は嗚咽が込み上げ、矢野の送りバント失敗で、私は、灰になりました。 「下流社会」(光文社新書)、「しみったれ家族」(ミリオン出版)と続けざまに読み、落ち込みました。親が下流なら子は下流、しみったれは遺伝する。「上流」、「下流」の二極化が固定化しつつある現代日本に追い討ちをかける小泉「改革」。あるいは、二極化したから小泉自民党のやりたい放題なのか・・・実際、俺も金がない。希望格差が開きまくってる実感。あぁ、ツライ・・・ というわけで、救いを求めて一昨日、『ある子供』(監督 : ダルデンヌ兄弟)の試写会に行って来ました。「しみったれ家族」で言うところのタイプ4(読んでない人はわからないと思いますが、超面白いので是非読んで下さい)の若いカップルが主人公で、男の方は、お金の為に二人の間に出来た子供を売っちゃったりするんですが、ラストの「希望」に、私の心は、抜けるような青空のごとく澄み渡りました。号泣です。ホントはもっと泣けたんですが、試写ということで、両隣りの業界人が気になってセーブしてしまいました。 とにかく皆さんに観て頂きたいので詳細は省きますが、「愛」とか「信頼」とか「共感」とか、普段の私なら「ケッ」と斜に構えてしまいそうな事柄に素直に心が反応し、今年一番と言ってもいいくらいの体験でした。 当然のことですが、未来に希望が持てないのは、希望というものが何なのか知らないからです。愛を無意味と感じるのは、無意味じゃない愛を知らないからです。そして、その希望や愛は、1対1の人間関係の中からしか生まれません。「世界」と対峙する前に、目の前の人と素直に向き合え、という単純で些細で素晴らしい原点へ。 なんつって調子に乗って、昨日『ランド・オブ・プレンティ』(監督 : ヴィム・ヴェンダース)を観て来ました。「9.11後の世界の希望」みたいな紹介記事を読み、何と言ってもヴェンダース作品なので、超期待してたんですが、一言で言えば、「ケッ」でした。 こちらも詳細は省きますが、ヴェンダースはホントにあのラストの「希望」に信頼を寄せているんだろうか?という感じです。薄っぺらな希望は、私のようなしみったれには逆効果でした。 ふと思ったんですが、ダルデンヌ兄弟は労働運動とかにかなりコミットしているようなんですが、ヴェンダースは超巨匠になってしまって、「現実」から浮いた世界に行っちゃったんじゃないでしょうか?映画は、ホームレスやパレスチナの問題も絡んでいて、若いシネフィルみたいな観客はそれをありがたがって観ていたようなんですが、「現実」と格闘していない映画監督も観客もダメです。悪いけど、断言します。怒ったついでに言っときますが、喫煙所のない映画館(有楽町のシネカノン)もダメです。嫌煙の人は怒るんでしょうが、映画と煙草とコーヒー(or ビール)はセットなんです(私にとっては)。 でも、主人公の女優は良かったです。 ある映画のメイキングを撮らないかという話が来てます。ギャラはたぶん安いと思うんですが、ちゃんと決まったらやるつもりです。詳細が決まったらお知らせします。 |













