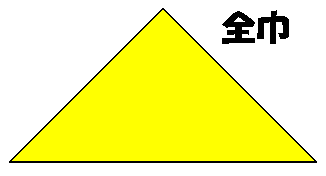![]()
救助・救出された人には、応急手当が必要です。地震等の際には、同時に多数の負傷者が発生することが考えられます。場合によっては、自分で自分の手当をしたり、付近の負傷者の手当をしなければなりません。
負傷者に応急手当をしたか、しないかで、その人の運命を大きく変えるかも知れません。
さて、地震の時は、どのようなケガが考えられるでしょうか。
窓ガラスなどの落下物によるケガ、電柱・ブロック塀が倒れ、その下敷きになった場合の骨折、あるいは火事によるヤケドなどが考えられます。
応急手当に使用するものには、三角巾、副子(ふくこ)、毛布などがあります。しかし、必ずこれらが無ければ手当ができないということではありません。
三角巾の代用には風呂敷やネッカチーフ、Yシャツやパンティーストッキングなども利用できます。また、副子には、板や棒、雑誌や傘なども代用できます。
正しい手当の方法さえ覚えておけば、緊急の場合には応用ができるはずです
◆三角巾は、山のような形をしていますが、この頂上を頂点といい、下を底辺といいます。そして、はしの部分を端(たん)といいます。
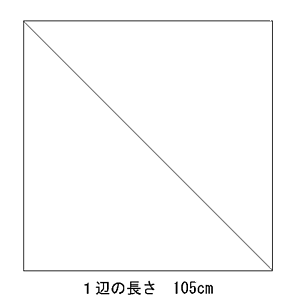 |
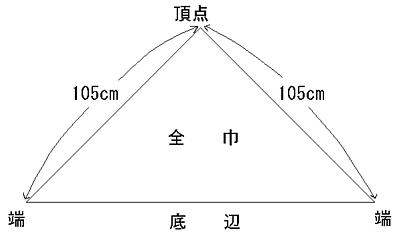 |
◆この三角巾は、傷の大きさに応じて使用できます。広い範囲のケガや関節を包帯したり、腕を吊る時などに便利です。
◆三角巾は、広げて使う場合とたたんで使う場合があります。まず、初めにたたみ三角巾の作り方について説明します。
 |
 |
 |
| 左手の親指と4指で三角巾の底辺の中央部を持ち ます。 右手の親指と4指で三角巾の頂点を持ちます。 |
右手三角巾の頂点を内側に折りこみます。 | 左手の親指で頂点を持ちます。 |
 |
 |
 |
| 折りこんだ三角巾でできた袋の部分に右手を入れ ます。 |
折り返します。 | これが、二つ折り三角巾です。 |
 |
 |
 |
| もう一度、右手を内側へ折りこみます。 | 袋の部分に右手を入折り返します。 | これが、四つ折り三角巾です。 |
 |
 |
|
| もう一度、右手を内側へ折りこみます。 袋の部分に右手を入折り返します。 |
これが、八つ折り三角巾です。 |
◆たたんだ三角巾は、包帯や副子の固定に使います。