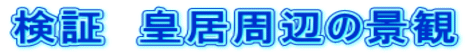|
皇居周辺の景観が危ない 高層ビル化で皇居景観論争勃発?! 
はじめに 08年11月1日(土)、夕方 皇居周辺の景観をめぐるシンポジウムが開催されるというので、会場の神田神保町学士会館で向かった。 そこで、二時間、識者(パネリスト メンバーは下に掲載)の話を聞き、あらためて日本の代表的な景観である皇居界隈が、大きく変貌させられようとしている現実を知り、強い危機感を持った。 【検証 皇居周辺の景観】 1 皇居周辺に高層建築ラッシュ 今、丸の内、大手町、有楽町界隈(通称「大丸有」)では、高層ビルラッシュのような建築物が次々と建設中もしくは建設計画が発表されている。現在建設中の東京駅前の新丸ビルが高さ200m。同じく駅前の中央郵便局がやはり200m。大手町の合同庁舎跡に180mのビジネスビル。大手門と内堀を境に皇居の真ん前に位置する和田倉門濠脇のパレスホテルが100mを越える建て替えを発表。などと続く。 2006年8月7日の読売新聞に次のような記事が掲載されたことがある。 「2002年9月にオープンした丸ビル(約180メートル)でも建設時に最上階のレストランから宮殿が見えることが判明したため、同庁(宮内庁)宮殿手前の石垣上に高さ20メートルのクスノキ2本を植えた。皇太子ご一家はじめ皇族方のお住まいがある赤坂御用地でもビルの高層化は進んでおり、秋篠宮邸では、中が見えないようにするためのフィルムを窓ガラスに張っている。」 宮城までおよそ600mの距離のある丸ビルでも、このような状況が起こっている。建設中の新丸ビルや計画立案中の中央郵便局のビルでも、2002年オープンの丸ビルで起こったことが、次々と起こってくるはずだ。 2 パレスホテルが30mから100mのビルへ 現在、差し当たって最大の問題点は、和田倉門壕脇のパレスホテルの建設(来春竣工、12年春開業の予定)かもしれない。パレスホテルは大手門と斜向かいに在り、その距離は100mほど、大手門を入って右手に位置する宮内庁病院は200mの距離になる。現在30mほどの建物が、一挙に100mを越えることで、宮内庁が同ホテルの建設計画変更の異例の要請をしているとの報道が、やはり読売新聞(08年5月19日夕刊)で報道されている。 この報道によれば、宮内庁は「プライバシー保護への高度な配慮が求められる」との見解をホテル側に発しているようだ。宮内庁の憂慮ももっともである。しかしこの問題は、皇族方のプライバシーを守るという問題に止まらない大きな景観論争に発展する問題ではあるまいか。それは皇居周辺が、日本を代表する公共性を持つ皇居という特別な地域であるからだ。近くには国会もある。この周辺地域においては、単に地権者の利益優先の思考を越えた高度な美意識というべきか、特段の配慮をした景観計画の下に秩序ある都市開発が求められるというべきだ。 そこで例を出して悪いが、多くの市民が出入りする公共施設としてのパレスホテルが、大手門から約100mの距離を置いたにせよ、100mを越える高さの塔のような建物が立ち上がることは、周辺の景観を壊し、さらにパレスホテルの高さを標準として、内堀通りのビルが100mでツイタテのように競って建てられる可能性もある。 3 「マンハッタン計画」の再燃のような高層ビル構想 今から20年ほど前、丸の内の大地権者である三菱地所が、丸の内再開発計画(通称「マンハッタン計画」)というものを発表したことがある。これは丸の内一帯に、高さ200m程度の超高層ビルを約60棟を建設し、丸の内を世界有数の国際金融センターにしようという計画だった。これは丸の内を、アメリカのマンハッタンのようにしようというものだが、この計画が実行された時の想像図がある。一目見て、もしもこの計画が実行されたならば、世界中が、日本人の美意識を疑うに違いないと思われるひどい代物だ。 例えば、マンハッタンと同じくロンドンのシティも国際金融センターとして有名だが、シティの都市計画は、古い建物や道路、川などを活かしながら、上手に調和した景観を造っている。やはりこの皇居周辺の街造りについては、当シンポジウムのパネラーとして参加した西村幸夫氏(東大大学院教授 都市計画)の主張するように、「行政がリーダーシップを取って、地権者や市民が入って議論しながら」というやり方が肝心ではないだろうか。 4 日本建築を愛するブルーノ・タウトの声を聞け かつての江戸城本丸は、天守閣を含む五層六階高さ約60mの大城郭だった。朝日に、また夕陽に映えて、江戸中から見渡せたと言う。千葉の方からも、白く輝く江戸城が見えたとのことである。要するに大都市江戸のランドマークだった。高さがたかだか、60mで江戸中から見えたとすれば、やはり富士山も江戸中から見えて、「富士見」という地名が方々に残るのもなるほどである。 さて、かつて日本を訪れたドイツの著名な建築家ブルーノ・タウト(1880−1938)は、日本建築に感動して、「ニッポン」や「日本文化私論」、「日本美の再発見」などの名著を著した。この中の「日本文化私観」の中で、タウトは、丸の内界隈の開発に触れて次のように書いている。(長文だが、示唆を含む文章なので引用する。) 「東京においては、かつて企業者の投機事業の犠牲として、宮城を囲む壕の一部が埋め立てられようとしたことがあるが、・・・幸いにして、ある私的有力者の発起で、この無謀な行為は阻止され、古き美の一部は救われることができたのであった。都会の美ーそれは企業家の思惑の統制および一般公衆の利益重視の程度如何に拠るものであると断言してよかろう。都会の美は芸術の対象であり、それを実現するのが、建築家なのである。・・・どんなに調和を持っている建築でも、その周囲が全く不調和を極めているとしたならば、それでは何にもならない。まるで掃き溜めの鶴のようなものである。・・・それゆえに、日本は建築家にまず高い社会的地位を与えることが必要であり、建築家自身も進んで果敢な闘争を試みることが必要だ。」 ここには、ユネスコ世界遺産の概念である「コア・ゾーン」と「バッファ・ゾーン」の概念が含まれている。つまり、皇居という造形的にも生態系的にも素晴らしい空間構成が東京のコア・ゾーンとしてあったとしても、周辺地域が、無秩序な開発思想で、都市開発が進められたとしたら、バッファ・ゾーンたるべき地域は、意味をなさなくなる。つまり孤立した旧江戸城の皇居は、台なしになってしまうということである。やはりここは、タウトの言うように、しっかりとした美意識と公共性に基づいた都市計画を行うようにすべきではないだろうか。そのためにも、議論をもっとオープンにして、日本の顔としての皇居を、タウトが指摘するごとく掃き溜めの鶴にしないよう論議を尽くす必要があると思われる。(佐藤弘弥記)
|