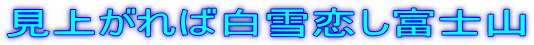

久々にゴルフに興じた。早朝、中央道を急ぐと、白い月が真っ青な西空に懸かり、夏の季節に冠雪を失った富士は、黒々とした山容を見せていた。コースを歩くと、薄の穂が夏の名残のある風に揺れる中で、蝉が命のひとかけらを燃やし尽くすように鳴いていた。
ふと芭蕉のあのふしぎな句が浮かんだ。「やがて死ぬけしきは見えず蝉の声」。芭蕉は、奥の細道で「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」という名句を残している
が、それ以外にも「蝉」に関する多くの句を残している。この句もそのひとつだ。蝉とは、芭蕉にとって命そのもの。蝉とはやがて命の尽きるはずの自らであ
る。
山寺で芭蕉が体験したことは、蝉の声が岩にしみ入るようにけたたましく鳴く命の営みだった。山寺に行ったことのある人間であるとよく理解できるが、山寺は
夏の頃、生命力そのものである大量の蝉が、けたたましい声で鳴く。つまり、騒音に近い状況を、芭蕉はあえて「閑かさや」と表現したことになる。
山寺の岩には地元の人々の遺骨が納められている。つまり蝉の生に対し、岩が象徴するものは死なのである。芭蕉は、この地方で営々と営まれている生と死の連
鎖を知ったとき、ある種の「悟り」を得て、蝉の声すら聞こえない心境に至ったと考えられる。そこでけたたましい「蝉の声」を「閑かさや」と表現し、この句
に不滅の命を与えたというべきである。
季節外れの蝉の最後のひと鳴きを聞きながら、ふと彼方を見上げると、若い薄の穂の向こうに、初冠雪を恋しそうにしている黒い富士山が聳えていた。
見上げれば白雪恋し富士の山 |
|