トマソンの定義
トマソンを定義すると、「使いようがなくて無用になっているけれども、何かたたずまいが変な物」というものです。ただこの定義だけではトマソンのもつ味わい、ほかの概念との微妙な位置づけまでは分かりません。それを分かってもらうために、そもそもトマソンが発見され、そして命名された経緯を紹介しましょう。
第1物件:四谷祥平館純粋階段
1972年のある日、赤瀬川原平・南伸坊・松田哲夫の3氏は四谷にある祥平館という旅館の裏を歩いていて、奇妙な階段があることに気づきました。普通階段には上がったところに入口がある。ところがこの階段には上がったところに入口がない。上がって下りるだけで、何の用事も足せない階段なのです。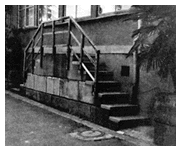 彼らは一旦は「入口を塞いで窓にした結果、本来なら要らない物だけど、『壊すのも大変だし、このままとっておこう』というので残ったのだろうな」と納得はしたのですが、手すりの補修の跡を見つけ、その結論は揺らぎました。本当にゴミであれば補修などしないはずです。
彼らは一旦は「入口を塞いで窓にした結果、本来なら要らない物だけど、『壊すのも大変だし、このままとっておこう』というので残ったのだろうな」と納得はしたのですが、手すりの補修の跡を見つけ、その結論は揺らぎました。本当にゴミであれば補修などしないはずです。この階段について考えをめぐらすうちに、彼らはこの階段に「機能上から見ると何も役に立たないけれど、ゴミじゃなくて、逆転するとものすごく崇高な物になる」そういった芸術作品に似た位置を見いだしたのでした。
第2物件:お茶の水三楽病院無用門
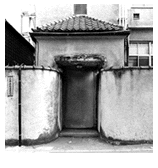 四谷の階段について話し合ううち、南氏が似たものがあることを思い出しました。お茶の水の三楽病院にあったその門は、門だけれども封鎖されて入れない。けれど塀がちゃんと湾曲していて、庇(ひさし)があって、ランプがついている。あまつさえそのランプは夜になると灯るのです。
四谷の階段について話し合ううち、南氏が似たものがあることを思い出しました。お茶の水の三楽病院にあったその門は、門だけれども封鎖されて入れない。けれど塀がちゃんと湾曲していて、庇(ひさし)があって、ランプがついている。あまつさえそのランプは夜になると灯るのです。見かけは全然違うけど、世の中にあるあり方が非常に共通している。用がないけど、捨てられずにいて、周囲の人間から無意識に保護されている。世の中にはそういう物件があるらしいということが次第に明らかになってきました。芸術と似ているけど、一層ゴミに近く、芸術を超えるものだということでこれらは“超芸術”と命名されました。
そして“トマソン”と命名
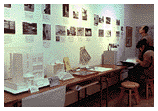 その後、当時赤瀬川氏が講師をしていた美学校で、一つの科目として超芸術を探すということが始められました。一方「写真時代」(白夜書房)誌上で赤瀬川氏が『超芸術』の連載を始め、共鳴する人達も増え、展覧会をやろうというところまで話が盛り上がりました。そうなると“超芸術”ではない、もう少し馴染みやすい名前をつけることが必要になってきたのです。
その後、当時赤瀬川氏が講師をしていた美学校で、一つの科目として超芸術を探すということが始められました。一方「写真時代」(白夜書房)誌上で赤瀬川氏が『超芸術』の連載を始め、共鳴する人達も増え、展覧会をやろうというところまで話が盛り上がりました。そうなると“超芸術”ではない、もう少し馴染みやすい名前をつけることが必要になってきたのです。いくつかの候補が挙がったのち、“トマソン”という名称が浮かび上がってきました。当時読売巨人軍に在籍していたゲーリー・トマソン選手は、大きな期待を持たれながら来日したものの三振が多く、全く成績がふるいませんでした。本来ボールにバットを当てるためにいながら全く機能しない、という点がまさに“超芸術”と同じだったのです。
このようにして“超芸術”は新たに“トマソン”という名称を与えられました。
トマソンの「味わい」
 以上がトマソンという概念が発見された経緯です。十分理解していただけたでしょうか。
以上がトマソンという概念が発見された経緯です。十分理解していただけたでしょうか。補足するならばトマソンには、芸術作品を見たときと同じような感動があります。そしてそれを意識的に作った人がいないという事実がさらに興味を惹きます。確かに人が作っているのだけれど、無用なものを作ろうと思って作ったのではなくて、しかたなしに修繕・造作していった結果がトマソンの形になった。そしてそれはもとから作品としてあるのではなく、私達がみつけて初めて作品になるのです。
言葉を重ねるよりも…
このようにトマソンとは発見して作品になるものですから、その製作の唯一の方法は実際に街を歩いて採集することです。採集といっても不動産的なものですからカメラで記録するということになります。ただ最初に挙げた定義だけを頭に入れて見ていくと、むしろつまらない物ばかり見つけることになる場合もあります。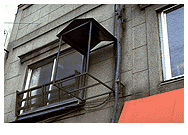 理屈からすればトマソンなんだけれど、別に面白くも何ともない物件もあるのです。本当にいい物件は定義に合っているかどうかを問題にする前にまずその美しさにうたれます。ですから、本当はこうして言葉を百並べるよりも、名品といわれるトマソンを見た方がはるかに理解しやすいはずです。
理屈からすればトマソンなんだけれど、別に面白くも何ともない物件もあるのです。本当にいい物件は定義に合っているかどうかを問題にする前にまずその美しさにうたれます。ですから、本当はこうして言葉を百並べるよりも、名品といわれるトマソンを見た方がはるかに理解しやすいはずです。
この文章の作成にあたって、CD-ROM「超芸術トマソンの冒険」(JUSTSYSTEM)に収録されている赤瀬川原平氏の言葉を大幅にお借りしています。