|
家族内殺人事件の 社会心理学的考察 (中) ー日本人のこころで何が起こっているの か?!ー 佐藤弘弥
(上)1ー6 承
前7 事例検証1【会津若松母親殺人事件】 「17歳の少年 母の首を持って自首」 昨年2007年5月15日(火)早朝、信じられないテロップが画面を流れた。 この頃、毎日のように様々なニュースが飛び込んでくる、さすがに昨年2007年5月15日(火)、会津若松で起きた17歳の高校3年生による実母殺害事件 を聞いた時には、己の目と耳を疑った。その後、背筋を冷たいものが流れたのを記憶している。自分の貧弱な想像力を完全に越えているとさえ感じられた。 これを狂気として片づけてしまうのは簡単だ。しかしたとえそれが、どんなに狂気じみたものに見えようとも、現代の日本に生きる若者の心が引き起こした事件 であることに変わりはない。その意味で、この事件は、何らかの社会性を帯びた事件として考察すべきだ。 それにしても、少年を一番愛しているはずの母親を殺害し、その首を持って自首するという悲劇的な事件を起こした少年の心で、いったい何があったのか。この 事件を紐解いてみることは、日本人の若者の心で起こっている何ものかを解明する糸口を見つけることに通じるかもしれない。いっさいの予断を持たず、事件の 真実を冷静に見ていくことから始めてみよう。 ◆事件の概要 事件の概要は、おおむね次のようなものだった。 07年5月15日午前1時半頃、福島県会津若松市内のアパートで、17歳の県内有数の受験校(県立)の高校三年生が眠っていた母親を殺害し、予め用意して いたノコギリでその首を切断した。そのご通学用のバッグに母の首を詰めてアパートを出て、深夜営業のインターネットカフェで、DVDなどを見て時間を潰 し、6時20分頃、携帯電話でタクシーを呼び、その首を持って7時頃警察に自首した。 少年は、会津若松から南西部に60キロ離れた金山町の出身。実家には祖父母、団体職員の父と保育士の母(47歳、事件の被害者)弟がいた。少年は男ばかり の3人兄弟の長男で、兄弟仲は良かった。ひとつ違いの弟(高校二年)とアパートを借りて、高校に通学していた。母は保育士の仕事をする働き者の女性で、週 末にふたりの兄と弟の世話をするためにこのアパートを訪れていて、今回の事件の被害者となった。尚、隣の部屋に寝ていた弟は、兄の凶行にまったく気づかな かった。 尚、この事件現場となったアパートで、少年による想像を越えた猟奇的な犯行が明らかとなった。 少年は、母親の首とともに、右腕も切断し、これをスプレーで白く塗って、プラスチックの植木鉢に挿し、そこに土を入れて置いていたというものだ。左腕も切 断しようとした跡が残されていたが、弟に気づかれると思い止まったものだという。少年は母の遺体をさらにバラバラにする意図を持っていたとのことだ。  5
月16日朝日新聞夕刊は一面トップで少年の凶行を報じた
◆マスコミ報道による少年のイメージ 同日の朝日新聞の夕刊は、少年について、次のように報道している。 『高校2年の時、同じクラスだった男子生徒(17)は、休み時間にも周りが騒いでいる中、1人で勉強していた少年のことを覚えている。「いじめられてい た、というわけではないが周りが近寄らないという感じだった。親しい友人もいるような様子ではなかった」と話した。 実家近くに住む親類の70代の女性は、少年について「礼儀正しく、いつも静かなええ子だった。いくら考えてもわからない」と、突然の事件に戸惑いを見せ た。 (中略)少年は中学時代、スキーの選手で、県大会でジャンプや複合競技で活躍。東北大会に出場したこともあったという。 近所の女性は「スキーのジャンプを一生懸命やっていて新聞で報道されたのも見たことがある。スポーツは万能だった。勉強もできて優秀だった」。』 またウィキペディアのまとめによれば、次のようになる。(※筆者注:尚、ウィキペディアでは、記事の原典の新聞記事各社とリンクを貼っていて、信憑性は高 いと思われるが、現在、新聞社自身が、原典となった本記事をリンク解除しているので、リンク先の数値は、本引用文からは削除している。) 『少年は中学校時代、スポーツ万能で欠席もなく成績も優秀で性格も明るく、何事にも一生懸命な優等生であった。県スキー大会の複合とジャンプでは上位入賞 を果たしている。だが、中学2年に受験勉強のためジャンプをやめている。通った中学は1クラス20人足らずの小規模中学校であったが、中学校の校長は「文 武両道。あらゆる分野で活躍していた」と少年を評している・・・。 (中略)少年は科学部に所属してはいたが、活動には全く参加していない・・・。 高校入学の頃から少年には精神的な不安定さが目立ちだす。また、一家は2007年2月7日に自宅が土砂崩れ被害に遭っていた。 高校3年になってからは5日間登校しただけで、2007年4月13日を最後に登校していなかった。4月半ば「同級生から嫌がらせされていて、学校に行きた くない」「親には相談できない」と別の学校に通学する親しい友人に漏らしていた・・・。だが、学校側は2006年11月に行った記名式のいじめのアンケー トを参考にいじめはなかったとしている・・・。 4月20日に市内の病院の精神科を一人で訪れ、不眠や学校に自分がなじめない事を訴えていた。4月27日には担任がアパートに行ったが、留守で会うことは できなかった。担任が少年の携帯電話にかけても少年が出ることはなかった。その後5月1日には母親と別の病院に行き、「精神的に不安定なので、登校を強く 促さないように」と言われていた。事件直前までうつ病の治療を受け、抗不安薬などの薬物を服用していた。それゆえ、一部では薬物の影響も指摘され た・・・。 母親は「学校に行く気力がわかないと漏らすようになったため、病院で診てもらった」と5月7日に学校に連絡する。これが最後の通信であった。別の学校に通 う親しい友人は5月13日に最後に会っているが、コントローラーを投げつけたりと、何かいらついている様な様子であった・・・。母親は、5月14 日は午後6時過ぎに仕事を終え、アパートを訪れていた5月15日は母親の47歳の誕生日だった。少年は、「弟でも良かったが、たまたま母親が泊まりに来 た」と述べている。』(ウィキペディア「会津若松母親殺害事件」の項) ◆受験のためにスキー競技を断念した影響?! まず、以上のことから、大雑把に少年のイメージを思い描いてみる。家庭は中流家庭で3人兄弟の長男。子どもの頃からスポーツも勉強も優秀で、近所では自慢 の子どもだった。特にスキー競技で、マスコミの取材で取り上げられたりしたこともあり、少年にとって、スポーツは、少し大げさに言えばアイデンティティと も言えるものだった可能性がある。 子どもの頃、少年は穏やかで挨拶もできる子だった。時系列でみると、中学二年において少年の心に変化を及ぼす事態が起きた。高校受験のために、それまで取 り組んでいたスキー競技を断念したことだ。私はこの中学二年で、スポーツを断念した時からの少年の心の動きに注目する。 人間誰でも、自分の得意分野というものがある。勉強が余り得意でなくても、手先が器用とか、抜群の運動能力とか、ところが少年の場合は、どちらも優れてい たために、周囲が過剰な期待をこの少年に掛けた可能性がある。周囲とはもちろん第一に実家の父母であり、また出身中学の教師ということになる。彼は、田舎 町の中学校において、少年はスキー競技において、県を代表して東北大会にも出場するほどの腕前だった。それに勉学も優秀ということで、中学校ではヒーロー のような存在だった。それが都市部の進学高に入学した途端に一変してしまう。これはよくありがちなケースだ。 田舎育ちの少年がいきなり、都市の生徒数も多い有数の進学校に入るとどのようなことが起こるか。会津若松の地元中学からの進学が圧倒的に多い中で、初めか ら孤立してしまう。急に友だちが少なくなり、自分の田舎町では、優秀だったものが、平凡な生徒になってしまうことがよくある。ここをうまく乗り切って、友 人を作り、部活などに精を出すようになればいいのだが、少年の場合は、孤立してしまった。しかも、少年は部活も自分の得意であったスキーではなく、科学部 へ入る。スポーツの得意な人間が、それを止めて、文化系のクラブに入る。これも大きな転落の始まりだったかもしれない。そこにはおそらく、親の意向や期待 もあったはずだ。少年の思いとは別のところで、親の期待が一流大学への進学という、進学校では当たり前のことであるが、徐々に少年は追い詰められて、自身 を失って行ったことが考えられる。 また、少年の実家が、「2007年2月7日に「土砂崩れ被害に遭った」という事実が気になる。というのは、この事件から10年前に起きた「酒鬼薔薇聖斗」 と名乗る少年が起こした「神戸連続児童殺傷事件」(1997年6月28日逮捕)の犯人「少年A」が、5千人もの人が亡くなった神戸大地震(1995年1月 17日)で被災していることがあるからだ。 ◆少年の供述の矛盾と本音を考える いったい何がこの少年を凶行にかき立てたのか、断片的な供述ではあるが、その供述は、大きな矛盾を孕んでおり、吟味してみる必 要がありそうだ。まず事件後、少年は、取り調べにも素直に応じ、「母親に恨みはない。誰でもいいから人を殺したかった」と言い、一方で「世の中からテロや 戦争がなくなればいい」というのは、少年の中で明らかに相矛盾するアンビバレンス(両面感情併存)な状態にある。 また「ホラー映画を見ているうちに人を殺したくなった」、「グロテスクなものが好きだ」などと、巷に溢れているホラー映画やマンガなどの影響もほのめかす 供述をしている。更に「「弟と母親への憎しみを隠すために、マスコミにセンセーショナルに取り上げてほしかった」とも。直接的な動機を聞かれると「別 に・・・」と答えたりしている。留置場での生活態度は、事件に対する改悛の情などは見られず、食事や睡眠も普通に行っているようだ。尚、事件後4ヶ月に及 んだ精神鑑定の結果は、「責任能力はある」との判断が下されている。 接見した弁護士は「普通の子」との見方をしている。それにしても、奇異に事件に見えるが、この事件で見え隠れしているのは、この犯人の少年の「冷静さ」と 「準備周到さ」である。殺害の凶器の準備から、殺害後、本人は「どうせ捕まる」との認識を持ち、証拠品として、母の首を通学で使っていたバックに詰め、イ ンターネットカフェで時間を潰し、自ら携帯でタクシーを手配し、会津若松署に自首するというものだ。まるでこれはタイムキープしながら、予め準備したシナ リオ通りに犯行を演じたような完璧さがある。この少年を乗せたタクシー運転手も、少年が冷静だったため、異変にはまったく気づかなかったという。 ◆少年の心を支配する「自己顕示」と「暴力への渇望」 私は少年のアンビバレンスな供述の裏に、「自己顕示欲」と「自己正当化のためのカモフラージュ(心理偽装)」があるように見える。その背後には、狂気の中 に冷静沈着な彼なりの計算が伺える。そして何よりも怖いのは、強い「暴力」と「グロテスク」なものへの強烈な憧れのようなものが見え隠れしていることだ。 そこで、私は少年の偽らざる心情は、以下のようにも言い換えられるべきではないだろうかと考えた。 それは「母に恨みがあった。母を殺したかった。世の中にも恨みがある。いっそ日本でも戦争やテロが起きればいい」というアナキズム的心情が意識(一部は無 意識として?)としてあることだ。 つまり少年は、真反対のことを供述していることになる。母や世の中に対する恨みを隠し、母の生首を持って自首するということで、マスコミにより「スキャン ダラス」で「ミステリアス」で「センセーショナル」に取り上げてもらえるとの強かな計算があるのではないかというものだ。もっと別の言い方をすれば、少年 は、恨みや反社会性という一般的な動機では、マスコミがよりセンセーショナルに取り上げてくれないと思っているのである。 少年は、少年なりの知識と判断力の中で、犯行計画を練り、それらのひとつひとつをまるでゲームのようにしてこの犯罪を実行したのではないだろうか。もちろ ん彼自身では、自分の犯行がどの程度の歴史性と社会的インパクトを持つものであるかを事前に知り得ているのである。この少年の中には、その程度の知能はあ る。しかし残念ながら、中学時代優等生だった地位から、進学校に入って、徐々に落ちこぼれとなり、運の悪いことに得意だったスポーツも断念したことで、自 己のアイデンティティを見失って、精神のバランスを失って犯行に及んでしまったものと考えられる。この犯罪の背後には、現代の若者を取り巻く、受験カリ キュラム全盛の教育システムの中で精神的ストレスを溜め込んでいる若者のうっ積した不満があることは明白である。 ◆「不登校」という少年の命の叫び 少年は、優秀であったが故に、親たちから過度な期待を掛けられ、また県内有数の進学校に越境入学したことで、悲劇は起こったと言うことも出来る。 また少年が、別の高校に通う中学の同級生に電話をしたという内容が妙に気になる。そこで少年は明確に「同級生から嫌がらせ」があったことを話し、「親には 相談できない」と言っていることだ。つまり、何らかの「イジメ」が少年に向けられ、このイジメを「親」にも「学校」にも、相談出来ない何らかの事情があっ たということだ。しかし当の学校側は、ご多分にもれず、少年に対し「イジメはなかった」との認識を持っている。今後、この母親殺人事件の背景として、学校 内での「イジメの有無」がクローズアップされてくる可能性がある。いずれにしても、不登校には何らかの理由があったはずで、それは少年自身の「助け て!!」という無言の叫びだったのである。その叫びをくみ取れなかった親も学校側も、何か打つ手はなかったものかと悔やまれる。 ◆母の首を取ったことの神話的意味について さてイギリスの人類学者フレイザー(1854−1941)は、その著「金枝論」二十一章「タブーとされるもの」の中で、「頭」を上げ「多くの民族が頭を特 別に神聖なものと考えている。」(永橋卓介訳 岩波文庫版(二)164頁)と言っている。そしてさまざまな民族が、どんなに頭を神聖なものとして、見てい るかをこれでもか、とばかりに例示している。 例えば「マルケサスの人間なら誰の頭でもタブーであって、他人はこれに触れてはならず、跨いではならなかった。眠っている子供の頭ですら、父親といえども 跨いではならなかった。」(166頁)あるいは「タヒチ島では王や王妃の頭に手を差し出した者は殺された」(同頁)としている。 確かに日本でも、他人の頭に簡単に手を触れるなとは良く言われることだ。エピソードとして、奥州での後三年の役(1083)があったおり、源義家の臣下と して鎌倉から駆け付けた鎌倉景政(かまくらかげまさ)は、敵の矢を右目を受け、これを抜くために、顔(頭)を踏んで抜こうとしたのを者を「人の頭に足を乗 せるとは何ごとか」と叱り飛ばして、跪かせてその矢を抜かせたというのがある。 下って戦国時代、戦において、敵の首を取ることは、勲功を上げることだった。男たちは、立身出世のために、少しでも身分の高い武者の首を取ることに血眼に なった時代もあった。 漢字学者の白川静氏(1910−2006)によれば、そもそも「道」の語源は、敵の首を持って、辻辻を歩いていくことを、語源にしたものであるとの解釈が なされている。 このように考えてくると、人の頭を取るということは、それ自体がタブーへの挑戦であり、戦という敵というものに対峙した時にはじめて許される行為である。 フレイザーによれば、戦争の勝利した時ですら、敵の首を取った者は一定期間喪に服したり、肉食を避けるなどの時を過ごして、悪霊からの祟りをやり過ごした のである。 考えてみれば、今回この少年は、首を取り、かつそれが母親の首であるという点において、二重の意味でタブー(禁忌)を犯してしまったことになる。真に恐ろ しいのは、この少年が、漠然とではあるが、今回の母親殺しの歴史的意味をセンセーショナルな意味を認識していることだ。要するに人間は、長年タブーとして きた母親殺しという犯罪領域に足を踏み入れてしまったということになる。それは単純に言えば、母親という存在が「一番力の弱い社会」の象徴だったからに他 ならないと思う。 そして最後に、今回の少年の信じがたい犯罪行為(家族内殺人)について、これをいささか、神話的に解釈するならば、母を敵と見立てて、その首を取って、意 気揚々と引き揚げる凱旋する勝利者のイメージすら私は浮かんでくる。早計かもしれないが、少年にとっては、ひとつの「戦の代償行為」であったかもしれな い。それは、「・・・マスコミにセンセーショナルに取り上げてほしかった」などという少年の自己顕示的な供述からも十分頷けるものと思うのである。 8 世界中で蔓延するテロと戦争報道に曝される子どもたち 次に、日本社会において、家族内殺人がひん発する第4の背景として、世界中でテロや戦争が蔓延していることを論じることにしたい。 考えてみれば、前節の犯罪事例で論じたように、少年たちは、ほとんど毎日、テロや戦争の情報や映像を目にしている。その影響は計り知れないものがあ りそうだ。そのことは、少年の供述に端的に表れているように思われる。 「世の中からテロや戦争がなくなればいい」 今、改めて、実の母を殺害した少年の言葉を噛みしめてみる・・・。 これが少年の本音か、それとも自分が犯した重大な犯罪に対する自己正当化か。その判断は意見の分かれるところである。私は、この言葉を、反すうしながら、 かつてチャップリンが映画「殺人狂時代」(1947年作品 原作オーソン・ウェルズ)の中で言った名セリフを思い出した。 「一
人を殺せば殺人者だが、戦争で百万人を殺せば英雄となる」
チャップリン演じる殺人結婚詐欺師が開き直ったように吐いた社会風刺の利いたシニカルなセリフだ。 映画の設定は、35年間、銀行員として真面目に務めたていた男が、大不況の煽りで失職し、足の不自由な妻と幼い子を養うために、悪の道へ転落していくとい うストーリーだった。男は、裕福な女性を狙って結婚詐欺を働いては、彼女たちを次々と殺害し大金をせしめていく。このセリフは、戦争当事者と戦争犯罪とい うものに対するチャップリンというひとりの映画人が全人格を賭けて世界中に発した恒久平和への祈りと解すべきだ。 私は、母を殺害してしまった少年のいびつになってしまった心を憐れむ。何を言うかという人がいるかもしれない。もちろん私は、母殺しの少年を褒めるつもり もヒーローにする意志も毛頭ない。しかしチャップリンの名セリフと、少年の言葉が、私の中で妙に響き合うのである。 少年は、現代に生まれ、日々、テレビ映像やインターネット上で、テロとそのテロに対する報復の戦争の凄まじいばかりの暴力を見せつけられながら17年間を 生きてきた。そして少年は、親や教師にせき立てられるように「受験戦争」と呼ばれる世を生きらざるを得なかった。 この会津若松の少年の心の足跡(そくせき)を辿れば、おそらく物心を付いた時から、テロと戦争による暴力を見て育っているはずだ。例えば、2001年今か ら7年前、11歳だった少年は、ニューヨークで起こった9.11の凄まじいテロシーンをテレビで生々しく目撃したはずだ。茶の間の少年が、WTCのふたつ の高層ビルに旅客機が突っ込むシーンを目撃した時、特撮では考えられない戦慄を感じたはずだ。その後に起こったビルの倒壊と数千人の人々の死という悲劇が あった。 アメリカでは、これを機に急速にナショナルな感情が津波のように起こって全米を覆って、ブッシュ政権は、報復の戦争(アフガニスタン介入=空爆開始は 2001年10月7日)を宣言した。 日本政府も同盟国として、直ちにこれに同調した。小泉政権は、対テロを口実としたアフガニスタン介入という「戦争」に海上給油という形で後方支援を行うた め「テロ対策特別措置法(2001年10月29日)」を通すなどした。 この結果、事実上、日本国憲法の精神である「9条」は骨抜きとなったことは記憶に新しい。その後、アメリカは、核兵器開発の疑惑を強調し、イラク戦争 (2003年3月19日)を起こす。しかし後に、イラクに核兵器が存在しないことが分かる。アメリカが介入したアフガニスタンに臨時政府を樹立したもの の、タリバン勢力の抵抗は止むことなく、またイラク情勢は、国内テロがひん発する状況にある。 私たち日本人大人の目からも日常茶飯事となった凄惨なテロ現場からの報道を目の当たりにして、テロや暴力に対する「慣れ」のような感覚が醸成されつつある のを感じる。もっと言えば、暴力によって、人間の尊い血が流れ、命が失われることを何とも思わないようになってしまっているところがある。いわんや少年た ちは、まだ心が未成熟なのである。 人間の心は、幼児の頃には、真っ白いままだ。コンピューターで言えば、ソフトがインストールされていないマシンである。やがて、家庭や学校による教育に よって、子たちの心に、はじめて考える力が芽生えはじめる。 子どもの心は、大人社会を映す鏡と言われる。もしも現在の子どもたちが、どこか感覚的に影のようなものを引きずっているとしたら、それは大人社会そのもの が持っている影ということができる。 子どもの心が正しく成長するためには、テロや戦争などの暴力的な暗い影を経験させる時には、大人社会の悪しき部分として、明確に教え込む必要がある。しか し日本社会は、子どもたちの心を、養成していくためのシステムが少し不足している。それは、どうしても少しでもいい学校に入学させたいという親や教師のエ ゴが反映している結果、どこかに教育に歪みが生じていることから来ているのではないだろうか。 また、今や、日常溢れているテロや戦争の暴力を、肯定するような風潮が、政治家ばかりでなく、社会全体にあるような気がする。インターネットの有害サイト は、フィルタリングによって、一定程度隠すことができるが、現在世界中で日常茶飯事起こっている暴力的なニュース全体に、フィルタリングを掛けることは難 しい。したがって真実の報道は、大切だが、子どもたちへの影響度まで考えて、しかるべきコメントなどを付け加えるなど、報道機関各社は一層工夫する必要が あるのではないだろうか。 次回は、昭和19年度版「国民生活白書」と「青少年白書」の重要項目の分析を通して、日本の青少年の心の成長の障害となっている問題点を洗ってみたい。 9 最新版「国民生活白書」を読む 家族の結びつきの希薄化とは?! 今私の前に内閣府が発行した平成19年度版の二冊の白書がある。ひとつは「国民生活白書」(以下「国民白書」と表記)。もうひとつは 「青少年白書」 である。ふたつの白書を、それぞれ分析していく中で、ひん発する「家族内殺人」の根底にある日本人の人生観や子どもたちが抱えている諸問題に光を照射して みたい。 19年度版「国民白書」には、この白書を一貫して流れるキーワードがある。それは「つながり」あるいは「つながりの希薄化」というもの で、この白書の副題がそもそも「つながりが築く豊かな国民生活」となっている。 この「つながり」を、別の言葉で言い換えるなら、「結びつき」のことである。この「結びつき」が、日本社会の中で、いつの間にか、「希 薄化」してしまったことは、日本人の誰もが否定しようのない事実との認識を共有しているのではないだろうか。 まさに「つながりの希薄化」という表現は、現代を生きる日本人の人間と人間の結びつきを象徴する言葉として、私自身も「なるほど」とう なずいてしまった。 考えてみれば、「核家族化」も「都市化」も、敗戦後の日本社会において、「高度成長」と言われる時期を通して起きた農業社会から工業社 会への変化に伴って起きたものである。 今回の「国民白書」は、大雑把に分けて、4つの「結びつき」の現況とその原因を探ろうとしているように見受けられる。その4つとは、第 一に「家族」 第二に「学校」第三に「地域」第4に「職場」である。特に「家族」には多くの紙面を割いている。このことは、現在の「結びつき」の中で、家族間の問題が、 非常に大きくなっているということを、この白書をまとめ上げる段階から編者である内閣府自身が持っていたということになるのではなかろうか。 実際、現在の日本人の家族の間で、人間心理として、どんな感覚で、生活を行っているが、少しばかり見えるような統計があった。 それは、日本人の「家族観」というものを象徴する次の統計だった。 まず次のグラフ1(第1ー2−1図=36頁)を見ていただきたい。 
このグラフは、「あなたにとって一番大切なものは何か」という質問に対する
回答である。これを見て、一目瞭然なのは、「家族」というも
のをもっとも
大切だ、とする人生観が高まっていることである。ほぼ1968年から、家族と答える人の割合が、右肩上がりで高まっていて、2003年には、45%の人が
「家族」と答えるまでになっている。
「家族」の次に高いのが、「生命・健康・自分」というもので、自分の健康を大切
にして、生きがいを持ちたいとの気持が伺える。それで
も、その割合は21%であり、一位の「家族」とは比較にならない。次が「愛情・精神」というものだがわずか13%に過ぎない また、この定性的分析によって、顕著なのは、「国家・社会」、「家・先祖」、 「仕事・信用」、「金・財産」というものに対して、相対的 に、人生において、もっとも大切と言えるものではない、とする価値観が生まれていることだ。 これは戦後の欧米流の個人主義的な価値観が、一般化し、国家や家や会社というも のに対する帰属意識が希薄化している傾向を如実に物語る ものではないかと思うのである。 そこから、では「家族」への帰属意識はどうか、という問題が生まれてくる。戦後 の社会構造の変化に伴って生まれた人生観の変化がある中 で、「家族」というものだけは、今でも「一番大切だ」と答える人が、何故このところ急増しているのか。このことを考えてみたい。 「国民白書」は、家族内での「つながりの希薄化」について、家族という集団その ものが、たとえ同居しながらでも、さまざまな事情で、一 緒に過ごす時 間が少なくなっていることを指摘している。その一番の問題は、家族が、仕事の関係やら共稼ぎやら、子どもの塾通いが一般化したことから、顔を合わす機会が 少なくなっていることだ。 特に、2006年度の統計グラフ2(第1ー1−7図=15頁)では、父親のほぼ4人に一人(23.5%)が、平日にはほとんど子どもと接していない、と答 え ている。母親の方も、最近では、4分の1(24.4%)の家庭で、30分以内の接触しか子どもと接していない現状が浮き彫りになっている。これは明らかに コミュニケーションの不足である。
この親子のコミュニケーションの希薄化を国際比較でみると、次のグラフ3
(第1ー1ー13図=20頁)になる。
これを見ると、顕著なのは、日本の父親が、韓国の父親についで、わが子との接触 が少ないのに比べて、母親との接触が、一番長いというこ とである。ここから、日本における子育ての現状が、母親依存型であることが明白となる。 ただ最近は、格差拡大の日本社会は、父親の給料が上昇しないという傾向が顕著 で。そのために、家計を助けるということで、母親もパート タイマーや、 結婚前に働いていた職場や技能をもって働く女性も増加しており、今後ますます、親子の接触は少なくなってしまうことが予想される。実際の統計でも、「働く 父母の平日の帰宅時間の推移」のグラフ4(第1ー1ー17図=23頁)のように、父親も母親も帰宅時間が遅くなる傾向がある。
このように見てくると、現在の冒頭で、「あなたにとって一番大切なものは何
か」として、多くの人が「家族」と答えた背景には、どこか「温もりの包ま
れた一家団欒の家族」というものへの郷愁のような気持があるのではないかという推測が成り立つのではないだろうか。つまり統計に回答をした人は、自分の家
族を取り巻く厳しい現実を思いながら、一方では、そうではない理想の家族のイメージを、この国民生活白書は表しているのではないかと思うのである。
次に「青少年白書」について見ていくことにしたい。
10 最新版「青少年白書」を読む 「児童虐待」と「いじめ」社会・
日本
最新版「青少年白書」の冒頭にある一枚のグラフ1(第1ー1−2図=3頁)
を見ながら、しみじみと思う。いったい戦後60数年間の間に、日本社会がどのよ
うに変わったのか。またそのために日本人の心の中で、どのような価値観の変転が起こったのか、と・・・。
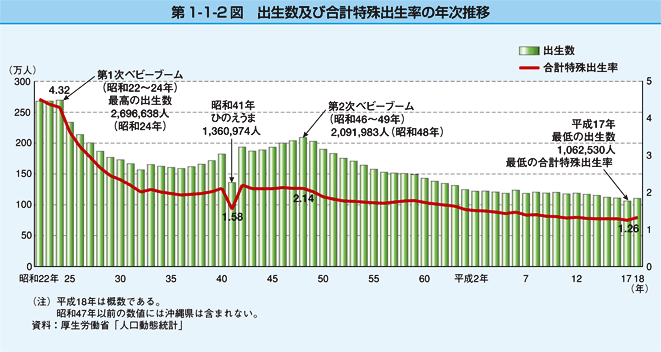 ◆明
治維新から第二次大戦の敗戦までの日本人の熱
明治維新後の富国強兵と国家を挙げた欧化政策によって、アジアの俄(にわか)軍事大国となった日本は、日清・日露の戦争で戦勝国となり、少し増長した勢い でアジア諸国に戦線を拡大した。最後にはアメリカを敵に回して自滅してしまった。それでも、長い徳川300年間の鎖国政策から一転、明治維新以後、ほぼ 50年間で、科学技術から政治体制まで、欧米諸国にこれを習い、受容しようとするエネルギーは、凄いの一語だ。ここに私は良い悪いを抜きにして、日本人の 潜在的能力を感じる。 明治維新以降の日本人の心には、ある種の全体主義的な熱狂があったことは否定できない事実だ。この熱狂の奥には、徳川300年間の封建制度の中でひたすら 内へ内へと心的エネルギーを半強制的に昇華させられてきた歴史に対する反発のような感情があったの だろうか。元々日本文化の中には、聖徳太子や織田信長が仏教やキリスト教などの日本人にとって未知の宗教を積極的に受け入れようとしたように新しい外の文 化や文明に対する受容精神があると言われる。西洋列強のアジア進出という政治的圧迫を受けながら、日本社会と日本人は、このままでは、西洋列強の植民地に なるという危機意識を持ち、明治維新という改革を成し遂げた。その帰結として、軍事力の増強は、日清・日露戦争を招来し、軍部の政治力を強めた。こうして 日本の暴走は始まったのである。 第二次大戦の敗北は、言うならば、日本人の「暴走」からの目覚めであった。しかしこの大戦の損害と犠牲は、余りに大きかった。日本人は、この戦争を機に、 戦争の悲惨と無意味さを実感し、二度と戦争の惨禍に見舞われないようにと、世界に魁けて、戦争放棄を謳った画期的な平和憲法を公布したのであった。こうし てそれまでの全体主義的な思想を捨てた日本は、世界で初めて非戦の誓いをした民主主義国家として生まれ変わったのである。 第1のグラフを見る時、戦争へ向けられていた国民のエネルギーが、この出生数の縦棒に如実に示されるごとく、日本経済を復興さ せようと転換されているのを実感する。しかし第二次ベビーブームと言われた昭和46年(1971)から昭和49年(1974)をピークとして、子どもの出 生数は減少に転じ、日本社会は少子化の方向へ向けて歩み出す。 また単に少子化するというだけではなく、二代、三代と複数の世代が同居していた大家族から核家族の時代へと移ることも、日本人の「家族」というものに対す る価値観に大きな影響をもたらしたと考えられる。しかしながら、一方では、「国民生活白書」に示された通り、親子の関係は、希薄化していった。そして、ど ちらかと言えば、母親が父親の役割まで行うような母親中心の偏った親子関係が生まれ、父親の影は、家族内で極めて薄くなってしまったのである。 ◆児童虐待をする親の実態 最新の「青少年白書」を見ながら、私はふたつのことを思った。ひとつは、児童虐待という親が子どもに対して行う犯罪行為がこの10年で、激増している事 実。もうひとつは、いじめ問題が、なくならず高原状態で推移していることだ。まず児童虐待の問題から論じたい。 「児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数」の表1(第1ー2ー22表=19頁)を見ると、空恐ろしくなる。平成2年(1990)の1101件か ら、平成17年(2005)では34,472件となっている。数から言えば31倍に増えていることになる。異常な増加率である。 これは、若い親たちが、子どもとどのように接してよいのか分からなくなっている様を如実に物語るものだ。さまざまな原因が考えられる。最近では、若い夫婦 の離婚率非常に高くなっ ていて、相手方の連れ子を、虐待して、死に至らしめるような非常識な事件も、多発している。このことは、子どもを教育する立場の親自身が、親の自覚もない ままに、子を育てる立場にいるというおかしな状況が起こっていると見ることもできる。あるいは、恋愛すらマニュアル化された現代社会にあって、マニュアル のようにはいかない子育てという幼児教育は現代の親たちがもっとも苦手なことのひとつかもしれない。 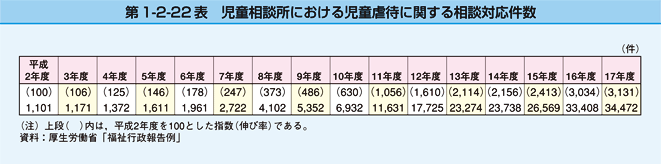 今から、20年ほど前、私は、母親が自分の娘である幼児をどう見てもイジメ
ているとしか思えない現場を見てしまったことがある。おそらく育児ノイローゼだ
と思うが、その20代後半の年齢の母親は、何かあると、すぐに2歳位に見えるわが子を叱り、そして頭をパンと叩くのである。その度に、子どもは泣き出すの
であるが、そうすると、母親は、更に怒り出して、怒鳴り、叩くのである。異様な光景だった。
私はその時、この少女の心が大きく傷ついていると思うと同時に、この少女は、近い将来母親に反抗するな、と感じた。もっと手短に言えば、将来母親は復讐さ れるはずだ、と直感したのだ。 この母親の性格は、社会が作ったものである。おそらくご主人が、仕事か何かで、忙しく慣れない育児に付きっきりの母親が、疲れ果てノイローゼ気味になっ て、その症状がどんどんとエスカレートしていたものだったはずだ。もしも仮に、この若い母親が自分の父母と同居していたなら、状況は大きく違っていたに違 いない。 子どもたちの暴力ばかりが、多方面からさまざまに批判されているが、子どもの 家族内暴力の発端には、面倒を見切れない親に対するうっ積した怒りや憤り、あるいは復讐心のような感情もあるのではなかろうか。むしろそちらの方が大き い。少なくても私はそう思う。子どもは、親に守られて、成長するものである。ところがこの親が守るどころか、子を虐待する昨今の親子事情は、日本社会でも 大きな問題となっている。その 原因は、さまざま考えられるが、最近の統計では、子どもの頃に親に虐待されて育った親が、同じように子を虐待してしまう親になってしまうケースがあるとい うことも言われる。つまりこれは、親にされたことを自分の子どもにしてしまっていることであるが、このような虐待の連鎖を止める運動を起こす必要があるこ とを実感する。親が守れない子をどのように社会が保護するか、これは大きな問題である。 ◆いじめ問題と教師への校内暴力の横行 ふたつ目の問題は、「いじめ問題」である。文科省が公立学校でとった数値が示されているが、この統計表2(第1ー5−9表=44頁)はおそ らく氷山の一角だろう。もっと、もっとある可能性が高い。例えば、先の「事例検証1」で取り上げた母親殺しの会津若松の高校三年生も、当事者の高校では、 「イジメはなかった」という認識を 語っているが、本人が「あった」と事前に友だちに電話相談をしているのだから、間違いなく、あったのだろう。それでも、当事者の教師たちは、ついつい、隠 してしまう傾向にある。単に責任逃れとは思いたくないが、学校かあるいは、最寄りに、子どもたち(もちろん親も)が、何でも困ったことを相談できる施設を 創設することが必要ではないかと感じる。特に公的なものではなくても、民間のNPO組織のようなもので、身近で手軽なものが良いと思う。 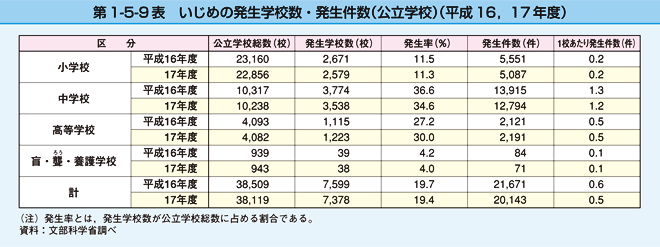 このイジメという問題は、何も子ども社会の問題ではない。このイジメには、
日本社会全体が抱えている弱い者イジメの影響を受けているという側面がある。つ
まり大人社会が、子どもの社会に鏡のようになっているのである。日本社会は、現在、格差社会と言われ、強い者がますます強く弱い者がますます弱くなってい
く傾向にある。例えば、この10年間で、一億中流と呼ばれた比較
的均質だった社会構造は壊れて、低所得で生活する大多数の国民と官僚や政治家や大企業の一部のエリートたちの層に二極化してしまっている。この社会構造そ
のものが、日本社会のイジメを形成している根本にあるイジメの社会構造だと私は思うのである。
それから校内暴力に関して、教師への暴力行為(第1ー5ー13表=46頁)が、増加の一途を辿っていることだ。いかに小学生自身も高学年になると身体が昔 より大きくなったとは言え、自分の師である教師に向かって暴力を振るうという事件がジワジワ増えていることはゆゆしき問題である。単に教師に対する暴力 は、権威者に対する反抗という以上に、教育の本質である社会規範を習うべき学校内において起こっていることであり、これを未然に防ぐことができないのであ れば、学校の存立そのものが危うくなる。また教師への暴力は、家族内暴力にも、たちまちエスカレートしていくことが考えられる。その意味でも、学内から暴 力を一掃する緊急対策を実行することが必要だ。 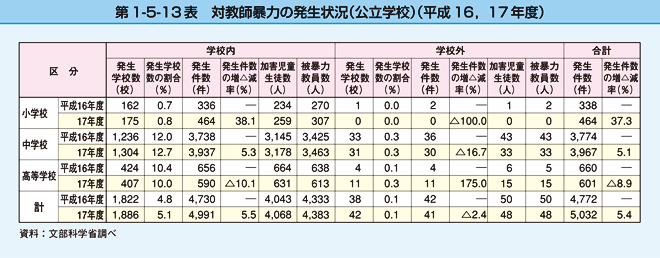 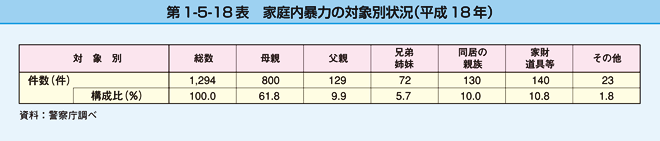 ◆ま
とめと感想
「国民生活白書」と「青少年白書」を見てきた。このふたつの政府が作成した白書を読みながら、少なからず、問題点がはっきりしてきたと思う。 それは現代の子どもをたちを取り巻く生育環境が非常に厳しいという現状である。私は、かつて、もう一度子どもからやり直してみたい、と漠然と感じたことが あった。しかしたった今、ふたつの「白書」を読み終えてみて、その思いが急速に萎えていくのを感じた。 現代は子どもが生きにくい時代だ。言うならば現代日本は「子ども受難の時代」と呼称したいような時代ではなかろうか。 その理由の第1は、受験戦争の狂躁の中で、容赦なく選り分けられていく厳しい現実だ。この受験中心の生活を強いられる中では、子どもが子どもらしく、明る く楽しく生きられる時代ではない。今や都市部の子どもたちにとって、公立校は、差別される対象になりつつある。また一流大学に有利な私立受験校(中高一貫 校も増加中)に入るには、親の負担率も非常に高い。その結果、日本社会に給与所得に格差が拡大している現在では、一流大学に入学する確率も、親の経済力に よって大きく左右される現実がある。子どもは、家庭で、学校で、日々受験によって、心を傷つけられている。 またそうして選り分けられた子どもたちが、現在親の世代となってきているのである。そこには、運良く、エリートコースに乗った親も、逆にエリートコースを 外れ、石川啄木の短歌にある「働けど働けど楽にならざり」のワーキング・プアに陥っている親もいるはずだ。 どちらの親も、自分の子どもだけは、後悔の多い人生を送らせまいと、子どもに多大な期待を掛ける。子どもは否応なしに、親の期待をプレッシャーとして頑張 るのであるが、うまく行く場合とうまく行かない場合がある。 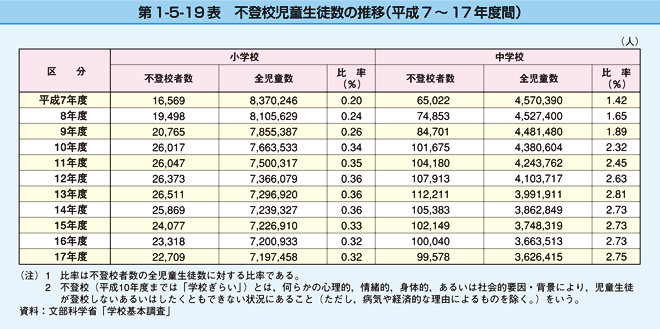 「国民生活白書」から日本社会では、特に母親が、父親の分まで、親を勤め上
げ、母性と父性の両方を持って、過保護、過干渉と呼ばれる親子関係が生まれてい
る現実が浮き彫りになった。多くの心理学者が「父性の喪失」という問題を提起しているが、家族問題の根底には、この問題横たわっている可能性がある。その
結果、母親に子どもの暴力のベクトルが向かってしまう傾向があるのかもしれない。
次回は、日本社会における父性の喪失という問題の所在を事例を検証しながら確かめてみることにしたい。 つづく
|
|||



