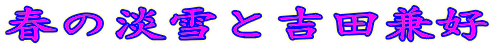

小廬山から淡雪の小石川後楽園を望む
(2010年2月2日撮影)
|
東京に二年ぶりの雪が降った。早朝、うっすらと積もった雪の上をさくさくと踏みしめ、これを竹箒でザッ
ツ、ザッツと掃いた。朝日を浴びて眩しく輝く、白雪はやはり美しい。
徒然草の吉田兼好(兼好自選歌集)に、こんな雪の歌がある。
はかなくてふるにつけても淡雪のきえにしあとをさぞしのぶらむ
兼好は、春の淡雪が次々と降ってくるのだが、降る先から、溶けて消えてゆく、そのはかない様に歌を詠みたくなるような風情というものを感じているのであ
る。
降りながら消える、というのは、人の人生にも連なる儚さがある。宇宙の時間で考えれば、確かに人の一生は、宇宙の瞬きにもならない一瞬の光芒に過ぎない。
人は生まれたと思えば、死ぬ、そんな運命にある。
でも、ここからが、兼好の凄いところで、この儚い世そのものを、超積極的超肯定的に受け入れる性格にあるように思う。
同じ歌集にこんな歌がある。
浮きながらしばし漂ふ水の泡の消えなですまぬ世とは頼まず
この歌は、「としすけ」という知人が亡くなった時に詠んだ歌と詞書きがある。その中に、結縁経の「世皆不牢固如水沫泡炎」(世は皆、牢固でなく、水の泡沫
の炎の如し」が引用されている。つまりこの歌は、この知人の人生が、固い牢獄で過ごした浮世に漂うような儚い一生とはまったくかけ離れた、水の泡沫が炎の
ごとく立ち上るようなものだったとその人の一生を讃えているのである。これは兼好の人生に対する考え方の根幹を成す思考だ。
この思考法は、フランスの哲学者パスカルが名著「パンセ」の中で語った「人間は一本の葦
(あし)に過ぎない。しかしそれは考える葦である。」という思考に近いものだ。
この兼好の人生論は、とかく日本文化というものを、弱々しい人生を儚く=否定的に見がちなステレオタイプの日本文化に対する間違った認識とは、180度違
うものだということを再認識した。
そういえば、兼好は徒然草の第七段で、次のように言っている。
「あだし野の露消ゆる時なく、鳥部山の煙立ち去らでのみ住み果つる習ひならば、いかにもののあはれもなからん。世は定めなきこそいみじけれ。」
「あだし野」とは墓地、「鳥部山」は火葬場である。つまり兼好は、墓地もなく、火葬場もなく、人が長く生きるような世の中であったら、世の風情もへったく
れもない。人の一生は、定めがなく、明日のことなど分からないからイイのだ、と思っているのである。
世の中の価値観が目まぐるしく変化変動し、昨日勝者だった者が、あっさりと否定されて敗者となる。あるいは若かった者が老いの身の上となり、杖を頼りによ
ろよろと歩む。この世の現実に起こる陰翳を、少しも憂えることなく、それも風情と淡々と見つめる吉田兼好の眼は、たとえ知人が亡くなった際にも変わらな
い。このような人間が中世に存在したことを日本人は誇りとすべきだ。
東京に降った雪を眺めながら、日本文化の奥にある深い思考に触れた気がした。 |
|