Horsfield's Tortoise
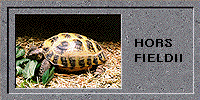
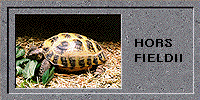
ホルスフィールドリクガメは様々な名前で呼ばれています。
Middle Asian Tortoise, Central Asian Tortoise, Steppe Tortoise, Horsfield's Tortoise, Russian Tortoise
Afghan Tortoise,Four-toed Tortoise などです。以下ホルスとします。
ホルスは、1944年にGrey によって最初に報告されて以来、Testudo(地中海リクガメ)属に一般的には置かれてきました。Mediterranean tortoises (地中海リクガメ)と呼ばれるリクガメには、他に
Testudo graeca, T.hermanni, T.marginata, T.kleinmanni (ギリシャリクガメ、ヘルマンリクガメ、マルギナータリクガメ、エジプトリクガメ)がいます。ギリシャリクガメについては、ギリシャリクガメについてのなかで詳しく述べます。
しかし、その習性や、生息地、体の機能などから、Testudo属とは別のAgrionemys horsfieldi
(Agrionemys 属 の種としてのホルスフィールドリクガメ)という分類が1980年代半ばに提案されました。最近は、こちらの分類のほうが有力になっているようです。
ホルスの生息地はロシア南東部、南部東部イラン、パキスタン北西部、アフガニスタンで、カスピ海の東部という地域になります。気温、湿度については、ハウジングのページを参照して下さい。
また、降水量を見てみますと、東京で年平均1405mm程ですが、ホルスの生息地のあたりでは、年平均で154〜400mm程しかありません。これは、東京における6月1カ月ちょっと程度の降水量ですから、かなり乾燥していることがわかります。日本の気温よりも湿度がホルスにとっては重大な要因となってきます。ホルスの生息地域はリクガメの生息域の北端です。
乾いた、ゴツゴツした岩の多い砂漠地帯や丘陵地やローム質のステップなどに生息していて、高度も海抜1500メートルから、それ以上の地域です。そのような生息地の中の、泉や小川の近くで植物が茂っている場所で生活している訳です。泳ぎさえしませんが、ある程度は水の中を歩き回ることも知られています。
ホルスの大きさですが、成体で甲長5〜7インチ(12.5〜17.5センチ)、8インチ(20センチ)以上あるのはまれです。背甲はかなり扁平であり、色は、明るい黄褐色から黄緑色の地に黒や茶色の模様がはいります。腹甲は、黒か茶のしみのような色になっています。他の地中海リクガメにしばしば見られる、前腹甲板と後腹甲板の間のヒンジはありません。シッポの脇の縁甲板は、少し広がっていて、雄のほうが雌よりも顕著です。また”四指リクガメ”の俗称の示すようにそれぞれの足の爪は、他のリクガメと異なり4本です。
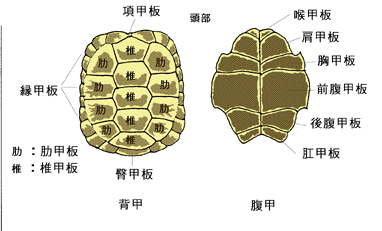
雌雄についてですが、ホルスが性成熟するのには、10年程かかります。幼体のうちは、ほとんど区別できません。3年から4年程度で少し判別可能になってきます。雄は形態的にはシッポが長くなり、甲羅に収納された時に腿に対して横向きになります。雌のシッポは短く、大抵まっすぐになっています。しかし、個体差がありますので、他のリクガメよりシッポだけで判別するのは、かなり成熟してからのほうが確実です。雄は、3年から4年目くらいから、時々総排泄孔からペニスを出す光景が見られるので判別できます。また腹甲は雌雄ともに平らで、雄だからといって凹んでくることはありません。成長したホルスは雌のほうが大きく、6から7インチあるのに対して雄は4から5インチと言われていますが、これも個体差がありますし、飼育下では食事によってずいぶん差が出てくるようです。
性格的には、雌雄ともに活発です。雄のほうが活発であることが多いのですが、マウンティングの行動(一般的には雄が生殖のため雌の上に後ろから乗る行動)が見られたからといっても雄であるとは限りません。生殖行動については、ギリシャリクガメなどに見られる、甲羅を雄が雌にぶつけるといった行動は備わっていません。それらの行動に対しては大変無防備で、ホルスを他の種といっしょに飼育していたりすると、ホルスの雌は甲羅にかなりダメージを受けてしまい、出血したりもしますので大きなストレスを受けることになります。けしておすすめできません。雄は雌の周りをうろうろし、正面にまわって雌の顔を見据え、首を上下に振ってアピールします。時には雌の首や顔に噛みついたりもします。飼育下であまりに過度に雌が噛まれるようならば、攻撃的な雄としばらく隔離する必要があります。いちどうまくつがわせられるとホルスは、5年間程は卵を産みつづけることが可能です。
ブリーディング(繁殖)については、別のページを参照して下さい。
日常の行動は,飼育下では、かなり活発ですが自然の状態においては、1年の内に活発に活動する期間は大変短いのです。1年のうちわずか3カ月程です。春先の3月から5月頃に冬眠から覚めてすぐにパートナー探しを始め、5月から6月に雌は2から6個の卵を産みます.時にはもう2から3個の卵を産むこともあります。卵は自然の状態では80から110日程孵化するまでにかかります。
6月から7月までは活発に動きますが、気温が32度から35度になる夏場には、大抵地中に穴を掘って中におり、気温が下がった時か夕方から夜にかけて餌を探しに出てくる程度です。そして1から3カ月程は、地中に掘った穴にふたをして、夏眠します。秋には冬眠に備えて再び活発に活動して、食べまくります。活動中もホルスは、夜間は地中に80から200センチ程の長さの穴を掘って眠ります。彼らが穴堀りが得意な理由です。そして日中気温が10度を切る頃になると現地ではすでに夜間氷点下の気温になります。ホルスは冬眠のための穴掘りをしますが、この穴は、普段の夜寝る穴とは少し異なります。2メートル程の長さの穴で、内部には直径30センチ程の部屋がたいてい存在し、他の部分は土でふたをされます。ある科学者によると、ホルスはその生息地に適応するために、零下でも凍結しない体液の機能を有しているということですが、その穴の中は、外が零下でも2度程度の温度が保てるようになっています。あくまで記録ですが零下4.8度でも生き延びたという例はありますが、冬眠中でも2度以下では、危険で、さすがのホルスでも死んでしまうケースもあります。
そして、春先まで冬眠するという行動をとるのです。地表面の土の温度が0度でも数インチ地中にもぐると、彼らの生息地のドライな環境では温度が15度程度になり、自然のホルスはこの温度のグラデーションをうまく利用して、冬眠中の自分の体温を4度から5度になるように保っています。
飼育下での冬眠については冬眠のページを参照して下さい。
食事についてはリクガメの食事のページで詳しく説明しますので、参考にして下さい。ただホルスは、他のリクガメに比べて、その生息環境のきびしさに適応して、あまり緑の葉を多くは食べません。
自然の状態では、かなり乾燥した草や葉などもよく食べているようです。もっとも飼育下では、個体差はありますが、たいていの野菜は食べてくれます。
ホルスの病気について少しここでふれておきます。一般的なリクガメに共通する病気については、
リクガメの病気のページで詳しくご説明いたしますが、輸入したてのホルスの一番の健康の問題は、内部の寄生虫です。主に、線虫、原虫ですが、輸入されたホルスには、まずウジャウジャとそれらの寄生虫がいると考えてまちがいありません。人間にはまず感染しませんが、他のリクガメには糞から感染します。かなり個体が弱っていたり、他の病気のために体調をくずしていたりするのでないかぎり、寄生虫が原因で死んでしまうといったことにはなりませんが、何かの拍子に過度に増えることもあります。
糞を見ると、たいてい線虫が数匹確認できるといった状態ならばさほど気になりませんが、他の個体とは別けておくべきでしょう。体調が戻れば、肉眼で確認できる寄生虫はほとんど糞にまじることはなくなりますが、必ず体内に寄生していますから、他のリクガメがいる場合には、駆虫したほうが安心です。また、体調をくずして、寄生虫が過度に増えてしまい、糞のほとんどが小さい線虫で埋まってしまっているといった状態の場合は必ず駆虫して下さい。駆虫についてもリクガメの病気のページでふれますので参考にして下さい。腸壁に穴をあけられてしまったりするとかなりやっかいなことになってしまいます。
またホルスにおいては甲ら板の損傷が、非常に一般的であり , 実はほとんど至る所に存在します。
それ自体で病気という訳ではありません。それは一つには鱗甲と腹甲をホルスフィールドリクガメはまれな方法で発達させるという結果として生じます。しかし最初は特に輸送中のラフな取り扱いと栄養不足を意味しています。清潔に保っておくならば、その傷んだ領域は、単にだけはげ落ちるだけです。そして新しい甲らが、はげ落ちた下に形成されます。適切に管理された食事は、このプロセスの助けになります。
ホルスフィールドの分類
ホルスフィールドリクガメ(Testudo horsfieldi Gray,1844)は、旧ソビエトなどに棲息している種で、そのためロシアリクガメという別名もついています。ほかのリクガメと比べて、甲羅の形に非常に特徴があります。扁平で、真上から見たときに正円に近い形をしています。甲羅の色は、明るい黄色で、各甲板に不規則な黒い斑点模様があります。また、前脚のツメの数が4本であることから、ヨツユビリクガメとも呼ばれています。
ホルスは、現在、地中海リクガメ属(Testudo)に分類されていますが、この属の分類で議論があります。確かに、頭蓋骨の特徴からは地中海リクガメ属に近いと考えられるそうですが、甲羅の骨格などから判断するとヨツユビリクガメ属(Agrionemys)という独立した属に分けたほうがよい、と主張する専門家もいます。外見の特徴では、尾の先端に突起がある点などで、ヘルマンに近いとも言えます。しかし、その突起はヘルマンのものと比べると小さく、目立ちません。また、尾の両脇の太股のところには、複数のイボのような小突起があり、この辺りは、ギリシャの特徴に近いとも言えます。
ホルスの亜種に関しては、まだ議論がはっきりしていませんが、今現在は次の3つの亜種が提案されています。
●カザフスタンホルスフィールド(T.h.kazachtanica):カザフスタン、トゥルクメン
●ホルスフィールド(T.h.horsfieldi):パキスタン、アフガニスタン、イラン、中国西部
●ルストモヴィホルスフィールド(T.h.rustmovi):トゥルクメン南西部、コペトダク山脈
(最後の亜種は、現在提唱されていますが、まだ正式には認められていません)
それぞれの特徴などは、詳しい調査がされていないようで、まだよく分かっていません。