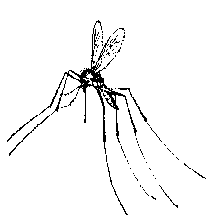
この短編は、八月二八日の高舘での法要の後、藤里貫主の首にすがって血をすすっていた蚊により、インスピレーションを得て書いた作品です。ご拝読いただいて、何かしら感じ取っていただければ幸いです。そしてこの拙き作品を、毛越寺貫主藤里慈亮大僧正に捧げます。大僧正は、我々の意図をお酌み取りいただき、高舘においては、法要まで取り仕切っていただきました。本当にありがとうございました。佐藤
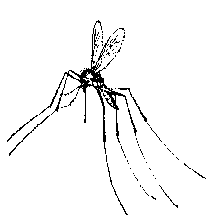 |
第一話
俺は何故ここにいるのだろう。生まれてまもなく、自分がやぶ蚊だと気付いた。もう過去のことは覚えていない。生まれる寸前までは記憶していたような気もするが、最近はすっかり、蚊の性分が身についてきていて、昔のことなど思い出すようなこともなくなった。
今はただ、生き物をみると、血が吸いたくなる。もちろん一番うまいのは人の血だ。柔らかな人の肌に針を刺す瞬間は緊張する。何しろ気付かれでもしたら、たちまちペシャンコに潰されかねないからだ。多くの兄弟たちは、人の手の犠牲となって死んだ。しかしドキドキしながら、甘い蜜のような血をすする瞬間は、たまらない。そこでいちいち自分の命を惜しんでいるようでは一人前のやぶ蚊ではない。
ある夏の日のこと、今日も甘い人の血を吸いたくて、さまよっていると、ぞくぞくするような甘い香りが、平泉の高舘の方からしてくるではないか。夢中で飛んでいくと、何やら大勢の人間どもが、義経堂に向かって階段を登っていくようだ。俺と仲間は、このごちそうを逃すまいと、この一団にめがけて殺到した。
白装束を着た人間が、二人ほら貝を吹きながら、義経像の前で、立ち止まり黙礼した。そのうちの一人が、背負っていた朱色の笈を下に置くと、若い僧侶二人が、その笈を義経像の前の祭壇に据えた。
僧侶は三人いる。その中の長老の風貌の僧侶が、中央に腰を掛け、意味の分からない言葉で法要を始めた。こんな機会はそうめったにあるものではない。俺はどきどきしながら吸い付く獲物を探した。
すぐに長老格の男の血をいただくことに決めた。理由は特にない。大体若い蚊というものは、やはり若い人間の血を吸いたくなるものだ。俺はそうではない。むしろ年をとっている人物の血の方が好きだ。熟成した甘さがたまらないのだ。直ぐさま長老の正面に回った。気付かれてしまうので、後ろから首筋を狙うことにしたのだ。
ピシャという音が、聞こえ、若い僧侶に群がっていた仲間がやられた。しかし甘い血を吸うためには、それぐらいは覚悟の上だ。その頃、俺は細心の注意を払い、ふわりと長老の首に舞い降りた。一瞬、長老の後ろにいたあごのしゃくれた男と目線が、あったような気がしたが、もう甘い血の誘惑の前では、開き直るしかなかった。
足を思いっきり踏ん張ると、少しずつ針を、長老の肌深くに食い込ませた。あごのしゃくれた男が、ジロジロ見ているが、ここまでくるとペシャンコになろうがなるまいが、血をいただくしかない。一気に血をすすりにかかった。うまい。こんなうまい血を味わったのは、生まれて初めての経験だ。あごのしゃくれた男が、やたらにジロジロ見てくる。馬鹿な男め。俺は大声で言ってやった。
「他人の首より、自分の首こそ、気にしあがれ!」既に、その男の首には、仲間に刺された二カ所の吸われた跡が赤く浮かんでいた。馬鹿な男もいたものだ。俺は完全にこの男を無視し、長老の首から甘い甘い熟成した血をいただき続けた。
それにしてもこの長老も大した御仁だ。普通なら、少し経つと、人間というものは、かゆみによって、気付くものだが、いっこうに気づいた様子もない。ここで俺の血の吸う技を披露しておこう。俺の血の吸い方は、やぶ蚊の中でも最高水準にある。俺はこれまで俺よりうまく血をいただくやぶ蚊に会ったことがない。そのやり方は、微妙で絶妙で、誰もマネなどできっこない。まずは最高の獲物を選ぶ。馬鹿な人間に興味はない。そんな血を呑んだら、こっちが病気になってしまう。獲物を見つけたらいよいよ誰も真似のできない技を繰り出す。
俺の得技は、連続吸引の合わせ技だ。まず少しすすっては、ふわりと飛び立つ、そしてもう一度場所に舞い降りて血をすする。場合によっては、4,5回そんなことを繰り返す。仲間は、この時の俺のことを舞っているようだ言う。この微妙な感覚は決して説明出来るものではない。
だが今日の場合は、長老の血をいただきながら、そんなことはどうでもよくなった。だから今日は一度も飛び立つこともなく、同じ所から血をすすり続けた。誰が見ようと、睨もうとそんなことは、もはやどうでもいい。それほどこの長老の血の味は甘美だ…。
時々「源義経公810年祭…」とか何とか言っている人間の声が聞こえたが意味が分からない。ただその中の「ヨ・シ・ツ・ネ」という響きが妙に気になる。前にも聞いたような気がした。しかしながら今の俺には、その記憶を引き出す能力はない。
次々と仲間がこの四、五十人の集団に襲いかかり、数匹の犠牲者を出しながらも、最高のごちそうにありつけた。俺は10分近く、少しずつ最高の血を腹一杯に吸い込んだ。そばの若い僧侶二人に食いついた仲間は、五匹ほどごつい手で打ちのめされて折から振っている激しい雨に流されて行った。
今日の俺は運がいい。長老は10分近く経過した今も、ただ一身でお経を読み続けていて、いっこうに、俺を振り払う素振りすら見せない。俺の腹の中は、長老の血でいっぱいとなった。これ以上ごちそうになると飛び立てない可能性すらある。
そして徐々に吸い込んだ血が消化し始めてきて、不思議なことが、俺の中で、起き始めた。最初は食べ過ぎのためかとも思ったが、そうではなかった。実に妙な感覚だった。とうに忘れていたはずの人間の言葉が、理解できるような気がするのだ…。
しばらくして、とぎれとぎれの記憶が繋ぎ合い、人の言葉が理解できるようになってきた。やがてこの長老の名を知った。長老の名は、藤里貫主。毛越寺の一番偉い人物だ。。今日この平泉高館で行われている儀式は、「源義経公810年の供養祭」。「ヨ・シ・ツ・ネ」という響きがやたら気にかかる。その名が聞こえて来る度に、どきどきする。胸の奥で「思い出すな、思い出すな」と、叫んでいるもう一人の俺がいる。…待てよ。俺は義経を知っていた。確かに、遠い、昔、聞いたことがある。でもどうしても思い出せない…。
第二話
藤里貫主の血をたっぷりすすった俺は、どうしようもない感覚になり、ふらふらと飛び上がった。胸が苦しかった。重い身体を必死で支えていると、丁度義経堂の正面に安置されている義経像の前まで来ていた。俺はぞっとした。義経が明らかに俺を睨んでいるではないか。そして古い記憶が心の奥底から、どっとばかりに蘇ってきた。た。そうだこの像は義経だ。俺が破滅に追い込んだ義経だ。義経は、俺のことを馬鹿にした男。憎き敵。俺の全人格ををせせら笑い、否定し、頼朝公の弟君ということを鼻に掛け、やりたい放題のし放題。俺が一言口を挟むものなら「古い戦法では通じない。ここはまあ私に任せておきなさい」と言って部下の前で大恥をかかされた。
そこで俺は奴を破滅させることに命をかけた。俺だって鎌倉権五郎景正の流れを汲む家柄、頼朝公には敵わないとしても、雑使風情の腹から生まれた義経に負けるはずはない。あの小僧に、そこまで馬鹿にされては、家門の恥。だから俺は頼朝公に一通の手紙を書いたのだ。
「このまま義経公を好きなようにやらせるのは、非常に危険です。義経公は、頼朝公の弟君という権威を傘に着て、やりたい放題のし放題。我々鎌倉武士のことは、完全に無視を決め、奥州から連れてきた佐藤兄弟や怪しげな坊主の武蔵坊弁慶とか申す者とばかり打ち合わせをしている状態。またこの度は、総大将である頼朝様を無視なさって、勝手に公家の連中と仲良くなり、最高の官位までもらって得意になっている始末。従いまして、平家追討で鎌倉を発った者の中に、非常な不満が蔓延しております。どうか頼朝様、この状況をよくご理解の上、賢明な判断をなさってください」
すると賢明なる主君頼朝公は、あの憎き義経を、場合によっては、自分の地位までも狙いかねない危険人物とみなされた。俺としてもまんまと作戦成功となったのだった。それにしてもあの義経という男は、奇想天外な男だった。「自分には神のご加護があるから、不可能も可能になる。嵐も地震も恐れることはない。一身に神仏に祈り、奥州の兵法にすがっていれば、必ず勝つ」と言って聞かないようなところがある。とにかく手が付けられない男だった。俺からすれば、奴は波に乗っただけの並みの男ではないか。たまたま木曾義仲を奇襲で破って、自分には神が憑いていると錯覚してしまったのだろう。
悪いが俺は子供の頃から四書五経を、たたき込まれ、六歳にして、論語を諳んじた男だ。誰にも負けるわけがない。特にあのような感性だけで生きているような男は鼻持ちがならないのだ。冗談ではない。何かあると俺の案は全部、教科書通りの愚案だと避難する。自分の主張が通らなくなると、勝手に行動して、勝利を収めてしまう。世間では、全てが義経の手柄となって、この俺たちは、益々もって笑い者とされた。冗談ではない。一ノ谷や屋島の奇襲と言ったところで、兵法の王道から言って邪道も邪道、大邪道。たかが偶然の勝利ではないか。
そこへ行くと、さすがに頼朝公は賢明だった。すぐさまあの小僧を追放し、責め立て、高舘の館で自殺に追いやった。俺は胸がすっとした。大体この俺を馬鹿にするなんぞ、10年早いのだ。思い知ったか、義経め。
その義経の首が鎌倉の先まで来たが、俺はそこでも頼朝様に手紙を書いて、兄弟の仲を永遠に封印してやった。
「この度、怨敵義経公の首が、実検の為、相州藤沢に到着致しましたが、決して鎌倉に入れてはいけません。噂によれば、義経公は、生前から、『もしこの義経が死ぬことがあったら、必ずや、怨霊となって、鎌倉殿以下名だたるものを祟り申す』と言っていたそうです。ここは一つ私儀が、こちらから藤沢の里に出向き、怨霊となった義経公の怒りを封印しましょう。私一人が犠牲になれば済むこと、頼朝様どうか、首実検の大役を、私にお任せください」
奴の首は、見るも無惨な姿だった。しかし俺にしてみれば、何と胸のすく瞬間だったろう。俺の才能を馬鹿にした小僧の首が、焼けただれた哀れな姿でそこにある。ここだけの話しだが、一発屁をその首めがけてぶっ放してやった。そして「やい、やい、やい、俺様を馬鹿にした罰だ。後悔先にたたずと言って見ろ、この生意気な小僧めが」と叫んでいた。
絶頂だった。奥州の秀衡が死に、義経を殺し、いよいよ俺の出番が回ってきたのだ。所詮義経は戦の天才。俺はそこへ行くと政治の天才。いったん戦が収まれば、俺の時代が来ると分かっていた。もはや俺の上昇運をだれも止められないとさえ思った。そんな俺が、今なぜこんな姿に身をやつしているかって、そのことはもはや思い出したくない。まさか俺だってあんなことが我が身に起こって、やぶ蚊となって生まれてくるなんぞ、誰が想像できただろう。
第三話
俺の運命が狂ったのは、頼みの頼朝公が突然亡くなられたことからだ。誰よりも俺はあの殿を尊敬していた。あのお方こそ、新しい国を造るためにと、神様から使わされたと信じてきた。それなのにまさか義経が死んで僅か十年後に五三歳の働き盛りで逝かれてしまうとは…。
俺は今でも自負している。鎌倉文化を創ったのは、源頼朝公とそしてこの梶原平三景時なのだ。そうではないか。やっとの思いで宿敵義経を倒し、奥州を征伐し、日本全国に守護と地頭制度を敷き、夢にみるような完璧な国家が出来上がろうとしていたのだ。さしずめ我ら梶原一族は、京の都で権勢を振るう藤原鎌足以来の名門の家となることももはや夢ではなくなった。その矢先に、あの怖ろしい出来事は起こったのだった。
頼朝公と俺は、百名ほどの一行を連れて、箱根へ向け鷹狩りに出かける最中のことだった。頼朝公の館出て由比ヶ浜の入り江に差し掛かると、空が俄にかき曇り、真っ黒な雲が天空を覆い尽くしてしまった。馬は恐怖のためか、何度もいななきを放って首を上下に振った。これはただ事ではない。すぐに俺は頼朝公に進言した。
「殿これはすごい雨になりますぞ。幸いすぐに戻れる距離ですので、引き返しましょうか」
「何を言うか。鷹狩りとは、すなわち戦なり。戦の訓練をするというのに、直ちに引き返す魂胆では、武士としての腹が据わっていない証拠じゃ。よいか景時、このまま進むのじゃ。一時のにわか雨が怖くて、国家を導けるか」と、まるで屋島の合戦時の義経のように言われた。ヨ・シ・ツ・ネと思った瞬間に、俺の動揺は頂点に達し。雲は低くたれ込めて不気味な様相を呈し始めた。
そしてついに雷光が周囲を光の海に変えた。「あっと」という声がそこかしこから聞こえ、やがてその声は、強烈な雷鳴によってかき消された。明らかに怨霊の仕業だった。このままいたら、天神の餌食になってしまうに違いない。
「殿、これはまずい。やられてしまいますよ。逃げましょう。あの茂みの中へ」
頼朝公もただならぬ状況に俺と同じ事を感じたのか。静かな声で、
「義経の怨霊だな…」と呟かれた。
動揺する馬の手綱を引きながら、我々は、雨に濡れた茂みの中に分け入って行った。その瞬間も稲妻が空を右に左に走り、雷鳴は一向に鳴りやむ気配がない。そしてとうとう頼朝公が休めまれていた松の木に落雷して、その木は真っ二つに割れて、馬を引いていた部下が一人折れた大木の犠牲となって死んでしまった。
「殿、殿、大丈夫でございますか」
「無事じゃ。無事じゃ」
「それはよろしゅうございました。残念ながら、馬まわり役の源太は死にました」
「そうか、かわいそうにのう…それにしてもこの異様な天候はどうしたというのだ」
「今この景時が、近くの寺に人をやって、僧侶を呼んで参りますので、しばしお待ちください。法力によって、この雷雲を退散させますので…」
「そうか、さすがは梶原景時、いざという時に頼りになるのはお前だけじゃ」
「殿ありがとうございます。命を掛けてお仕えもうしますぞ」
その時、強烈な光が辺りを照らして、一瞬なにが起きたのか分からなくなった。
おそらく近くに雷が落ちたのだろう。そのまま俺は意識がなくなった。夢うつつの中で、暗い闇の中を、白装束で歩いてくる者がいる。声は出なかったが、俺はそれが義経であることを分かっていた。音もなく近づいてきた義経は、俺の方を向いて静に言った。
「とるに足りぬ男よの…。景時…。お前の命は取らぬ。意味がないからじゃ。しかし兄君は許さぬ。とるに足りぬ男を利用した罰だ。許さぬ」
俺は何とか「お許しを、お許しを」と叫んでいたが、声にはならなかった。
「景時、景時、お前は人の生き血を平気ですするような男、お前が今度生まれて来るときは、やぶ蚊となって、永遠に死ねない身の上となる。よいかお前は永遠にやぶ蚊となって生まれ変わる…」その時には何の意味か分からなかったが、白装束の義経は、確かにそのように言って闇の中に消えた。
「梶原殿、梶原殿」その声で起きてみれば、俺は、長谷寺の離れに眠っていた。長谷寺の別当妙善という和尚が心配そうにこっちをのぞき込んでいる。傍らには、部下どもも心配そうにこっちを覗き込んでいる。ふと気が付いた。頼朝公のことが急に思い出されて、
「殿は、頼朝の殿は?」と思わず大声で叫んで、上体を起こした。
「…残念ながら頼朝公は重体でござる」静に妙善は、そう言って涙をぽろりとこぼした。「そんな馬鹿な、何故あのようなことで、天下の征夷大将軍頼朝公が亡くならねばならぬ。第一頼朝公を支えてきた俺の立場はどうなる。それでなくても俺の才能をねたみ、追い出そうとのたくらみがあるのだ。殿何とか、生きてくだされ、生きてくだされ、俺のためにも…」俺は思わず本音を言ってしまった。まあ妙善は味方だから、言いふらすことはないだろう。
「梶原殿、そのようなことを言ってはなりませぬ。不謹慎ですぞ。聞かなかったことに致します。おおそれより首から顔中、やぶ蚊に刺されて真っ赤になっておりますが、かゆくはありませぬか?」
「やぶ蚊に刺されている?」俺はぞっとした。義経は夢の中で、俺がやぶ蚊になって永遠に死ねない、とか何とか言っていたことを思い出した。
「鏡を見なされ」と、渡された鏡の中を覗くと、本当にやぶ蚊に刺された跡が、首から顔にかけて、ごま塩のように点在しているではないか。それを見た瞬間、かゆみが襲ってきて、どうしようもなくなった。部下の話によれば、近くに落雷して全員が気絶してしまったようだ。助けに来た者が到着した時には、無数の蚊の大群が、倒れた我々の身体にたかっていて、しこたま血を吸っていたらしい。特にひどかったのは、頼朝公で、落雷で電流が身体を貫いた上に、無数の蚊により血をすすられて瀕死の重傷で苦しんでいるとの事、しかしこのことを世の中に知らせる訳にもいかず、病気ということにして伏せておくこととなった。
頼朝公は、数ヶ月落雷の傷とやぶ蚊の跡が化膿し、苦るしみ抜いた挙げ句に亡くなられた。俺の運命もあっさりと変わった。頼みの殿が死んだのではどうしようもない。すぐに俺は鎌倉を追放となり、不様に死んだ。蚊と生まれ変わるために死んだのだ。
第四話
俺は鎌倉の中でもとびきりの嫌われ者だった。俺には俺の考えというものがあった。ズバリ言えば、頼朝公の負の部分を俺が全て引き受けていたのだ。元々地獄へ行くことは覚悟の上だ。ただやぶ蚊になってしまうことはまったく予想外だったが…。
俺が死ぬとすぐに義経の怨霊が、霧の中から憤怒(ふんぬ)の形相で現れた。ぞっとした。その怒りがあまりに強いものだから、義経は体中から蒸気のようなものを発していた。しかもその身体は東大寺の大仏よりも巨大だった。俺はとって喰われるかと思って、
「義経さま…どうかご勘弁を、私はただ頼朝公の仰せにしたがっただけでして、貴方様には何の恨みもないわけで…ですから、そのこのところをご考慮いただき、お手柔らかに、ご勘弁を、貴方様の下部になりますから、どうか、お許しを…」と、嘘泣きをしながら言った。
地獄へ来ても、俺には状況を計算するだけの頭があった。義経は所詮「涙武士」、攻めてくる奴にはめっぽう強いが、女や子供、弱い民にはからきし哀れを掛けすぎる気性がある。俺はそこの所を突いた。すると案の定憤怒形相が緩んで、蒸気も弱くなった。そして俺は畳み掛けて、得意の弁舌をふるった。
「義経さま、所詮、私は頼朝公に飼われていた篭(かご)の鳥でして、貴方様もそれは重々ご存じのはず。忠義に忠実なあまり、貴方さまには、ついついご無礼の数々があったこと、お詫びいたします。でもそれは戦の世では仕方のない運命のようなもの。そうではございませんか。義経さま、私も今このように哀れな最後を遂げたからには、もうこれ以上恥をさらしたくはありません。お詫びします。何でも致します。そして貴方さまの慈悲の心にただただおすがりするしかございません」
俺は義経の怨霊の前に平身低頭し、その巨大な足先に触れようとした。しかしそれがいけなかった。少しやりすぎだった。俺にはまだ、義経憎しのオーラが出ていたらしく、指先からウソがばれた。直ぐさま心を見透かされ。義経がこのように唸った。
「カジワラ、カジワラ、相変わらずのウソ八百。よくぞそこまでウソが次から次と数珠繋ぎで出てくるものだな。ほとほと感心させられるわ。虫けらにも劣る奴よ。もはやお前の罰は、決まっておる。お前の性分にもっとも相応しい罰がな」
「決まっているのですか、あのそれはどんな罰で…」その言葉を言い終わらないうちに義経の怨霊は消えた。ちょっと待ってくれ。と言いたかったが、とにかく目前の恐怖が消えて俺はほっとした。とにかくその場所を離れたかったので霧の中を俺はさまよい続けた。しばらくしてほの暗い中に微かな光があるのが見えた。ほっとした、正直言って助かったと思った。その光の方にどんどん近づいて行くと、香ばしい匂いが腹の空いた俺の胃袋を刺激した。きっとおいしい食べ物もあるに違いない。腹が空いては戦ができぬ。義経の居ぬ間にとにかく腹ごしらえと行きたかった。そこですっと光の中に飛び込むと、強烈な風が俺をどこかに運んで行くようだ。その中で声が聞こえてきた。静かな優しい声だった。あの恐ろしい義経の声ではない。きっと仏様だったのだろう。
「これ哀れなる者よ、お前は百万べん、やぶ蚊として生まれ変わらねばならぬ。ただしその中で慈悲の心が起こったならば、もう一度人に生まれ変わるチャンスを与えよう。しかしこの罰は苦しいぞ、苦しいのは当然だ。お前の本来の心が、やぶ蚊だからだ。心の根本がその芯から変わらねば、百万べんが、更に二百万べんになるかもしれぬ」
そして気が付いた時には、俺はボウフラとしてどぶの小さな水たまりにいた。別にどぶの匂いも気にならなかった。いやむしろ自分のふる里に帰ったような心地よさがあった。やがて少しして、やぶ蚊の成虫になり、人の生き血を吸いながら、ああなんて人の生き血は甘いのだろうと、感じた。このままだったら、別に蚊のままでいいや、住めば都という言葉の通り、やぶ蚊稼業も悪くはない。と思った瞬間、ざまあ見ろ、義経と舌ならぬ、人の生き血を吸う触覚をぬっと出していた。
それから俺は何度、人の生き血を吸い、吸いそこねて、叩き殺されたことだろう。別に蚊の生涯も悪くない。ただしイヤなのは、死んだ後で、仏様が出てきて、必ず反省文を書かされることだ。どうも俺は仏が苦手だ。まだまだ百万べんは遠いし、別に人間でなくてもいい。慈悲なんてまっぴらだ。そう思っていると、今回はたまたま義経ゆかりの奥州平泉の小さな水たまりで9999回目の生を得たのだった。
第5話
俺はずっと人から嫌われ続けてきた。それでいい。何も問題はない。嫌われ者で結構。嫌われ者には嫌われ者の生き方がある。一種の開き直りかもしれぬ。でもいい。やぶ蚊にはやぶ蚊の楽しみがある。ずっとそう思ってきた。今の今までそれが俺の思想のすべてだった。それが藤里貫主の首筋に舞い降りて、血をいただきながら、そのお心に触れた瞬間、初めて嫌われ者の俺自身に疑問が湧いてきたのだ。不思議だ。第一、お経などまっぴらだったこの俺が、それを心地よくさえ感じている。何故このような気持ちになったか…。貫主のお経を聞きながら、たまらないほど悲しい気持ちに襲われた。涙が溢れてきて止まらない。ああ、俺はいったい、こんなところで、何をしているんだろう。それに引き替え、自分の血が吸われていることを知りながらも、黙ってされるがままにしている藤里貫主という人が、俺の目の前にいる。でも悲しいかな、自分の気持ちとは裏腹に、その人の生き血を吸うという行為を絶つことができないやぶ蚊の俺もまたそこにいた。
藤里貫主のお経が、実は俺が陰謀によって葬った源義経…公…のお心を鎮めるための法要であることを知った。その義経…公が木像の中からじっとこっちを見ておられる。「お前も黙って、このお経を聞け」という声が、どこからか聞こえてきた気がした。確かに昔聞いた義経公のお声だ。「はい」と、返事をしたかったが、とてもそんな余裕はない。涙がどっと溢れてきた。恥ずかしい。
死んでしまいたい。このまま死んで、闇の中に、消え入りたい。俺は心底、今、ここで殺されたいと思った。貫主に、思いっきり叩いてもらい、死にたかった。心の中で、何度も”早く殺してください。今すぐ打ってください”と念じた。しかし貫主は動かない。動く気配がない。まるで石仏のようだ…。この読経は未来・永劫・永遠に続くのか…。そして俺は永遠に死ねないのかもしれない。
俺は泣きながら、ふらふらと飛び上がり、気が付くと、義経の像の前で力つき、義経堂の縁側の下に落ちた。そばでは義経公を鎮魂する人々が行き交い。俺はその足で踏みつぶされることだけを望んだ。しかし俺を踏んでくれる人物はいない。俺は本当にこのまま永遠に死ねないのかもしれない。ぞっとした。
そんな俺を余所にたっぷりと生き血を吸い、満腹となった仲間は、次々と自分のねぐらに帰っていく。心配した兄弟が数匹、俺のそばに近寄ったが、俺は手を振って別れを告げた。俺は死にたい。どうしても今日ここで死にたいのだ。そして仏に慈悲について聞いてみたい。慈悲とはいったい何なのだ。
いや、でも、何も、俺は、人間に戻りたい、などと、大それたことを思っているわけではない。ただ自分と違う価値観を持った藤里貫主のような人と語り合いたい。知りたい。そう思っただけだ。(完)
99/09/04 HSato