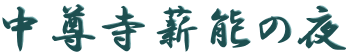  (佐藤弘弥 09年8月14日撮影) |
| 1 中尊寺で、恒例となっている中尊寺薪能を鑑賞した。 8月14日は、お天気にも恵まれ、訪れたおよそ八〇〇名の観客は、白山神社の能舞台の回りに陣取り、かがり火が焚かれる中、次第に迫る夕闇の醸し出す幽玄の美を満喫しているようだった。 午後4時、白山神社関宮千代丸宮司の祭儀の後、薪能奉行工藤雅樹氏(考古学者 平泉世界遺産登録推薦書作成委員会委員長)による火入れの儀が賑々(にぎにぎ)しく行われて、能は静かに始まった。 中尊寺の薪能は、代々伊達家の能の指南だった喜多流宗家が、白山神社に奉納するものである。私は杉木立に囲まれた白山神社の境内の中で、時の過ぎるのも忘れて一服の涼を味わった。時折、蜩(ひぐらし)が謡いに競演するように近くの木に留まって鳴くと、その風情はひとしおのものがあった。 今年の演題は以下の通りだった。
この能は、特に修羅物(武人の霊を主人公として戦を主題とした謡曲のこと)の中でも、「勝修羅」(かちしゅら)と呼ばれる目出度い能とされる。 確かに、能にしては、激しい勢いでびっくりするほどだ。実に若々しいエネルギーに満ちた勇壮な曲である。景季は義経にとっては、頼朝に讒言(ざんげん)をして、兄弟の仲を裂いた梶原景時の息子である。義経を愛する者にとっては、梶原景季と聞くだけで、違和感が湧くのであるが、シテを演じた佐々木多聞氏の舞いが素晴らしく、そんなことも忘れてしまった。 又能というものが、戦争の時代が長く続いた戦国時代から、やがて平和の時代となる江戸時代において、戦争の時代を経験した武者たちが、この「箙」などを鑑賞し、やがていつの間にか、亡霊である梶原景季の魂と一帯になって、自らの戦争体験を思い出し、涙を拭っていた姿を想像した。 |
 白山神社 薪能の夜 |
| 2 中尊寺の白山神社は、関山の最北端の位置にある。この社の裏には、西物見があり、直下には衣川が流れている。そこから眼を上げて行くと、前九年の役で滅んだ安倍一族の館跡が並んでいる。 そこから西に眼を転じれば、官軍(源頼義・義家親子)と賊軍(安倍貞任ら安倍一族)が激しくせめぎ合った衣の関の古戦場がある。さらにそこから真北に視線を戻し、地平線の方向を見渡せば、もちろん目には見えぬが、安倍一族の終焉の地、厨川柵(くりやがわのさく)が脳裏に浮かんでくる。 現在の盛岡市安倍館町周辺に、この柵はあったとされる。ここは安倍貞任や藤原経清周辺の地だ。その時、貞任は負傷をして戸板に乗せて、頼義と義家の前に運ばれてきて、すぐに絶命したという。また経清は、国府の役人だった者が自分を裏切ったとして頼義の激しい怒りを買った。頼義は、そこで刃こぼれをさせた刀で、経清の首をじわじわとノコ引きにされた。これによって、前九年の役は終わり(1062)を遂げたのである。この時、清衡は7歳だったが、母に手を引かれ、その場ですべての出来事を見ていたはずである。凄まじい戦争体験である。 私は白山神社が北を向いている理由は、初代清衡が、安倍一族と自らの父藤原経清の御霊を弔うためにあるのではないかと推量している。 白山神社のあるこの周辺は、清衡が平泉を開府するに当たって、最初に開発された地域だった。空海が高野山を開いた時に、最初に地主神である高野明神の社殿を建てたように、平泉の鎮守である「白山神社」を建てた可能性がある。 白山神社の周辺には、多宝塔が立ち、二階大堂と呼ばれた大長寿院が立ち、この中を奥大道と呼ばれる官道が北に向かって延びていた。 3 白山神社の社伝によれば、この場に、天平19年(1591)関白の座に就く目前の豊臣秀次と伊達政宗がやってきて、能を鑑賞したということである。おそらく、この時は奥州仕置と呼ばれる豊臣秀吉による天下統一の過程で、旧勢力であった鎌倉時代からの地頭であった葛西氏や九戸氏などの改易などがあって、たまたま中尊寺を訪れたものと思われる。この時、私は中尊寺の歴史にとって、大変重要な歴史的事件があった可能性があると思っている。 それは中尊寺経(清衡が書写させた5300巻の金銀泥一切経のこと)の持ち出しである。江戸幕府編纂の編年体の史書「続本朝通鑑」(1670)によれば、同年10月、「豊臣秀次。平泉の大蔵経・・・を京都に送る」(「大日本総合年表」による。 岩波書店 1990)とある。(中尊寺経の持ち出し(搬出)時期については、慶長三年春(1598)とする佐々木邦世氏の説もある。) 中尊寺経は、別名「金銀泥一切経」とも呼ばれる中尊寺に伝えられてきた最大の宝物である。この経典は、初代藤原清衡が、大長寿院別当の蓮光に書写させたもので、5300巻ほどあったとされる。 書写の銀字金字と銀字で交互に法華経や華厳経などの経典を書写したもので、仏教史の中でも特筆されるべき宝物である。そのほとんどが国宝に指定されているものだ。 現在4500巻ほどが、現存しているが、そのほとんどは、何故か高野山にある。高野山の本堂に当たる金剛峯寺には、豊臣秀次切腹の間があるが、高野山は、豊臣秀吉の信任を得ていた僧侶の木食上人を通じて、中尊寺から運び出された中尊寺経が、さまざまな経緯を通じて、中尊寺経蔵から高野山に渡ったものと考えられる。現在中尊寺には、僅かに十七巻余りが残るだけである。それに対し高野山には、4296巻が現存している。 もちろん本当の犯人は、秀吉だろうが、その実行犯は秀次だったのか。そこに正宗の関与はなかったのか・・・。そんな歴史の謎を思いながら、その後、焼失した能舞台が、正宗の子孫(伊達家)によって再建された不思議を思った。能舞台では、「箙」が終わり、休憩時間となった。 |
 白山神社能舞台 |
 かんざん亭から夕日を見る |
| 4 今年の東北は、異常気象というべきか、未だに梅雨明け宣言が気象庁から出されていない。米の生育にとって、この八月は稲の花が咲き稲穂の入る一番大切な時に当たる。この時、日照時間が少ないと大変なことになる。今日のような晴天が明日も明後日も続くことを願いながら、杉木立の隙間から空を見上げれば、もうすっかり秋らしいいわし雲がゆっくりと天空を泳いでいた。 喉の渇きを潤そうと、背後の白い幕をたくし上げて、軽食の置いてある「かんざん亭」に向かう。時刻は五時四〇分を過ぎている。日は西に傾き、かんざん亭の大きな窓越しに、夕陽が射し込んできていた。夕陽の中で、若い女性が二人が浴衣姿で、お稲荷さんを頬張っていた。二人の輪郭が夕陽に映えて輝いていた。 西の窓際に行くと、衣川の象徴である聖なる山三峯山は、夏の夕陽を浴び、まるで緑の衣を羽織ったピラミッドのように見えた。ただ昨年6月の岩手・宮城内陸地震で陥没した箇所があり、夕もやの中であったが治山工事の傷痕も生々しく映った。その右奥には、雲に覆われた焼石岳が微かに見えた。黄金色に輝く雲は、刻々とその彩りを変えていった。中尊寺の薪能の幕間に、自然の織りなす見事な別の舞台を見物することなど、予想もしなかっただけに感激した。 ところで、このかんざん亭は、盛岡出身の建築史家の故藤島亥治郎氏(東大名誉教授・平泉町名誉町民)によって設計されたものだ。藤島氏は、この他に戦後になって建てられた平泉の建物をほとんど設計している。中尊寺では、金色堂の新覆堂、宝物館である讃衡蔵(さんこうぞう)、そしてこのかんざん亭。毛越寺では、本堂と宝物館、また浄土式庭園である大泉が池の復元にも関わっている。平泉文化遺産センター(旧名:平泉郷土館)などもある。 このかんざん亭で、写真を撮り、お茶とお稲荷さんで腹ごしらえを終えると、二幕目始まりのアナウンスが聞こえた。演目は野村万作、萬斎親子による和泉流狂言「樋の酒(ひのさけ)」であった。何とも楽しい喜劇である。 米蔵と酒蔵の番を命ぜられた太郎冠者(万作)と次郎冠者(萬斎)が、つい出来心で、酒蔵の壺を開けて、酒を飲むと、余りの美味さに、酒盛りにエスカレートしたところで、主人が帰ってくる。 他愛もないストーリーだが、その声の調子や無駄なものをそぎ落とした動きなど、心の底から笑みがこぼれてくる。形(かた)に裏打ちされた伝統芸と野村萬斎という盛りを迎えた狂言師の花を垣間見せてもらった気がした。 最後にところの太郎冠者のセリフに「流石は泉の壺、汲めども尽きぬ酒蔵かな」というものがあった。これは、自らの「和泉流の狂言」と「平泉の文化」というものを「汲めども尽きぬ酒蔵」と暗に表現したのかなと思い、「うむ、なるほど」と深く心に留めたのであった。 5 次第に夜の帳が落ち始める。すると、かがり火が能舞台をボーッと浮かび上がらせる。これがこの世ならぬ非現実の世界にリアリティーを与える。一般には「幽玄」と言われるものだ。 この白山神社の能舞台は、1852年、伊達家によって再建奉納されたものだ。一見茅葺き屋根で、質素な建物に見えるが、世界的な建築家のブルーノ・タウト(1880−1938)は、1934年2月27日(火)に、この能舞台を見た印象について、このように評し、写真まで残している。 「非常に繊細なもので、全体がすばらしく簡素な木の構造だ。舞台のうえで足を踏みならし、板からでる特別な音色を試してみた。全体が田舎風に繊細なこの建物は、中尊寺で[岩手県・平泉]で一番印象に残るものだった。やはり日本独特のものだ。」(「タウトが撮ったニッポン」武蔵野美術大学出版 2007年刊) タウトの写真は、能舞台の正面右斜めの角度から茅葺き屋根を強調するように能舞台を右に配置し、左には半分だけ、白山神社が写っている。茅の輪は見えない。背後には西物見の杉木立が見える。この写真から屋根の形状や茅葺きそのものにタウトが興味を持っていることが伺える。 また、戦後には、イギリスの陶芸家のバナード・リーチ(1887ー1979)も、民芸運動家の柳宗悦(1889ー1961)と一緒に、平泉を訪れ、特にこの建物を上げて、その美しさを讃えている。 二人は、日本文化に造型の深い芸術家であるが、一般の外国人観光客にとっても、この能舞台は、中尊寺境内の中でも、印象に強く残る建物と映るのではなかろうか。現在、白山神社の能舞台は、近世の能舞台遺構として重要文化財に指定されている。 6 舞台では、「杜若(かきつばた)」が始まった。能の本質は、普通の眼では見えないものを主題として、そこに儚く美しい情緒を感じ取ることである。能のストーリーにおいては、序破急と言われる起承転結で構成され、終結となる。 能の主人公の多くは、この世(現世)に思いを残して亡くなった人物が亡霊となって現れる。亡霊たちは生きているものに、自分の思いを述べ、回向(成仏)を頼むびである。亡霊でない場合は、花の精とかになる。先の「箙」では、梅の精が実は、修羅道に落ちた梶原景季であった。彼は自分の武者振りを誇りながら、何とか修羅道に落ちた自分の成仏を、僧に乞い願うという物語だった。見るものは、そこに自分の人生を重ね、修羅の道ではなくとも、さまざまな人生の壁に囲まれた自分を重ねてみている。 能の「杜若」は、伊勢物語の在原業平の恋物語を主題としたものだ。主役(シテ)は、杜若の精であるが、これは在原業平の恋人であったと想定される二条の后(きさき)の高子の亡霊である。この女人は、昔在原業平と恋に落ちて、その思いが断ち切れずにあの世を彷徨っている。 冒頭の能「箙」では、修羅道に落ち、戦の栄光が忘れられず、彷徨っている男子であったが、「杜若」では、恋の深みにはまった女人が主人公である。 能においては、このように亡霊が、自らの生前の思いを断ち切れず、この世に現れて、回向(成仏)することを乞い願い、この世に現れるケースがほとんどだ。すわなち、能の舞台では、この世とあの世の境が取り払われ、能を鑑賞するものは、怪奇な物語を、自然に受け入れているのである。 この能の物語の奥には、日本人の集合的無意識と同時に、ギリシャ悲劇に通じるような人類共通の集合的無意識が眠っていると考えられる。 「箙」の奥には、戦争というものが、この世から消えない根源にある意識が横たわっている。それは戦争(戦い)というものが、男子の心を喚起させる魔力があること。戦争は単に、ひとりのヒトラーのようなリーダーが登場し、それに乗せられて、起こるというのではないこと。また国家間の支配の論理や市場経済のどん欲な性格に引き起こされるだけではないこと。人間個人の中にある暴力性が倫理性のワクを越えて、男子の心を高揚させ狂気に誘うということを、教えてくれる。 時に、「杜若」の能では、男女の関係の中に、戦にも似た愛憎の地獄というものが存在し、この世の規範である法や道徳という一線を越えてしまう危険なものであることを教えてくれる。同時に、その危険極まりない思いの中で、人間はそれでも恋をし、死んで行く定めにある。そして死してなお、その思いは残って、花に仮託し、現世に生きる私たちに、そのことを伝えてくるのである。そこで能の中では、僧と杜若の精の問答があり、救済として、仏教の教えが明かされるのである。 そして能「杜若」では、最後に実は在原業平という人物が、実は恋愛というものを通じて、悟りを開かせる神であったと明かされる。これによって全国を行脚した在原業平の女性遍歴そのものがが全面的に肯定され、最後には、「杜若の花の悟りの、心開けて、・・・草木国土悉皆成仏(そうもくこくどしっかいじょうぶつ)・・・失せにけり」となるのである。 つまり明け方、杜若の精(実は二条の后の亡霊)は、僧の助言によって見事に悟りを開いて、愛憎の地獄から脱して、成仏したことで幕となる。 この「草木国土悉皆成仏」は、天台宗で説く教義である。この能「杜若」の原作者は、その言葉を最後のクライマックスにもってきて、心を持たないとされる草や木や国土でも成仏できる。まして女人が悟れぬはずはない、と恋愛を通じても「女人成仏」はできると説くのである。原作者は、世阿弥の娘婿の金春禅竹(こんぱるぜんちく:1405−1470?)とされる。おそらく、作者禅竹は、この「草木国土悉皆成仏」を言いたいがために、この作品を書いたと考えられる。 7 日が沈み、かがり火は、能舞台を浮かびあがらせている。ふと金色堂の佇まいが気になり、白山神社の真っ直ぐな参道を南に歩いて、金色堂に向かった。目が闇に慣れ、金色堂が薄暗がりの中で、微かに光を放っている。尖塔の上には、夕陽の残り日が青白く見えた。この奥に、奥州平泉が栄華を誇った百年を牽引した四代の御霊が眠っていると考えると、背筋が震えた。 奥州平泉が、滅亡して八百有余年、中尊寺は、さまざまな困難に直面しながらも、初代清衡が中尊寺供養願文で掲げた理念を守り伝えてきた。そこには歴史としてはけっして語り伝えられていない人間ドラマがあったに違いない。中尊寺白山神社に伝えられる薪能も、そんな奥深い歴史文化の象徴のひとつだ。そのことを考えると、芭蕉が「兵どもが夢の跡」と表現したことの意味が、より深く、しかも身近に感じられた。 夏の夜やかがり火踊る白山社 ひろや 了 |
 白山神社能楽堂前からかんざん亭を見る |
 お能の休憩時間のかんざん亭 中尊寺薪能写真集 |