村山直儀「一ノ谷の義経」を描く
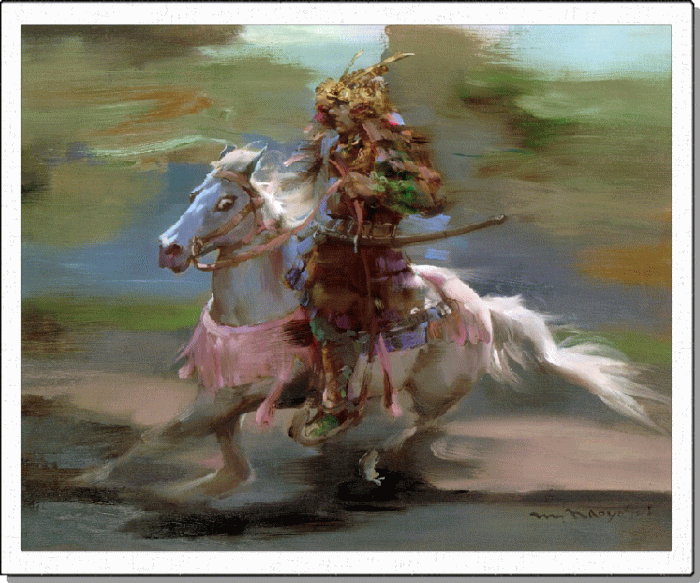
「馬上の閃き」
(村山直儀 油彩 20号 2004年)
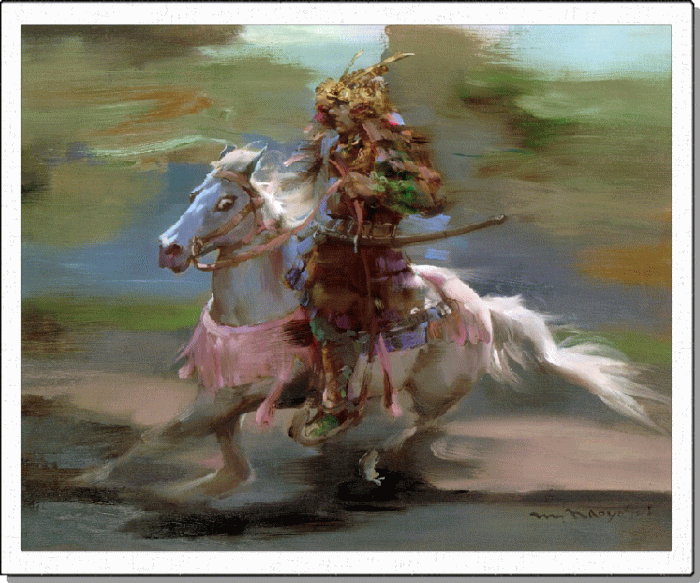
「馬上の閃き」
(村山直儀 油彩 20号 2004年)
村山のアトリエに行くと、何気なくこの画がソファーの背もたれの上に無造作に置かれていた。
猛烈な勢いで疾走する馬と武将。馬はまっすぐに正面を見据え、武将は、右手前方に目をやって何か を考えているように見える。太刀を差し、弓を持っているはずだが、動きの中で見えない。太陽は逆光で、おそらくは朝日。今まさに陽が昇ったばかりのよう だ。
「先生、これは義経さんですね」
「もちろん」
「それも絶頂期。一ノ谷ですか?!」
「そう逆落としの直前というところかな・・・」と言うなり村山はテーブルにあった缶のお茶を「ごくり」 と呑んだ。すぐに、想像の翼が、福原(神戸)の一ノ谷へ飛んだ。
次に私の脳裏に「孫子」の一節が浮かんできた。
「兵とは詭道なり」という言葉だ。もちろん中国の兵法書「孫子」の言葉だが、戦争の本質を鋭く突いてい ると同時に、源義経の軍事的才能を端的に語る時にぴったりくる。「詭道」の「詭」は、言(ごんべん)に「危」と表記する。意読をすれば、「せめる」、「いつわ る」、「たがう」とも読む。詭道は、「鬼道」にも通じると考えられる。だから「孫子」のこの一節は、「兵法とは敵が思いも掛けない戦術を仕掛けて勝利を勝 ち取る方法である。」となる。
考えてみれば、一ノ谷を館として万全の布陣していたの平家五万にしてみれば、義経はまさに鬼その ものであった。
一ノ谷合戦は、元暦元年(1184)2月7日に起こった。この日の未明、26才の義経は、一ノ谷 の平家を攻め落とそうと奇策を練っていた。それは平家の背後を奇襲によって突いて陣形を乱すことだった。彼は本隊を土肥実平らに任せ、自分は、秘かに一ノ 谷を前方に見下ろす鵯越に向かった。旧暦の2月と言えば真冬である。朝四時と言えば、まだ闇が辺りを支配している。それに猛烈な寒さであったろう。まあ、 それでも、鞍馬山や奥州の冬を経験している義経にとって、寒さは敵ではなかったかもしれない。
義経は、わずか気心の知っている精兵七十騎ばかりを引き連れ、闇夜の山中を平家が陣取っていた一 ノ谷の背後に到着する。そこで火を起こし、暖をとり、一息ついて、これから実行する策を部下たちに告げた。一同大胆な作戦に、武者震いをした。ゆっくりと 夜が明けて行く。そして次第に鵯越の地形が見え始める。目の前に見える断崖が予想以上に角度あり、兵たちは、とてもこれは馬で下れる坂ではないと思うが、 口には出せないでいる。
そうこうしているうちに、朝の6時頃、暁をついて、熊谷直実親子が先陣をついて平家の陣に「我こ そは武蔵の住人」と名乗りをして、攻め入ってゆく。実はこれは功を焦った熊谷の抜け駆けであった。平家の側は、これを義経の戦術と思ったのか相手にしな い。しかしこれをきっかけとして、そちこちで小競り合いが始まる。兵法によれば、相手が陣形を構えている城を攻めるのは、良策ではない。どうにか敵を城の 外に誘い出すか、陣形を乱すしかない。一進一退ながら慎重に戦をすすめる平家の有利はどう見ても動かない。
その動きをじっと高みから義経は見ていた。義経は、ふたつのことを考えていた。ひとつは、敵の陣 形のどこに穴があるかである。ふたつ目は、この坂の攻略である。何度も馬を使った山岳軍事訓練は奥州で経験していたが、これほどの険峻な下りは経験したこ とがない。義経も部下には漏らさなかったが不安がなかったわけではない。しかし義経は軍略を心得ていた。戦には時の勢いというものがある。勢いがあれば、 この程度の坂は克服できる。孫子の言葉に「勝者の民を戦わしむるや、積水を千じんの谷に決するがごときは形なり」というのがある。これを意訳すれば、「民 を戦に導くと時に、たまった水を深い谷底に一気に切って落とすようにすれば勝者になれる」ということになる。命もいらぬとの覚悟をもって、この坂を越えれ ば、戦の神は、我に味方し、平家の陣形は崩れ、源氏は勝利者となる。そんな確信が義経にはあった。問題は逆落としのタイミングである。実際に、何度か、逆 落としのコツを兵に示しながら、シュミレーションを繰り返す。やがて陽は瀬戸内の海から昇ってきた。この村山の画は、その時の義経の雄姿である。
義経の声が、画の中から聞こえてきたような気がした。
「よいか。怖れるな。馬は心得ている。人が怖れれば馬も怖れる。このように手綱を引いて、我に続け」義経は、こうして鵯越の坂を、先陣を切って落ちて行ったのである。
村山の新作は「馬上の閃き」と名付けられた。義経は、馬の上で、戦いながら、策を思いつく。それ はこれまで誰も考えなかったような策である。このような義経の閃きの瞬間を何故、村山は画にしたのか・・・。
2004.08.06 Hsato