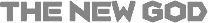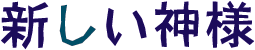
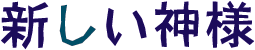
「山形新聞」―「山形ドキュメンタリー映画祭99」検証・『個の視点』―(1999.11.02)
「映画で自分が初めて肯定された。土屋さん(土屋豊監督)が私を必要としてくれた。それで満足。これまで、自分が必要とされていると思ったこと、一度もなかったから・・・」。フィプレッシ賞(国際映画批評家連盟賞)特別賞を獲得した「新しい神様」(日本、一九九九年)の主役、雨宮処凛(かりん)さんはしみじみ語る。 レンズは、民族派パンクバンドでボーカルを務める彼女を追う。だが、テーマの軸は彼女の思想ではない。二十四歳の彼女がビデオ日誌風に語る「自分探し」だ。「小中学校ではいじめられ、自殺願望があった。皆から否定され続けた」という少女時代の原体験。二十一歳のころ、偶然、民族派の小説家にデートに誘われ、行ってみたのが超国家主義団体の集会だった。 心のよりどころが見つからない時、「充実できればなんでもよかった」と振り返る。ただ、依存する対象が「ファッションやお金じゃ安易すぎる」と考えていたし、今の日本はちょっとおかしい、と疑問は感じていた。このころ、「平成のええじゃないか」という催しを自分で企画したりもした。元オウム真理教信者、在日コリアン、病院を告発する精神病患者・・・。多種多様な人が集まった。 天皇という“巨大”な存在に精神を依存することで、一種の安心感を得ていた雨宮さん。映画の中で、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を訪問する。今度は故金日成主席という、北朝鮮では絶対的な存在に傾倒し始める。 この作品、「テレビの電波少年シリーズみたい」とよく評される。監督からビデオカメラを借りた彼女が、毎日のように一人、その前で自分の内面を告白するシーンが延々と続く。その中で、何かに依存することの安易さに気付き始めたように見えるのだが・・・。 映画の最後に近づき、土屋豊監督が「私にとって(雨宮さんは)必要な存在」とはにかみながら言う場面がある。これが、彼女にとって重要な意味を持ったのは確か。しかし、依存の対象が新たに見つかった−そういう意味ではない。映画祭デイリーニュース班から、「貴方にとって今の教祖は誰ですか?」と質問を受けた時、「土屋さんじゃない。最初はそうかと思ったが、違う。(教祖は)自分自身だ」と答えた。 ピンクの文字で書いた「主演女優賞 雨宮処凛」のたすき、首にはファンにもらった千羽づるを下げ、日の丸の扇子を手に、映画祭会場を歩く。期間中、そのファッションは関係者を驚かせた。それ以上に、彼女の生きざまに共感した若者達がサインを求める姿が、会場のあちこちで目立った。 「今は民族派にも以前程興味がない。今回の作品で自分を見つめ直し、『これでいいんだ』と思った」、「今は精神的に楽。自然体。」否定され続けて自分に自身を喪失した第一段階、大きな存在に依存して安心を得た第二段階を経て、こう話す彼女の人生は今、自己を確立する第三段階に入りつつあるのか。 自分探しをテーマにした作品が、明らかにこの映画祭の主流になった。「若い人たちの作品は、みんなそうだろう」と語るのは、今回製作集団CINEMA塾を率いて参加した原一男監督。かつて「極私的エロス・恋歌1974」で、集団から「個」へと、日本のドキュメンタリーの歴史を変えたといわれる彼があえて今、「日本の作品は爛熟(らんじゅく)期を過ぎて、エネルギーを失っているのではないか?」と主張。自ら作ったはずの現在の流れに一石を投じ始めた。 |