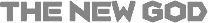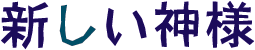
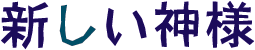
「インパクション116」―本日も日本国、ヘドが出るほど平和です―(1999.10.30)
なんか、維新赤誠塾という「右翼バンド」をやっている雨宮さん(24歳位の女の 人)と同じバンドメンバーの伊藤さん(同い年位の男の人)と監督の土屋さんの3人 をめぐるドキュメンタリーなんだけど、雨宮さんが自分でカメラを回してしゃべって いるシーンが半分を占めてて、それがすごくいきいきしていて、全然「バリバリの右翼パンク少女」という感じじゃなくておもしろかった。 彼女はこの映画の中でしきりに「自分なんてものはまったくない」と言っていて、だから「天皇陛下がいなくなったら私は困る、生きていけないもん。あなた(土屋監督)には必要ないかもしれないけど、私には必要なのー!!」と叫んでいる。でもね、それが私には不思議だったんです。だって彼女は本当に自分の言葉でちゃんと人と語れる人なんです。それなのに、どうしてそんなに「自分がなく」なっちゃってるのかしら? いじめられて「自分の人格が全て否定されるような」体験をもっている彼女は、自分と「社会との接点」が見いだせなくてあせっていて、でもポッカリ穴があいているようでどうしていいか分からなくて(この辺は私も共鳴できる感覚は持っていました)、精神的に追いつめられていた時に「民族派」と出会って、「これだー!!」ピカ ーンとそれまでのモヤモヤがウソのように晴れたんだと言っていた。学校とか職場とか狭い「社会」の中でずっと居場所がなかったのが、「民族派」と出会ってそれが初めて自分がいられる場所だったんじゃないかって、これは監督が言っていた言葉かな。 雨宮さんは「『民族』とかっていわれたら大きくてみんな居られるじゃない、自分の居場所が確認できる」そうで、でもその「民族」とか「天皇陛下」を必要としているのは彼女にとって「物語としての」なんだよね。だから彼女にとっては三光作戦がどうだ、とか従軍慰安婦のことはどう考えるんだ、と問い詰められても「そんなことはどうだっていいこと」なんです。彼女が言っている「天皇陛下」とか「民族」とかいう言葉は、「お国のために天皇陛下のために”民族”が一致団結して命を捨てていった」というような「物語のための物語による物語の言葉」でしかないんだから、彼女はそれを自覚しているし、そうやって物語に依存している自分を知っているからこそ「自分なんてない」ことになるんだろう。 それに比べて伊藤さんは、彼女のようには「物語」として割り切って「民族派」をやっているわけではないようにみえた。「今の時代は一生懸命何かする人がバカにされて情けない男みたいに思われる」「一生懸命に戦って、命を捨てるのが英雄だった時代に生まれていれば、自分も英雄になれていただろう」と言う彼は、神聖な場所である靖国神社ではしゃぐ雨宮さんに怒って撮影途中で帰ってしまったりしたらしい。 その「英霊」がけっこう彼と彼女を隔てているんじゃないのかな。 ともあれ、そんな2人をどちらかというと「左」である監督が出会って語り合って、だんだんそれぞれが親近感、信頼感(そして恋心?)を持つようになっていってる 、人と人とが関係をもっていくこと、変容していくこと、のドキュメンタリーだと思う。 上映会後のトークで「撮り終わった感想は?」と聞かれて、「いやぁ、今は土屋さんと結婚したいです」なんて言っている雨宮さんは主演女優賞です(本人がそういうタスキをかけていた)。 (加納穂子) |