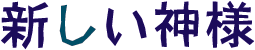
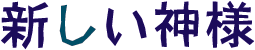
「週刊プレイボーイ」(2000.08.09)
まず初めに、この作品は実にポップな青春映画であると前置きしておきたい。なんだか怖そうな政治的映画だな、なんて思われたくないのだ。 主演の雨宮処凛、そして伊藤秀人は某右翼団体に所属し、維新赤誠塾という右翼パンクバンドを組んでいる。ふたりともバリバリの国粋派、天皇制の支持者。かねてから天皇制に疑問を感じていた監督・土屋豊が彼らと出会い、その日常をデジタルビデオでスケッチしていく。筋書きもシナリオもないまま、劇映画じゃないビデオレターが綴られる。「ギリギリの気持ちで作ったビデオレターですね。マスの最大公約数にではなく、見てくれるひとりひとりに話しかけるように作ったつもり」 三人はちょくちょくポテトチップとビールを片手に互いの考えを語り合う。日本の国体について。象徴としての天皇制の是非について。 雨宮の個性が実に可笑しい。ハジけている。よど号事件の犯人達に会いに彼女は北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)に行くのだが、空港に見送りに来た監督に、「拉致されたら助けに来てね〜」。 笑いとイデオロギーと、いつしか生まれる微妙な三角関係。その三つを柱に物語は進行していく。 「思想の勉強量を競うような会話は編集で省いた。二人の思想のその裏にあるものを探していくと、伊藤さんだったら、一生懸命に生きている人を笑うような社会の風潮が許せないと言う気持ち。雨宮さんなら、もともとすがるはずの自分なんてないから究極的に信じられるものを求めているという告白。考え方が違っていてもふたりのことを好きになっちゃって、どうしたら偏見を持たれずに彼らを紹介できるのだろうかと考えました」 軍服姿の、一見、エキセントリックなカップルの心根が初めて、彼らの胸の内の空虚感は現代の普通の若者と同種のものだと気づく。高度資本主義にがっちり守られて、娯楽はあるが哲学がない。安全だけど退屈。無力とニヒリズムの支配。3人はその中でもがいている。だからこそ大衆的(ポップ)。だからこそ胸を打つ。 「ニヒリズムはもちろん僕の中にもあったけど、今はこの映画を見てくれた人から様々な感想が届く。こんな僕でも誰かの気持ちを揺らせられることを知った。今は虚無を感じませんね。」 (長谷川博一) |
![]()