 リクガメを飼育する場合、太陽光は重要なはたらきをします。常に直射日光に当てられる環境であればよいのですが、住環境や季節によっては必ずしもそうは行きません。そのような場合に太陽光の代用品として飼育者が頼るのが人工照明です。リクガメ飼育に使われる人工照明には、フルスペクトル蛍光灯、白熱電球、あるいは紫外線灯など色々なものがありますが、ここでは、それぞれの照明器具の発光原理から放出光の特性、それらがリクガメに及ぼす影響などについて分かっている範囲でご紹介したいと思います。
リクガメを飼育する場合、太陽光は重要なはたらきをします。常に直射日光に当てられる環境であればよいのですが、住環境や季節によっては必ずしもそうは行きません。そのような場合に太陽光の代用品として飼育者が頼るのが人工照明です。リクガメ飼育に使われる人工照明には、フルスペクトル蛍光灯、白熱電球、あるいは紫外線灯など色々なものがありますが、ここでは、それぞれの照明器具の発光原理から放出光の特性、それらがリクガメに及ぼす影響などについて分かっている範囲でご紹介したいと思います。
 リクガメを飼育する場合、太陽光は重要なはたらきをします。常に直射日光に当てられる環境であればよいのですが、住環境や季節によっては必ずしもそうは行きません。そのような場合に太陽光の代用品として飼育者が頼るのが人工照明です。リクガメ飼育に使われる人工照明には、フルスペクトル蛍光灯、白熱電球、あるいは紫外線灯など色々なものがありますが、ここでは、それぞれの照明器具の発光原理から放出光の特性、それらがリクガメに及ぼす影響などについて分かっている範囲でご紹介したいと思います。
リクガメを飼育する場合、太陽光は重要なはたらきをします。常に直射日光に当てられる環境であればよいのですが、住環境や季節によっては必ずしもそうは行きません。そのような場合に太陽光の代用品として飼育者が頼るのが人工照明です。リクガメ飼育に使われる人工照明には、フルスペクトル蛍光灯、白熱電球、あるいは紫外線灯など色々なものがありますが、ここでは、それぞれの照明器具の発光原理から放出光の特性、それらがリクガメに及ぼす影響などについて分かっている範囲でご紹介したいと思います。
●太陽光の役割と人工照明
リクガメに限らず多くの生物は、太陽の恵みを受けて生活しています。地上にさんさんと降り注ぐ太陽光は、私たち生物に「明るさ」「色」「温度(暖かさ)」等々、実に多くのものを授けてくれます。リクガメは昼行性の爬虫類です。彼らにとっての太陽光の役割とは一体何かと考えてみますと、大きく分けて次のようなものがあるのではないかと考えられます。
1)視覚世界(明るさ/色など)を与える。
2)温度を与える。(体温を上げる)
3)ビタミンD3を合成する。
4)病原菌などに対する殺菌作用。
5)その他(今だ明らかになっていない効果)
中でも、2)3)はリクガメを飼育する場合の重要なファクターとなります。
ご存知のようにリクガメは爬虫類(変温動物)ですので、自ら体温を作りだすことができません。体温を維持させるには膨大なエネルギーが必要になってきます。エネルギー源となる食糧が乏しい自然環境の厳しいところで生き延びるために、リクガメ(爬虫類)は自ら体温を持つことを捨てたと言われています。それにより、少ないエネルギー(食糧)を効率よく利用し生命活動を維持していると考えられています。その代わり彼らは太陽熱で体温を常に調節しなければならないのです。リクガメは日溜まりで日光を浴びることにより、夜の間に冷えてしまった体温を上昇させているのです。太陽の下で日光浴をしている彼らは、太陽の熱エネルギーを利用して体温を維持しているわけです。
リクガメにとっての日光浴には、もう一つ重要な役割があります。これが【ビタミンD3】の合成です。ビタミンD3は、健康な骨や甲羅を育てたり、維持したりする上での重要なはたらきをする物質です。ビタミンD3の生理的作用の詳細については分かっていないことも多いのですが、腸内でのカルシウムの吸収を促したり、血清中のカルシウムとリン酸濃度を高めたりするはたらきがあるようです。いずれにしろ、ビタミンD3が欠乏しますと、成長期のリクガメではクル病になり、骨や甲羅が変形したり、後ろ足を引きずったりするなどの症状がでます。成体のリクガメでも骨や甲羅が柔らかくなるなどの異常を起こします。このビタミンは自然下では食べ物から直接取り入れられるのではなく、リクガメの体内で合成されています。この合成に深く関わっているのが紫外線の中でも特に【UVB】と呼ばれている波長のものです。動物の皮膚には、アセチルCoAより生合成されたプロビタミンD3(7ーデヒドロコレステロール)というビタミンD3の先駆物質が分泌されます。このプロビタミンD3がUVBの照射により活性化されビタミンD3になるわけです。ですので、リクガメを飼育する場合、紫外線(UVB)に当てることは大切な意味をもってきます。(これ以外にも、ビタミンD3を含むカルシウム剤を食事に添加することにより経口的にビタミンD3を補給するという方法もあります。ただ、リクガメにとっての必要ビタミンD3量などが正確に把握されていない状況では、逆に過剰症を起こすケースもしばしば報告されていますので、十分に注意が必要ですし、日光浴によりビタミンD3を活性化する方法の方が無難と言えます。)
屋外や直射日光がある程度当たる屋内で飼育をする場合には、自然光の恩恵に預かれるわけですが、太陽の光があまり当たらない屋内飼育がメインになる飼育環境では、この太陽光の役割を担ってくれる何らかの人工照明が必要になってくるわけです。
そんな幾つかの理由から、リクガメの飼育者は照明器具には大抵関心が深くなります。また、有効なライトを探し求めることになります。ここでは、ベース照明および紫外線(UVB)の補給源としての【フルスペクトル灯】と熱源としての【ホットスポット灯】について考察してみたいと思います。
●太陽の光
太陽の光をシミュレートするといっても太陽の光自体がどういったものかをある程度把握しておく必要があります。
法線面直射照度というものがあります。これは太陽の方向に正対する面の直射光による照度ですが、大気圏外法線照度(142000lx)、太陽高度と大気透過率によって定まります。これと、やはり天空光(拡散光です。)との合計で、自然界のある場所の照度を考えられます。これを昼光照度といっています。目安として、色々な天候時の太陽高度90度の(真上に太陽がある場合のことです)昼光照度をあげておきますと、
可視光線以外の紫外線について見てみます。
こうして太陽光をみてみますと、人工照明に比べて
といった特徴があることが分かります。
●キーワードについての解説
1)紫外線
話が少し逸れましたが以上のことをまとめますと、光は電磁波の中の人の目に見えるごく一部の波長域のものを指すということです。太陽を発生源として地上に届く電磁波を、波長の短いものから長いものへ順番に【紫外線】【可視光線】【赤外線】と呼んでいます。ですので、普通に光と言うときには、この可視光線のことを指しているわけです。電磁波としてはその他に、赤外線よりもさらに波長の長いマイクロ波や電波、紫外線よりもさらに波長の短いX線やガンマ線などがあるわけです。
リクガメを含めて爬虫類の飼育においてよく問題にされる光のうち紫外線というのは、その波長が380nm以下の光ということになります。紫外部は化学線とも呼ばれ、殺菌作用や化学的作用があります。(一方、赤外線は熱線とも呼ばれ、熱エネルギーを受熱面に与えます。)紫外線はさらに次の3段階に分類されています。
一般的に紫外線と一括りにされていますが、細かく見ていきますと上に挙げたように分けられ、それぞれでリクガメに与える影響が違ってきます。ビタミンD3の活性化に関与しているのは上記のうちのUVBです。また、ビタミンD3のうち60%は、波長が290〜300nmという極く狭い波長域で合成されるという計算結果も報告されています。UVBは、ビタミンD3を活性化させるという点では有益な紫外線とも言えますが、同時に生体にとって有害な働きもしますので、過剰に照射しますと危険であることを十分意識しておくことも大切です。290nmよりも波長の短いUVCは、地上20〜25kmにあるオゾン層に吸収されてしまい地上には届きません。UVCが生体に与える影響としては、有機体に選択的に吸収され突然変異の誘発、細胞分裂の阻止、細胞の破壊などを起こすことが挙げられます。具体的には例えば殺菌作用を持つということです。UVAが爬虫類に与える影響はまだはっきり分かっていませんが、ある種のトカゲの繁殖行動などに影響するなどの報告があります。まだ研究中の分野ですが、地上に届く太陽光にも含まれている成分ですので、飼育下でも同様のバランスで照射させた方がよいと考えるのが自然かもしれません。
2)色温度
それ以外に目安になるものとして、全光束、スペクトル分布、配光曲線、直射水平面照度などの項目をあげることができます。あまりあてにならないなどという批評をされる方もおいでですが、そのライトの性質を把握するのには、それぞれきちんと役にたつ項目ですので、注意して見るとよいでしょう。様々なメーカーに照明器具やランプのカタログを請求するとカタログを送ってもらえます。有料の場合もあります。それらのカタログなどを見ますと、これらのデーターが載っています。もっとも個人で光の様々な諸性質をきちんと調べられる装置を所有している方なら自分で調べればよいのですが、一般の飼育者はそれらのカタログデーターをある程度たよりにそのライトの性質を把握することになります。数値の意味と見方を把握しましょう。
4)全光束
●フルスペクトルライトとは
リクガメの飼育をはじめた方であれば、【フルスペクトルライト】という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、いったいどのような意味なのでしょうか。
フルスペクトルライトという言葉が使われ出したのは、Duro-Test社の Vita-lite(日本での商品名True-lite)が発売されて以来です。True-liteはすでに御存知の方も多いように「そのライトから出る光の成分をできるだけ太陽光線に近づける」ことを目標として設計されたということになっています。もちろん爬虫類の飼育のために作られた訳ではありません。古くから医療機関などでも使われました。自然光の下で物を見るのと近い色合いで物が見えるということで、色を大切にしなくてはならない職種でも使用されておりますし、学校などで採用した結果、生徒の学力向上に効果があがったなどの報告もあるようですが、いずれにしても人間のために開発されました。
現在ではいろいろなメーカーが、フルスペクトルライトですといって販売しているライトがすべて同じ基準を満たしているということはまったくありません。中には「可視光線」の範囲での分光スペクトル分布のみが、太陽光に似ているということで、紫外線など出していなくてもフルスペクトルライトと名付けているライトもあります。また、非常に分光スペクトル分布が、ある波長にかたよっている(たとえば、UVAを集中的に放射する蛍光灯)ライトであっても、つまり太陽光とはかなりスペクトル分布が異なるけれども、バランスはどうあれ、紫外線域までの波長の光を放射しているということで、フルスペクトルライトだといっているライトもあります。またそれを爬虫類の飼育用に最適といって販売しているメーカーもあるわけです。
フルスペクトルというのは科学的に厳密に定義されている専門用語ではありませんが、True-liteが発売された当時に使われていたた「フルスペクトルライト」という言葉は、以下の3つの条件を満たすライトを指していたと思われます。
1)については、可視光線の範囲を越えて、特に紫外線のUVBの波長帯の光までの光を放出するライトがリクガメ飼育のためのライトとしては有効といえるでしょう。
リクガメの飼育において有効なフルスペクトルライトとは、
1)可視光線に加え、UVBまでの紫外線を放出できる
といってよさそうです。
●市販されているライトの種類
●放射熱によるライト
●放射熱によるライトはUV-Bを放射できない理由
熱放射によるエネルギーですから、放出されるエネルギーの大半は熱です。電磁波では、当然熱線が主体です。しかし、波長が短い光は、そもそも放出するのが大変です。可視光線の波長帯の光でも赤っぽい光は比較的放出できますが、青っぽい光はかなり僅かしか放出されません。可視光線の波長帯の380〜750nmの光が全放射エネルギーのどれぐらいを占めるかともうしますと、わずか4%だけです。96%のエネルギーは光としては役に立っていないのです。そのほとんどが熱エネルギーとして放出されているわけです。
●放電によるライト
●放電によるライトの発光原理
●リクガメ飼育のための蛍光灯を考える
蛍光灯の一般的な性質を少し書いておきます。蛍光ランプの光束は、時間の経過とともに減少します。初めのうちはかなり大きく減衰します。1年たったら取り換えるのがよいでしょう。効率がかなり落ちてしまいます。
日本国内においては、照明器具のメーカーは、可視光線の波長よりも短い、紫外線の放射に関しては、かなり気を使っています。
●HIDランプ
●おわりに....
この場合の人工照明の役割として期待されるものは、あくまで太陽光の代用であることを念頭に入れると、上記の1〜5のようなものと考えられます。
他にも、ライトの点灯・消灯によって、屋内で飼育されているリクガメにとっては、一日のリズム/サイクルが感じられるようになります。このサイクルのことを「フォトピリオド」とも言い、これを適正に再現することにより、リクガメのバイオリズムを適正に保つことができ、また、長期の健康維持や繁殖などをうまく行なうための一つのカギとなっているという報告もあります。
可視光線の明るさで捉えるのならば、照度で考えるのが分かりやすいでしょう。照度は単位時間当たり受照面の単位面積当たり入射する可視光のエネルギー量をいい、単位はlx(ルクス)をつかいます。
日照あり、晴天 120000lxから130000lx
日照あり、薄晴れ 100000lxから120000lx
中間時 70000lxから100000lx
日照なし、薄曇り 35000lxから 70000lx
日照なし、雨曇り 12000lxから 35000lx
といった具合です。
ちなみに一般的な部屋などの明るさの数字を合わせてあげてみますと、
事務室(設計、写植)病院(剖検、救急処置)
など特に明るさが必要な部屋 1500から700lx
一般事務室、手術室、一般商店 700から300lx
学校教室 300から150lx
程度です。比較するとわかりますように、現在御自分の職場などで、もし陽も照っていない雨の日の太陽光と同じ程度の明るさを照明器具だけで得るためには、現在付いている照明器具の高さを変えないとすれば、およそ50倍程度の本数の照明器具を取り付ける必要があることがわかります。
もし、陽の照っている晴れの日の明るさを確保しようとするならば、なんと250倍程度の本数が必要です。(実際はある場所での光束密度の問題であるため、50倍から250倍の密度で照明器具を設置しなくてはならない訳です。)おおむね建物の設計段階では、上記の照度を目安に設計されているからです。
太陽光のUVBの照射量のデーターを幾つかあげますと
マイアミ, フロリダ州 (北緯26度) 6月21日 正午 253 μW/cm2
メルボルン, オーストラリア (南緯38度)1月29日 265 μW/cm2
これに対して人工照明ではUVBの照射量は
Duro-Test 社 トゥルーライト; 20 W, (60 cm)
光源からの距離 15 cm 3.1 μW/cm2
光源からの距離 30 cm 1.1 μW/cm2
光源からの距離 45 cm 0.7 μW/cm2
光源からの距離 60 cm 0.5 μW/cm2
光源からの距離 75 cm 0.2 μW/cm2
Zoo Med Reptisun 5.0 /Iguana Light 5.0 ; 20 W,
光源からの距離 30 cm 10μW/cm2
といった数字です。
よって、太陽光と照明器具では、明るさやエネルギーの桁が違うと考えておいていただきたく思います。
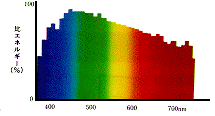 また太陽光のスペクトル分布がどのようなものかを知るために、6500Kの色温度における太陽光のスペクトル分布図を示しておきます。このように太陽の光にはムラがなくすべての波長の光をバランスよく放射しています。
また太陽光のスペクトル分布がどのようなものかを知るために、6500Kの色温度における太陽光のスペクトル分布図を示しておきます。このように太陽の光にはムラがなくすべての波長の光をバランスよく放射しています。
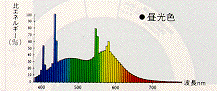 一般的な蛍光灯の昼光色といっているスペクトル分布です。ところどころに強い波長があります。やはり6500Kの色温度の蛍光灯のものですが、太陽光とはかなり違っています。
一般的な蛍光灯の昼光色といっているスペクトル分布です。ところどころに強い波長があります。やはり6500Kの色温度の蛍光灯のものですが、太陽光とはかなり違っています。
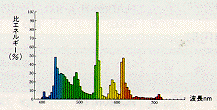 明るさと演色性をよくするために3原色の光の波長をそれぞれ強く発生するように調整した3波長域発光形の蛍光灯のスペクトル分布ですが、太陽光とはかなり違います。
明るさと演色性をよくするために3原色の光の波長をそれぞれ強く発生するように調整した3波長域発光形の蛍光灯のスペクトル分布ですが、太陽光とはかなり違います。
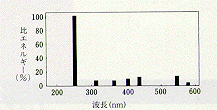 殺菌灯という名称で販売されているライトのスペクトルですが、特定の波長がとびとびに現れています。連続した波長の光を放射しているわけではありません。太陽光とはかけはなれたスペクトル分布です。
殺菌灯という名称で販売されているライトのスペクトルですが、特定の波長がとびとびに現れています。連続した波長の光を放射しているわけではありません。太陽光とはかけはなれたスペクトル分布です。
・明るさが明るい。
・紫外線の量が多い。
・可視光線、紫外線のスペクトル分布はゆるやかな曲線形状をしており、連続している。
フルスペクトル灯について述べる前に、まず、ライトの光の性質を知る上で、いくつかの指標となるキーワードの説明したいと思います。
私たちが利用しているエネルギー源としてもっとも重要なのは、何と言っても太陽光エネルギーでしょう。「光」というと目に見えるものを指しますが、光の仲間には目に見えない「赤外線」「紫外線」などがあり、これらを総称して「電磁波」などと言います。(広義の)光とは何か?という話を始めますと長くなりますので、ここでは端折って簡単に説明をしてみたいと思います。
「光とは何か?」という命題は、長く物理学の中で議論を呼んでおりました。古くはニュートンの「光は粒子である」とする粒子説やホイヘンスの「光は波である」とする波動説などがありますが、現在では「光は粒子と波の両方の性質を持ちあわせている」と考えられています。また、マクスウェルにより光は電磁波の一種であることも判明し、電場と磁場が直交する場を伝わっていくものとして考えられています。
各々の電磁波の境界となる波長ははっきりとしているわけではありませんが、紫外線と可視光線のおおむねの境は波長380nm(1nmは100万分の1mm)、可視光線と赤外線の境はおおむね780nmです。
太陽から地上に届く光の波長は290から3000nmであることから考えると可視光線の波長帯がとても狭いことを感じます。
・長波長紫外線【UVA】:320〜380nmの波長の紫外線
・中波長紫外線【UVB】:290〜320nmの波長の紫外線
・短波長紫外線【UVC】:290nmよりも短い波長のもの
また光の性質として波長以外に色温度という指標があります。光の色を現す指標で、赤っぽい光程色温度が低く、青っぽい光ほど色温度が高いといいます。単位をK(ケルビン)で示します。様々な光の色温度がどのようなものかの目安の図を示しておきます。
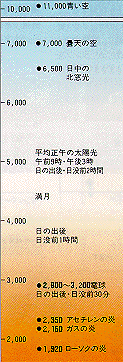 3)平均演色評価数
3)平均演色評価数
もうひとつの指標として平均演色評価数というのがあります。これは、一般的な色彩に対する色の見え方の良し悪し(光源の演色性の程度)を数値で表したものです。
基準光となるのは自然光で、ある特定の色を自然光で見た時を100としてそこから色ズレが大きくなる程、その光源の平均演色評価数が小さくなります。カタログなどでは(Ra)という記号で出ています。Ra=80とかRa=90とか書かれていると思います。ある色温度のRa=100というライトで、ある物を見れば、そのライトと同じ色温度の太陽光のもとで同じものを見たときと同じ色に見えるということです。
波長、光の色、太陽光との物の色の見え方のズレと3つあげました。よくライトのカタログに載っています。
全光束というのは、そのライトから出る光の絶対量を現します。lmという単位を使います。全光束という項目がなくても、ランプ効率(lm/w)という項目があればその数値からでもそのランプが出す光の量を知ることができます。これは大切な項目で、次に述べるスペクトル分布だけわかっても、絶対量が多いのか少ないのかわからなければ意味が薄れてしまいます。ランプ効率は、ランプが出す全光束とこれを発生するために消費されたランプ電力との比で示してあります。ほとんどすべてのランプには、消費電力は記されてあります。40W,60W,100W,などと書かれているその数字です。ランプ効率にその消費電力の数字を乗じてやれば、全光束が分かるというわけです。
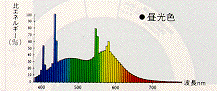 5)スペクトル分布
5)スペクトル分布
次にスペクトル分布ですが、グラフになっています。
大抵、横軸に波長がとってあり、縦軸に比エネルギーもしくは分光パワーといった
記載があり、単位を(%)としています。光の絶対量ではなく、どの波長の光を相対的にどのくらい出しているかを見るのに利用します。これはそのライトの演色性を確認するのにも使用します。
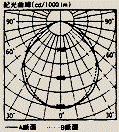 6)配光曲線
6)配光曲線
配光曲線は、そのライトから光が空間のどの方向へどれだけの強さ(光度)で出ているかを示すデーターです。図のようなグラフにして表します。配光の分布状態を曲線で示しています。
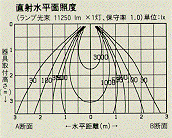 7)直射水平面照度
7)直射水平面照度
直射水平面照度のグラフは、かなり役に立つデーターです。器具の取り付け高さ、水平方向の離れによって照度がどのようになるか知ることができます。その器具を設置した垂直下方方向で、たとえば1mはなれるとどれ程の強さの光が当たるのかといった様子が示されています。
1)可視光線、紫外線とされる波長域の光を放出し、また
その分光スペクトル分布が昼間の太陽光のものと類似していること。
2)色温度が5500〜6800ケルビンであること。
3)平均演色評価数が90以上であること。
また、分光スペクトルが昼間の太陽光と類似しているというのは、2と3の項目と大変関係が深い話であり、
リクガメの飼育で
太陽光=昼間の(正午ぐらいの)太陽光の光
という意味で成り立つ項目と言えます。
実際の太陽光は、日の出から日の入りまで色温度は刻々と変化し、平均的には、日の出頃の1750Kから晴天の昼光である6000K程度まで上がって、また日の入りまで下がるということになります。
快晴の青い北の空などは12000K程ですから、その変化の幅は実際は大きい訳です。
よってできるだけ太陽光に近い光をシミュレートするとなれば日の出、日の入りの頃の時間帯においては、色温度が2000Kをきる程度まで下がり、お昼頃には6000Kまで上がる光を放出でき、かつそのすべての色温度においての演色性がよく、Ra=90以上であることが可能なライトということになりますが、そんなライトはありません。一つのランプで色温度を時間の経過とともに連続的に変化させられるライト自体がないので、昼間の太陽光の色温度を基準にしてその近辺でRa=90以上の光を出し、かつUVBを放出できるライトを選定するのが良いことになります。さらにランプ効率がよいライトを選定しないと電力ばかりくってしまって光の量が実際には少ないライトということになりかねません。
2)色温度が太陽光の白昼色に近い5000Kから7000K程であること
3)演色性がよくRaが80以上のもの(80以上を演色性が良いとしています)
4)スペクトル分布が太陽光と著しく異なっていないもの
では実際の照明器具とその性質を考えてみます。
まず、市販されているライトをおおむね分類してみると、
ハロゲンランプ
白熱電球
蛍光ランプ
コンパクト形蛍光ランプ
電球形蛍光灯
HIDランプ
といったものになります。
このうち、ハロゲンランプ、白熱電球は、フィラメントの発光を利用した光源です。フィラメントを高温に白熱し、その放射熱により可視光を放射させる光源です。ハロゲン電球は電球内に少量のハロゲン物質を含む不活性ガスを封入したもので、点灯中にフィラメントから蒸発したタングステンをふたたびもとのフィラメントに戻し、管壁を常に透明に保ち寿命を長くすることもできるようにしたものです。タングステンは地球上の全金属元素単体の中で最高の融点(約3380度)を持っていますので、フィラメントとして利用される訳です。ハロゲンランプ、白熱電球はいずれにしても、タングステンの熱放射による光を利用した照明です。赤外線反射膜をコーティングして熱線をできるだけカットするようにしたものや、バルブ内面がアルミニウムの反射鏡となっていて、下方への光の有効な照射をするようにしたレフ電球など、いろいろな種類の電球があります。色温度はハロゲンライトではおおむね3000K程です。平均演色評価数は極めて良好で、Raが100の白熱電球は数多くあります。しかし、ランプ効率はその構造上あまりよいとはいえません。
熱放射によって発せられる光は、赤外線から紫外線まで全波長域にわたる連続スペクトルの光を放射することが可能です。さらに条件がよければラジオ電波から赤外線、可視光線、紫外線、X線、ガンマ線にまで広がっています。太陽のエネルギーは熱放射といえます。では、ハロゲンランプや白熱電球はどうでしょう。タングステン線に変圧器を使って、流れる電流をどんどん増してゆくと、タングステン線の色が赤(600℃)〜黄(1100℃)〜白(1300℃)と変化してゆきます。高温になる程、短い波長の光を多く放出できるようになります。
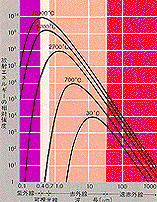 光源となるものの温度によって、その光のエネルギーが最大になる波長が決まってきます。ちなみに太陽光のエネルギーが最大となる波長は約500nmです。人間の眼の感度が最大となる波長は約550nmなので、人間の眼は太陽光のエネルギー分布によく適合していることがわかります。では、タングステンのフィラメントをみてみましょう。最高に熱して溶ける瞬前で3380℃です。どんなにがんばってもそれ以上の固体温度にはできません。さて、点灯させておける白熱電球の光の強さの最大値ですが、赤外線の領域の1100nmにあります。太陽に比べて、温度が低いので、エネルギー量のピークとなる波長帯が赤外線領域にずれます。
光源となるものの温度によって、その光のエネルギーが最大になる波長が決まってきます。ちなみに太陽光のエネルギーが最大となる波長は約500nmです。人間の眼の感度が最大となる波長は約550nmなので、人間の眼は太陽光のエネルギー分布によく適合していることがわかります。では、タングステンのフィラメントをみてみましょう。最高に熱して溶ける瞬前で3380℃です。どんなにがんばってもそれ以上の固体温度にはできません。さて、点灯させておける白熱電球の光の強さの最大値ですが、赤外線の領域の1100nmにあります。太陽に比べて、温度が低いので、エネルギー量のピークとなる波長帯が赤外線領域にずれます。
ピークの波長帯を離れると、放射エネルギーの相対強度は大きく減少します。熱放射によって強い紫色光を(可視光線のなかで、波長が一番短い光)出すための温度がどれくらいかともうしますと、ケルビン温度で3000Kの温度が必要です。摂氏温度ですと2726.85度ということになります。
紫外線となると、さらに高温を必要とします。ましてUV-B以下の波長帯の光は熱放射で放出するためには4000K以上の温度が必要になります。摂氏にすれば、3726.85度程です。地球上のすべての元素のなかでもっとも高い融点をもっている炭素をみてみても、その融点は摂氏3600度です。よって地球上のどんな固体をフィラメントとしてつかっても、熱放射で290〜320ナノメートルという波長のUV-Bは、放射できません。タングステンフィラメントは3380℃で溶けてしまいます。これより高温を地球上で作るのは、放電によりイオン化された気体中で可能となります(後述の放電管など)。
点灯してすぐにフィラメントが切れてしまう製品では意味がありませんから、白熱電球(熱放射によって発光するタイプの電球)では、3000Kぐらいまでの温度に押さえられていますので、紫外線の放射に関しては、ほとんど期待できません。電球の内部のフィラメントの放射熱により可視光を放射させる光源であるライトで爬虫類の飼育に有効であるという宣伝をしているものは、そのガラスに工夫が見られるものが多いようです。
色温度を上げるためにガラスに様々な物質を混入したり塗布して、昼光色に近い配光特性が得られるようにしているようです。ネオジムの酸化物であるNd2O3は、ガラスに赤紫色着色剤として加えられることはよく知られています。しかしガラスに色をつけるという手法であり、色付きのガラスは、220nm程度の紫外線まで透過する純石英ガラスなどと比べると、特性がどんどんズレることになってしまいますので、紫外線はますます出てこなくなってしまいます。ガラスが硬質ガラスであるライトではほとんど紫外線は出せません。
よってリクガメの飼育においては、フィラメントの発光を利用した光源のライトは主として熱源としての利用になります。光の色を操作してあるライトであれば、精神的な面では、効果が得られるかもしれません。
一方、蛍光灯やHIDランプなどは、気体を管球に封入し、電極間で放電を起こさせてその際発生する光りを光源としています。発光原理が前述のライトとは異なります。放電型のライトといいます。
HIDランプというのは、HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMP の略です。水銀ランプ、高圧ナトリウムランプ、メタルハライドランプの総称です。管球内のガス圧が10気圧程の高圧になっています。
簡単にその原理を説明いたしますと、低圧の水銀ガスを封入した管球の中に電極を設けて、電圧をかけます。陰極付近の電子が活性化し、放電します。電子を水銀ガスに放射すると、紫外線が放射されます。この紫外線を蛍光膜という膜(いくつかのルミネセンス物質でできています。)によって、可視光線に変換して光源とするのが蛍光灯です。
蛍光灯の管内には、低圧のアルゴンガスと水銀ガスが、主として封入されています。それ以外に封入するガスの種類と密度によって、また蛍光膜にするルミネセンス物質の種類によって様々な特性を調節しています。ルミネセンス物質というのは、外部から光(紫外線やX線などを含みます)や電子などをあてると光を放出する物質のことをいいます。たいていの固体や液体は、吸収された光のエネルギーは熱にかわりますが、ルミネセンス物質では吸収されたエネルギーは熱にはならず、ふたたび光として放出されるのです。その際に放出される光の波長は、吸収された光の波長よりも長い波長の光が放出されます。蛍光灯は色温度や演色性の調整がしやすい照明です。いろいろな特性を持つライトを作成することが可能です。
また、封入するガスの気圧をあげていくと、電子がガスにぶつかることによって、紫外線のみならず、可視光線も出すようになってきます。特別な蛍光膜を使わなくても、可視光線も出すようになるため、効率がよくなります。
HIDランプは発光部が小さく、輝度が高く、1灯当たりの光束が大きく、効率が高いという特徴を持ちます。商業施設、スポーツ施設などで使用されています。
放電型のライトは効率がよく、色温度を様々な設定にすることが可能で、さらにもともと原理的には紫外線を出しているライトですので、調整の仕方によって、太陽光をシミュレートしたライトが作成可能です。よってリクガメの飼育用のライトとしての使用を考えるとかなり有効なライトが作成できるはずです。
Duro-Test 社の Vita-lite(日本での商品名True-lite)や ZOO MED 社の REPTI SUN 5.0UVB, IGUANA LIGHT 5.0UVB などのライトは蛍光灯です。
フルスペクトルライトの老舗的存在のDuro-Test 社のVita-lite(日本での商品名True-lite)は、人間のための照明器具ですが、爬虫類の飼育者に愛用されてきたのはよく知られています。実際ごく最近まで、日本国内においては唯一使えるライトであったといってもよいでしょう。スペクトル分布も太陽光に似ていますし、紫外線量も生物に危険な程は放出せず、しかしUVBまで出ているライトです。
紫外線の照射量のみをもし問題にするのならば、蛍光灯のなかにも特徴的な製品もあります。
殺菌灯として市販されているライトは、254ナノメートル近辺の紫外線を大量に放出するものなどがあります。
またブラックライトという名称でいろいろなメーカーから出されているライトは、352ナノメートルの波長の紫外線を大量に放出します。ブラックライトを爬虫類の飼育用に使うということは、放出する紫外線の波長をきちんと理解すれば、意味がほとんどないことがわかります。このライトは、白をうきたたせるため舞台やディスコなどで演出用に利用されますし、宝石や金属の傷などを調べるのに利用されます。しかし化学的性質としてビタミンD3の合成には役立つことのない波長の紫外線ばかり出すライトです。
捕虫用のライトで350ナノメートル近辺の紫外線を大量に放出するライトなどもあります。
しかし、常時点灯しておいて、有害にならないようなライトでなければリクガメの飼育用には適しません。むしろ皮膚ガンの原因になったり、目の機能に障害を与えてしまいます。ビタミンD3の合成に有効なUV-Bも、その化学的な性質以外では、有害な面が大きい訳で、量が多く出ていればよいとはけっして言えません。
ある特別な波長帯の紫外線のみを大量に放射するというライトは、自然光とはまったく性質が異なる光ですから、リクガメにとっては害のほうが大きいライトであるといってもよいでしょう。化学的な性質においては影の薄いUV-Aも爬虫類の飼育という立場で見てみますと、太陽光には含まれている光ですから、活動を活性化させたり、微妙に生体の反応に影響を与えているとも考えられますので、太陽光を模した照明には、含まれていてほしい波長の光です。私達が入手できる安全なフルスペクトルライトはこのようにある程度限られているといってよいでしょう。
爬虫類の飼育用の照明というと、紫外線ばかりが取り上げられることが多いのですが、紫外線は生物にとって有害な波長の光であることを常に念頭においておきたいものです。
よって紫外線放出量が多い照明器具が飼育に適したライトとは言えません。バランスの問題といってもよいでしょう。
また、周囲温度に影響を強く受けます。ランプの明るさは、周囲温度が25度前後で最高になるように設計されています。低温になるにつれて急速に暗くなります。15度程度で約90〜95%、7から8度で80〜85%程の光束になってしまいます。光の明るさは光源からの距離に影響されます。リクガメの照明用としては40cm程度の距離を越えると、効果がかなり減ってしまうことを頭に入れておきましょう。
(店舗などで利用されているシステムで、光の色をある程度調整するシステムは、すでに商品化されています。色蛍光ランプというランプを使います。赤い色を出すランプと黄色を出すものと、緑を出すものにさらに白色のランプを加え、4本のランプをそれぞれの強さを調整してやることにより、赤みがかった色から白昼色、さらに青みがかった色と演出するシステムです。3000Kから10000Kまで調整できます。このシステムは高価ですので一般的ではありませんが、紫外線(UVB)まで放射する色蛍光ランプが作成され、商品化されれば、かなり質の高いリクガメ用照明が可能になりそうです。)
損傷の波長特性という指標があります。光エネルギーによる様々な物質への損傷の程度を考えているのですが、米国商務省標準局(N.B.S)が、セルロースのサンプルについて実験的に求めたグラフが現在広く使用されている特性です。
光の波長が短い方が、損傷度が高く、紫外線はひどい損傷度を示します。変退色を起こさせる波長の光という扱いです。ある照明器具を作成、販売したことによって、なんらかのトラブルが発生したときの責任問題を考えるとリスクが大きいため、できるだけ紫外線をカットする製品を作っています。
少しでも紫外線が出ているランプに関しては、注意書きが添えられ、かつそういったランプは(後述するメタルハライドランプなど)製品としては、そのランプと照明器具をセットにして販売し、ランプの光が器具の外に照射される前に、硬質ガラスや、紫外線吸収ガラスなどを光が通過するような構造の照明器具として販売しています。
なかなか国内産のリクガメ飼育に有効なライトが目に入らない理由です。もちろん海外においてもその事情は同じようなものです。ZOO MED 社がREPTI SUN 5.0UVB の販売許可を取るときに、紫外線の発生量としては、許可がとれる限界であったとコメントしています。
蛍光灯以外にフルスペクトルライトと呼べるライトはないのでしょうか。可能性としては、HIDランプに見つけられるかもしれません。紫外線の放出というポイントから考えますと、かなり絞り込むことができます。一般的ではないライトも含めれば、
水素放電管(168〜500nm)
キセノン放電管(200〜2000nm)
水銀ランプ
メタルハライドランプ
などがあげられます。普通に入手することが可能なものとしては水銀ランプ、メタルハライドランプでしょう。
水銀灯は、放電時の水銀蒸気圧によって、低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯の3種に分けることができます。
低圧水銀灯の一種に殺菌灯があります。また、高圧水銀灯は、高効率光源として、工場などの照明やスポーツ施設の照明などによく使われています。また超高圧水銀灯は水銀蒸気圧10〜200気圧、効率は40〜70lm/Wにも達します。
これも工場の照明や、道路の照明などに使われています。紫外線はかなり照射するのですが、光色に赤色が不足した光です。水銀灯を用いて昼光に近い光色を得るためには、白熱電球と高圧水銀灯の光をワット数の比で2:1の割合で混ぜると昼光に近い光色にすることができます。しかし、ライトの寿命や特性の違いから、複数のライトの混在で昼光色を得る方法はリクガメの飼育のための照明としては難ありです。
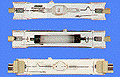 そこで登場するのが、メタルハライドランプです。このランプは、高圧水銀ランプの効率、演色性を改善したものです。水銀に加えて、各種の金属ハロゲン化物(メタルハライド)の発光を利用したランプです。演色性の良い(高演色形)と、発光効率のよい(高効率形)があります。スカンジウム、ナトリウム、ジスプロシウム、タリウムなどの金属ハロゲン化物を封入し、光色などを調整しています。
色温度は 2500K〜6000Kと様々なランプがあります。効率も50lm/W〜135lm/Wと各種そろっています。
そこで登場するのが、メタルハライドランプです。このランプは、高圧水銀ランプの効率、演色性を改善したものです。水銀に加えて、各種の金属ハロゲン化物(メタルハライド)の発光を利用したランプです。演色性の良い(高演色形)と、発光効率のよい(高効率形)があります。スカンジウム、ナトリウム、ジスプロシウム、タリウムなどの金属ハロゲン化物を封入し、光色などを調整しています。
色温度は 2500K〜6000Kと様々なランプがあります。効率も50lm/W〜135lm/Wと各種そろっています。
高演色形の HQIランプ は Ra = 80〜93 と自然光に近い演色性を持ちます。色温度が 4200K、 5200K、5600K、 などのタイプで HQI-TS(両口金タイプ)もしくは、MQDと呼ばれるランプは紫外線もUV-B波長帯まで照射しています。外管バルブにも石英ガラスが使用されており、発光管から放射される紫外線がそのまま外に出ています。定格ランプ電力も75、135、150、250Wとあります。全光束がすばらしく、20000lm程出ているものもあります。ちなみに40Wの蛍光灯の全光束は3000lm程ですので、光量が多いランプです。
メタルハライドランプという名前の電球すべてがUV-B波長帯まで照射しているわけではありません。たとえば、
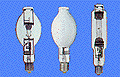 このような口金のタイプのメタルハライドランプは、外管バルブに硬質ガラスを使用したりして、できるだけ紫外線を外に出さないように設計されているものが多いのです。
光源色が昼白色のものを選択すれば前述の蛍光灯のフルスペクトルライトと同様にリクガメ飼育のための人工照明として利用できます。ただ、ランプとしては少し取り扱いに注意が必要になります。
このような口金のタイプのメタルハライドランプは、外管バルブに硬質ガラスを使用したりして、できるだけ紫外線を外に出さないように設計されているものが多いのです。
光源色が昼白色のものを選択すれば前述の蛍光灯のフルスペクトルライトと同様にリクガメ飼育のための人工照明として利用できます。ただ、ランプとしては少し取り扱いに注意が必要になります。
蛍光灯と同様に安定器が必要ですが、専用の安定器が必要です。また、ランプ自体は直接素手で扱うのは問題があり、手袋などを使用する必要があります。それは、指紋がついたり、油脂の汚れが付着したまま点灯しますと石英ガラスが失透(白濁)して寿命が短くなります。点灯方向にも制限があります。両口金タイプは平べったいランプ形状をしていますが、水平から±45°以内で使用する必要があります。これは封入してある金属ハロゲン化物が、電極を侵してしまうからです。値段も蛍光灯に比べると高価です。ランプ効率を考えると経済的ではあるのですが、いざ購入するとなると、ランプ自体が15000〜20000円、安定器が15000〜30000円、取り付け器具を含めるとダウンライト形で60000円程度から、またスポットライト形ですと85000〜110000円程度かかります。
その他にも幾つか注意すべき点がありますので、実際に導入する際には、メーカーの話などを注意して聞く必要があります。たとえば、紫外線を照射しているランプであるため、取り付け器具のうち、スポットライト形のものなどの製品では、カバーの部分に紫外線吸収ガラスを設置してあったりします。飼育用に利用するとなれば、そのガラスを取って使うようになりますが、メーカーはけして薦めてはくれない使用方法です。また、蛍光灯と違って、点光源に近いランプですし、高輝度であるため、常にリクガメの目に光源が入っているような設置の仕方をすると、危険であるケースも考えられます。
このようにリクガメ飼育のための照明について紹介してきました。今後、国内のメーカーによる爬虫類の飼育に効果的な照明器具の登場もあるでしょうし、外国のメーカーからも更に新しい器具が出てくるかもしれません。そうした状況の中で、私達飼育者としては照明器具の性能を正しく理解し、適切な使用ができる知識を身に付ける必要もあるでしょう。
またリクガメの個体差、普段の食事内容の違い、住環境などなどの違いもありますので、それぞれの状況に応じて臨機応変に最適な器具を選ぶとよいでしょう。