Graeca
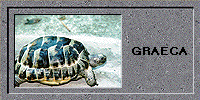
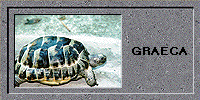
国内の飼育書などでは、一般的に、ギリシャリクガメはヨーロッパリクガメ属(Testudo)の中の一つの種として位置づけられています。また、ギリシャリクガメには、ギリシャ、イベラ、テレストリス、ザルドニィの四つの亜種がいるとされているのが一般的です。
しかしながら、ギリシャリクガメに関しては、まだ、その生息地の詳しい調査が行なわれている最中でありまして、その調査結果などから、従来からの分類法に対して、さまざまな異論などが唱えられるようになってきました。
うちにいるギリシャたちは、ひょっとすると、いわゆるギリシャリクガメ(Testudo graeca graeca )ではないかもしれません。
ギリシャリクガメの分類は、現在も研究者の間で諸説紛々としていて、現段階では大変に分かりにくいというのが正直なところです。それと言うのも、ギリシャリクガメはもともと非常に広範囲に分布していて、地域ごとの気象条件などにより、その大きさや甲羅の色合いや模様が多様化しているからです。この違いが、種の違いに起因するのか、あるいは、亜種か、地域変種なのか、まだ十分に調査研究されていないので、はっきりとは分かっていない状況にあるようです。
ここでは、その分類の歴史と現況をざっと紹介するに留めたいと思います。
ギリシャリクガメ(Testudo graeca)は、地中海リクガメ属に属します。中型のカメで、色合いは様々ですが、茶色や黄色の地色に、黒っぽい不規則な斑点模様がついている個体が多いです。環境にもよりますが、年齢とともに、全体的に色が黒くなり、模様も不鮮明になることが多いです。同属のヘルマンリクガメとよく似ていますが、臀甲板(尾のすぐ上の甲板)が、ヘルマンでは2つに分かれていることが多いのに対して、ギリシャは分かれていないことで区別できます。また、ギリシャでは、尾の両脇の太股のつけねに、円すい形の突起があることも、大きな特徴です。この突起は、ヘルマンには見られません。逆に、ヘルマンには、ギリシャでは見られない、尾の先端の突起があります。
ギリシャリクガメは、今のところ、以下の6つの亜種に分類するのが一般的です。
| 和名 | 別名 | 学名 | 主な分布域 |
|---|---|---|---|
| 1)ギリシャリクガメ | ムーアギリシャ | T.g.graeca | 北アフリカ、スペイン |
| 2)イベラギリシャリクガメ | トルコギリシャ | T.g.ibera | ギリシャ、トルコとその周辺 |
| 3)テレストリスギリシャリクガメ | アラブギリシャ | T.g.terrestris | イラン高原東部、アフガニスタン |
| 4)ザルドゥニギリシャリクガメ | イランギリシャ | T.g.zarudnyi | リビア、イスラエル、トルコ南西部 |
| 5)ニコルスキーギリシャリクガメ | - | T.g.nikolskii | カフカス山脈の南西部 |
| 6)アナムールギリシャリクガメ | - | T.g.anamurensis | トルコ南西部 |
上記のうち1)〜4)までの分類は、1946年にドイツの爬虫類学者ロバート・メルテンスによって提唱され、後の1958年にH.Wermuthによって修正が加えられたものです。最近になって、さらに5)、6)の2亜種を加えることが提言されています。
1)〜6)のうち、1)のギリシャリクガメのみが北アフリカに分布し、残りは、地中海東部域に広く分布しています。英国のカメ保護研究団体トータストラストの主催者であり、ギリシャリクガメをはじめ、地中海リクガメのフィールド調査や保護活動を長く続けている、アンディ・ハイフィールド氏は、既存のギリシャの分類に異論を唱え続けている学者の一人でもあります。彼は1990年以来、以下のような分類を提案しています。
−リクガメ科
−地中海リクガメ属 --(ホルスフィールドリクガメ)
--(ヘルマンリクガメ)
--(マルギナータリクガメ)
--(エジプトリクガメ)
--★グラエカ種(北アフリカに棲息する)
--★ザルドゥニ種
--★イベラ種
--T.i.ibera(本亜種)
--T.i.nikolskii
--T.i.anamurensis
−フルクラケリス属
--★F.nabeulensis(チェニジア産の小型種)
ハイフィールド氏の提案によれば、現在1つの種とみなされているギリシャリクガメは、2つの属、5つの種(★)に分類されることになります。同氏の主張をまとめますと、おおむね次の3つになります。
●北アフリカ産のギリシャ(T.graeca/以下グラエカ種)と地中海
東岸域中心に分布するイベラギリシャ(T.ibera/以下イベラ種)、
ザルドゥニギリシャ(T.zarudnyi)とは、それぞれ独立した別の
種とすべきである。同時に、ニコルスキーギリシャとアナムール
ギリシャは、イベラ種の亜種とすべきである。
●テレストリスギリシャという亜種の分類は、形態上の特徴や分布
域の記述が曖昧であり、小型で黄色みが強い個体を、なんとなく
すべてテレストリスとしている帰来がある。したがって、この亜
種は採用すべきではない。
●北アフリカには、グラエカ種(T.graeca)の他に、明らかにそれ
とは形態的に区別できるリクガメが存在する。これらは、地中海
リクガメ属とリクガメ属の両者の特徴を合せ持つと考えられるこ
とから、フルクラケリス属という別の属に分ける方がよい。こ
のうち、チュニジアに棲息する小型種をF.ナベウレンシス、アル ジェリアの大型種をF.ホワイティと分類するべきである。
【グラエカ種(Testudo graeca Linnaeus 1758)の特徴】
グラエカ種は、リビア、モロッコなど北アフリカに分布する種です。ごく少数が、南スペインやバレアレス諸島にも分布しています。1758年に、リンネによって初めて発見、報告されて以来、ヨーロッパでペットとして親しまれてきた種です。しかし、ペットとしての乱獲も一因となり、現在では、野生の個体数が非常に減っています。
学名のグラエカ(graeca)は、ラテン語で「ギリシャ」の意味ですが、これはギリシャに棲息するからではなくて、甲羅の斑点模様が、ギリシャモザイクに似ていることからついた名称です。
国内には、3年くらい前に、「テレストリスギリシャ」という名称で、多くの個体が輸入されていましたが、その中には、このグラエカ種が含まれていたと思われます。
グラエカ種の特徴としては、あまり大きくならないことがあげられます。オスで、平均すると、甲長12〜13cm、体重500gくらいにしかなりません。甲長15cm以上になることは、ほとんどありません。メスの方が大きくなり、甲長18cm前後で、体重1300gくらいまで育ちます。モロッコの野生個体では22cmというメスの記録があります。
また、甲羅の地色は、一般的には、明るい黄色で、甲羅の斑点模様は、こげ茶色や黒です。頭部や手足のウロコも、黄色みを帯びています。ただし、甲羅や手足の色は、棲息地や年齢、個体により、バリエーションがありますので、色合いだけで、必ずしも種の判別はできません。
甲羅は、ドーム状に小高く盛り上がっています。縁甲板の後ろの方が、フレアー状に広がるという特徴も見られません。まれに、ヘルマンのように、臀甲板が2つに分かれている個体もいるようです。イベラ種と比べて、手足が長く、顔つきも精悍だと言われています。性格的には、非常に神経質で、飼育環境が少しでも不適切ですと、体調を崩してしまう可能性があります。アフリカの沿岸部に分布する個体群は、乾燥に弱いことも知られています。リビアに棲息する個体群は、冬眠をしないことも報告されています。また、飼育下での繁殖例も非常に少ない種です。神経質な性格なため、攻撃的なイベラ種との同居は避ける方が賢明です。
【イベラ種(Testudo ibera Pallas 1814)の特徴】
1814年に、パラス(Pallas)によって旧ソ連で発見されたときには、独立した種(イベラ種)として分類されていましたが、後にメルテンスらによって、ギリシャリクガメ(T.graeca)の亜種だとされました。ここへ来て、また別種とする意見もあります。
グラエカ種と比べて大きくなる種で、オスで甲長18cm、メスで甲長20cmくらいになります。地域によっては、さらに大きくなることもあります。甲羅の形では、グラエカ種が、ドーム状に盛り上がっているのに対し、イベラ種は、横幅が広く、いくぶん扁平です。
甲羅の地色は、個体によって差がありますが、緑がかった茶色からオレンジがかった茶色です。甲羅の斑点は濃い茶色です。また、グラエカ種の第一椎甲板が丸みを帯びているのに対して、イベラ種のは角張っています。頭蓋骨の形も両者では異なり、イベラ種の方が鼻が幅広く、尖っておらず、目が大きいのが特徴です。手足も、イベラ種の方が太くて短く、骨格が両者でかなり違っていることが分かります。
また、ギリシャの特徴である太ももの付け根の突起の数は1つだったり、2つだったりします。棲息地によっては、後部の縁甲板が非常にフレアー状やノコギリ状になっている個体が見つかりますが、この特徴は、成熟したオスにおいて顕著です。
性格的には、攻撃的な個体が多いです。とくに成熟したオスは、非常に精力的でテリトリー意識も強いので、ほかの種との同居は避けるべきです。繁殖のためのペアでも、オスの執拗な求愛に、メスが参っていないか、常に気を配る必要があります。
また、イベラ種でも、ごくまれにですが、臀甲板が2つに分かれていることがあるようです。また、臀甲板の分かれていない親から、分かれている子が産まれることもあります。野生個体でも、この特徴を持つ個体がいるという報告もあります。逆に地域によっては、ヘルマンの12%が、臀甲板が2つに分かれていないことも、フィールド調査でわかっています。ですから、臀甲板が分かれているかどうかを、ギリシャとヘルマンを見分ける基準と考えることは、必ずしもできません。
これらの提案は、現在は、まだ専門家の間では一般的には受け入れられていないようですが、今後、DNAの分析や研究が進むなかで明らかになってくるものと思われます。
以上のように、ギリシャの分類は非常に複雑で、しかも、現段階ではどれが正論か決着がついていない状況にあります。普段、ギリシャと暮らしていく上では、どの種や亜種に属するのか、といったことは、取り立てて気にすることでもないかもしれませんが、例えば、繁殖を考える場合には、これは大きな問題となってきます。現在ひとつの種とされているギリシャリクガメが、実は複数の種に分かれるとすれば、ギリシャ同士でも、ペアによっては、うまく繁殖しないことになるからです。分類がはっきりしない現時点では、繁殖を考える場合は、なるべく色合いや甲羅の形状の似た個体をペアにするのが無難と言えるかもしれません。
また、購入したペットショップなどで、その個体の原産地を問い合わせたり、図鑑などの写真と見比べながら、種(あるいは亜種)を特定するのは意外と困難です。なぜなら、ペットショップへは必ずしも原産国から直接輸入されているとは限りませんし、また、個体の色合いや紋様、大きさなどは飼育環境に左右されることが多く、あまり当てにならないからです。