
総社の隣にある。いまにも朽ち果てそうだ。この寺の境内に三河国府の
正殿が眠っていた。
| 1.三河国 | 愛知県豊川市国府 名鉄本線国府駅 '96.6.19 '97.8.27 '02.06.01
06.04.08 |
三河国は今の愛知県の東半分である。豊田市を発して衣浦港に注ぐ境川の東、岡崎市、
豊橋市、安城市、豊川市、豊田市、刈谷 市などが現代の市街地である。
この国の国府は、名鉄本線急行で豊橋から名古屋に向かって2駅目に「国府」 という駅
があるので知れる。「国府」と書いて「こう」と読む。
| 三河国府跡(02.06.01,06.04.08) |
|
三河国府は平成3年(1991)から、13次にわたる発掘調査の結果、ほぼ全容が現れてきた。少なくとも、3回建て替えられたらしいことも判明した。8世紀の半ばから10世紀の中頃まで、この地に三河国府の国庁があったことが確認されたのである。
|
 |
| 曹源寺(06.04.08撮影) 総社の隣にある。いまにも朽ち果てそうだ。この寺の境内に三河国府の 正殿が眠っていた。 |
 |
 |
| 正殿跡 曹源寺の本堂。正殿跡が発掘された。 |
東脇殿跡 曹源寺の前の民有地から発掘された。 |
 |
| 前殿跡 前殿が発掘されたところは花畑になっている。 |
 |
 |
| 羊形硯出土品 | 羊形硯復元模型 |
| 羊形硯は三河国庁の東200mの地点から出土した。 平成12年(2000)の発掘調査で8世紀後半の遺構から発見された。 羊形硯は平城宮跡から2点、三重の齊宮跡から1点、岐阜県美濃加茂市 から1点の4点しか出土例がない貴重なもので、平城宮や齊宮跡から出土 したものと共通点も多く、愛知県の猿投窯産と推定されている。 |
|
 |
| 三河国府発掘現場(三河国府第13次調査報告書より) |
| 小野小町と三河 ところで貞観年間(860年代)に、文屋康秀が三河国の掾に任ぜられ、任地に向かう時に、 小野小町に一緒に行かないかと誘った。その時の小町の返歌が古今集巻十八にある。 文屋のやすひで みかはのぞうになりて、あがた見には えいでたたじやと、いひやれりける返り事によめる。 小野小町 わびぬれば 身を浮き草の 根をたえて 誘ふ水あらば いなむとぞ思ふ この時の小町は何才の頃だろうか。50才は超えていただろうか。小町は康秀の誘いにより、この三河の国府に来たのであろうか。その後の結果はどの古文書にも記載されていない。
小町ももちろん六歌仙の一人だ。古今集仮名序は
|
| 三河国総社 |
|
三河国府に隣接して、三河国総社がある。南北朝期の棟札に、総社五八社大明神宮とみえる。 |
 |
 |
| 鳥居 県社総社の碑が立つ。脇には地元の小学校のクラスが植えた花壇がある。 |
|
 |
| 拝所 社殿は垣に囲まれていて、垣の外から参拝することになる。狛犬に守られて堂々としている。 かたわらに村社本国総社の碑が立つ。県社に昇格前の碑であろう。 |
 |
 |
| 本殿 尾張造りの拝殿を持つかなり大きい建物だ。 |
国府遺構出土地 東側の林。国府の西脇殿が発掘された。 |
| 三河国分寺 |
| 三河国分寺は近年活発に発掘作業が実施され、ほぼ全容がわかってきた。 金堂、講堂を南北に配し、金堂の南に回廊を巡らし、回廊の西に塔を置いている。 |
 |
| 三河国分寺跡 |
| 寺域は180m四方で、築地に囲まれていたらしい。 平成13年の調査では、寺域の北側からも、律令期のものと見られる大型の遺構が発掘され、寺の経営地域として独立した部署(院)を形成していたのだろうと推測されている。 |
 |
| 現国分寺 この寺の本堂の下に天平の金堂が眠っている。天平9年(737)創建と伝える。 現存寺は確か曹洞宗の筈だったが、なぜか門前に南無大師遍照金剛の幟が はためいていた。真言宗に変わったのかしら。 |
 |
 |
| 現国分寺本堂 この下に古代寺院の金堂がある。 |
梵鐘 平安時代の作と思われ、銅製で 重さ678キロ。国の重要文化財。 |
公民館の隣に塔跡の碑があるが、説明版も無く、ただ荒れ果てたままである。
今後整備されるのだろうか。
 |
 |
| 塔跡の碑 | 塔の礎石 |
 |
 |
| 文化財保護用地 古代寺院の回廊の西南隅に 当たる部分にこの表示があった。 |
三河国分寺 ご住職が花がお好きらしく、 春の花が満開だった。 |
| 三河国分尼寺 |
| 三河国分尼寺の遺構は豊川市八幡町忍地に眠っていた。大正時代に忍地という地名から尼寺跡ではないかと発想して、最初の調査の鍬が入った。大正11年(1922)には隣接する国分寺跡とともに国の指定史跡とされた。 昭和42年(1967)から愛知県による本格的調査が行われ、平成に入って豊川市教育委員会が引き続き調査を進め、平成10年(1998)にほぼ全体の確認が終了した。平成11年(1999)から史跡公園への整備事業が始まった。 |
| 三河国分尼寺跡の整備がやっと終わり、史跡公園と資料館がオープンしたとの知らせを受けて、平成18年(2006)4月8日(土)訪問した。平成11年(1999)から6年がかりで、遺構上にあった清光寺を西に移転させるなど、かなり大規模な整備事業であった。 |
 |
| 復元された国分尼寺中門 古代遺構の上に復元された。国産のヒノキ材を使い、古代と同じヤリガンナで仕 上げている。朱塗りの柱と緑の連子窓が美しい。連子窓を有する回廊は複式回廊 で内側、外側両側を通れる贅沢な回廊であった。 |
 |
 |
| 金堂の礎石 基壇上に置かれた金堂の礎石。 中央に須弥壇跡がある。 本尊阿弥陀三尊像が安置されて いたはずだ。 この金堂の規模は国分尼寺としては 最大級の規模で、唐招提寺の金堂に 匹敵する。 |
鐘楼跡 金堂と講堂の間から発掘された。 左右対称に置かれ、西が鐘楼、 東が経堂だったと推定されている。 これは西の建物である。 桁行9m、梁行6mの礎石建物。 この遺構の上に清光寺の庫裏が あったため比較的良く保存されていた。 |
 |
 |
| 講堂の礎石 経典の講義などを行った講堂跡。 |
北方建物跡 倉庫か書庫か、尼房の裏から発掘された。 |
尼僧の定員は10人。みな三河国の有力豪族の子女達で、一人に4人ぐらいの従者が居たという。 尼房は講堂の北側に建てられた。彼女たちは東大寺の戒壇で戒律を受けたのだろうか? |
|
 |
| 三河国分尼寺史跡公園全景 尼房、講堂、金堂、中門が見渡せる。手前の板塀も寺域を囲んだ塀の復元である。 寺域は150m四方で、周囲を板塀で囲んである。 |
 |
| 三河国分寺(奥)と国分尼寺(手前)のイメージ図(三河天平の里資料館) |
 |
 |
| 三河天平の里資料館 平成17年(2005)に開館した。 出土品の展示や研究資料を提供 している。写真撮影可も嬉しい。 |
新井さん 親切に案内していただいた。 30名のボランティアが協力していると いう。 |
| 砥鹿神社(三河国一之宮) |
| 三河の一之宮は砥鹿神社(とがじんじゃ)である。 豊川インターを降りて北へ行くとすぐである。 主祭神は大己貴命。標高789mの本宮山上に奥宮がある。 |
 |
 |
| 鳥居 | 神門 |
 |
| 拝殿 折からの交通安全週間で、お祓いを受ける自動車が多く、 巫女さんは大忙しであった。 |
 |
 |
| 本殿 どうしても全体が見えない。 屋根が美しいのでどうしても見たくなる。 |
本殿 連子窓からレンズを入れて撮した。 檜皮葺流れ造りだ。 |
 |
 |
| 摂社えびす神社 主神大己貴命の子供の事代主神(えびす) と建御名方神(諏訪神)を祀る。 |
巨大なさざれ石 これは大きいさざれ石だ。 溶けた石灰石に小石が混じって固まったのが さざれ石だがこんな大きいのは珍しい |
| 豊川稲荷(おまけ2002.06.01) |
豊川稲荷は、日本三大稲荷として東京、大阪にも別院を持つ。
豊川閣妙厳寺と称する曹洞宗の名刹である。
稲荷というと、宇賀神を祀る神社というのが普通だが、ここは、
仏教の守護神、ダ枳尼真天を祀る仏寺である。

境内は3万5千坪。本堂は総檜造りの堂々とした建物である。
「ワンシラバッタニリウンソワカ」と真言を唱えておまいりすると、
悪事災難は除かれ、福徳知恵がさずかるという。
三河国地図
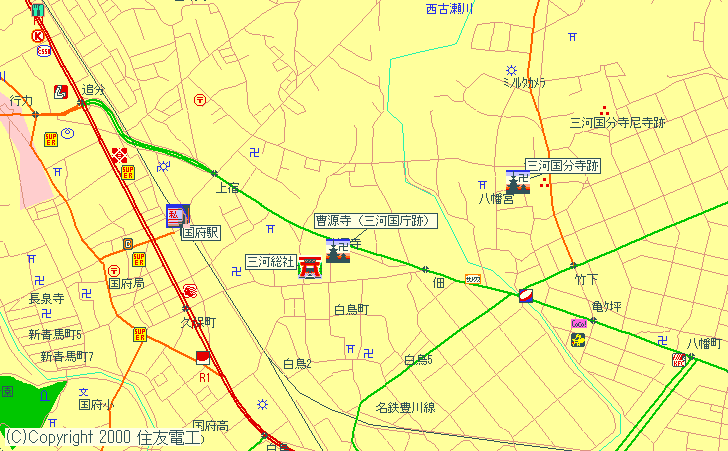
国府物語のトップページへ